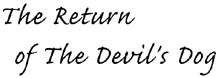Coral Fung -10
警察署から俺のフラットまでは少しばかり距離があったが、俺たちは互いの腰に腕を廻して片時も離れなかった。
彼は、古ぼけたソファの上に―俺の部屋に帽子掛けなんて気の利いたものがあるわけも無い。彼の行動は適切さ―被っていた帽子を置くと、俺の部屋をぐるりと見渡した。こんなフラットと彼の間に接点があったことなど無いのだろう。彼は窓際に立ち、通りに目を向けていた。
俺はフリードリヒの背後に回ると、その引き締まったウエストに両腕を回した。彼の体が一瞬緊張したようにこわばるが、それは俺にはとても新鮮だった。
「窓なんかより俺の顔を見ろよ。なあ、もっとアンタに触れてみたい。嫌か?」
窓に向けられた彼の体は俺と相対するように向き直る。俺は彼を抱き寄せると、ベッドルームのドアを開けた。
*
「クリストフ。私は―」
寝ぼけた頭で酷い有様だったベッドシーツを引き剥がし、新しいものに換えておいた事は今日の俺の行動のうちで、かなり上位に来るものだ。
明らかにこう言うじゃれあいに慣れていない口ごもりがちな彼の唇を解きほぐしたくて何度もキスを送り、もつれ合うようにしてベッドに身を沈めた。安いスプリングが軋んだが、気にもならなかった。
「聞いてくれ、俺、アンタに恋をした。フリードリヒ。それも、本気の恋ってやつだ。
だからさ、こんなこと、俺が言う資格なんて無いんだろうけど、もしもアンタが男とファックする好奇心を満たす為の相手を探してるんだとしたら、それは俺じゃない。
俺はアンタとそんな軽い関係を持ちたくないんだ。俺は確かにあんな店に勤めてる。だが、客に対してそんな風に思ったことも一度もない。アンタだから、こうしたいって思ってるんだ」
最後の警告だった。
彼の上にのしかかるようにして、彼の窮屈そうな軍服の襟元を緩めた。彼は、結果それが俺にたくましい首筋をわざわざ見せ付けるようなことになっているとは気づいてはいなかったようだが、頑として横を向き続けてはいたが、抵抗はしなかった。俺は彼の首筋から顎のライン、目元、そして唇と、キスの雨を降らせた。音を立てる様に、吸い付くように、彼に俺の唇が与える感覚を覚えさせるために。
「笑ったって良いぜ、フリードリヒ。俺はアンタに惚れてるんだよ。
アンタのことが好きだ」
彼の手首を掴んでベッドから縫いとめ離さなかった。俺の顔を真正面から見上げることができなくて、顔を逸らすフリードリヒの横顔は、とてつもなくセクシーだった。
彼はそんな事にはまるで気づいていない様で、のしかかる俺に顔をゆるゆると―それは本当に少しずつだったが彼は俺にまっすぐ目を向けた―上げ、言った。
「なぜ俺が笑うと思う?クリストフ。私も―。私も、お前が好きだよ。
君の言葉を借りれば私はお前に惚れているんだ。
きっと、昨日君に会ったときから。そうだったんだろうと思う」
「フリードリヒ」
「クリストフ。私も少し混乱している。だが、きっと―」
「混乱?それどころじゃないさ。アンタとあってから今まで、俺はアンタに振り回されっぱなしさ。この俺がだ。こんなこと初めてだ。だけど、きっと、フリードリヒ」
「ああ。クリストフ。きっと、これは運命だったのかもしれない。
こういう風にいつか出会うことが」
俺の理性を留めていた何かが外れた。フリードリヒと愛し合いたいと思った。キスをして、触れて、快感に震える顔が見たかった。彼の何もかもが欲しかった。
「俺はもっと、深いところで結ばれたいよ。アンタと」
彼の軍服を乱して肌を覆う窮屈な衣服を引き剥がす。俺の目の前には彼の―まさかここまでとは想像もしていなかった―肌理(きめ)の整った肌と、鍛え抜かれた筋肉がギリシャ彫刻のように隆起する素晴らしい身体があった。
「―クリストフ。待て、待ってくれ。私は!」
「フリードリヒ。待てない。止められない」
この美しい身体が人の目にさらされたことが今まで何度あったんだろう。いったい何人の女達をその腕に抱いて来たんだろう。逞しく、しなやかで美しいフリードリヒに―女だろうが男だろうが―夢中になる者が少なくないってことは簡単に予想がついた。だからなおさら、俺が彼を知るまでのこの長い日々に、この身体がどんな風に触れられて、それにどう反応したのか。それが嫉妬にも似た感情となって俺の胸を焦がした。何の躊躇もなく彼の薄い色をした乳首を子供のようにきつく吸い上げた。もう片手で片方の乳首を強く摘み上げ、彼がいったいどんな声を上げるのかを聞きたくて堪らなかった。
「クリストフ!」
彼は全身をわななかせて震えた。衣服を失った裸の腕で自分の口もとを覆って、折角の可愛い声を俺に聞かせまいとする。それは面白くない。俺は容赦なく彼の手首を掴んで彼の顔の横に縫いとめた。彼のささやかな抵抗はそれで封じられる。たくましく盛り上がった胸元に思うままに舌を這わせ、淡い色の乳首をなぶる。あとできっと彼が違和感を覚えるほど強く吸い上げた。敏感になっている乳首に俺が歯を立てたときには、フリードリヒは喘ぎを更に大きくし、シーツを握り締めることしかできなかった。
「―クリストフ、待ってくれ。―お願いがあるんだ」
乱れた呼吸のまま、途切れ途切れになる彼の言葉はとてもセクシーだ。偉大なるフリードリヒが乱れた制服に汗をにじませた扇情的な姿で俺に”お願い”をする。そんなこと、想像もしていなかった。
「なんだよ。アンタの頼みなら何でも聞くぜ?フリードリヒ。もっと激しいのが好みか?」
彼が何を望んだとしても応えたいと思った。
彼はゆるゆると首を左右に振った。
そして幾度も躊躇ったあとで、俺の舌と指ですっかり上気した最高にセクシーな顔を俺にまっすぐに向けてこう言ったんだ。
「―男と、男とこういうことをするのは、本当に初めてなんだ。分かってくれるか。私は、慣れていないんだ。みっともない姿をさらしてしまうかもしれない」
―ああ神様!
生まれて初めて神に感謝した。
この美しいフリードリヒが今まで他の男―彼の容姿と地位を考えれば、おそらく女性とそうなる機会は幾らでもあったんだろうと思う。だが、男となると話は別だ―とファックしたことがないっていうのは、つまりこの俺が彼にとって始めての男になるってことだろう?
「マジかよ?まさかはじめてだったなんて、想像もしてなかった。
怖い思いをさせたか?悪かった。うんと優しくしてやるよ、フリードリヒ」
俺はフリードリヒにとって少々手荒な愛撫をしてしまった胸元をそっと指先でなぞった。こんな風に誰かに優しく触れるのは初めてだった。
俺は緩急をつけて膚に吸い付いて感触を楽しみながら、彼のベルトを緩め、俺とフリードリヒとを隔てる邪魔な衣服を脱ぎ落とす。
硬いブーツが床に落ちる音がする頃、俺達は互いの膚を確かめ合うように抱き合っていた。フリードリヒは男とファックするという初めての場面に緊張を隠せずに、俺の腕の中で不安げな顔を浮かべていた。キスをするたびにその顔と息に少しずつ欲情の色が混じっていくのはすごく扇情的な光景だった。俺は彼がもっとダイレクトに反応する顔を早く見たくて、俺の下腹に触れてそこから透明な体液をにじませている彼のコックを扱いた。フリードリヒは大きく身体を撓らせて、俺の背中に両手を廻し懸命に苦しげにも見える表情で俺が与える快感を受け入れていた。
「怖いか?フリードリヒ」
「怖いんじゃない。ただこんなところを見られて―とても、恥ずかしいんだ」
軍服を着たあのフリードリヒがこんなにもベッドの中では不慣れで、こんな年の離れた俺の腕の中で翻弄されるのだと誰が想像できる?誰にも彼のこんなところを見せたくない。俺だけのものにしたいと思った。
「嫌じゃないなら、フリードリヒ。アンタが見せてくれるどんな声だって姿だって、俺からすれば惚れてるアンタが俺とファックして感じてくれてる姿なんだ。みっともないなんて思うな。声を出せ。アンタのすべてを知りたいんだ。見せてくれよ。
アンタを苦しませることだけはしない。約束する。ただアンタが気持ちよくて堪らなくなる顔を見たいだけなんだ」
フリードリヒが俺の腕の中で小さくうなずいた。彼のコックは俺の手の中でエレクトして熱かった。彼が俺とこうしている事に興奮を覚えてくれている何よりの証拠だった。俺が腰を揺らして硬くなったコックを押し付ける、彼は俺の男である最も象徴的な部分を感じて、眉を寄せた。
「俺のコックはアンタの気に入りそうか?」
「バカなことを、言うな」
「俺は真面目だぜ?大事なことだろ」
彼のコックの敏感な箇所を探るように角度をつけて手首を上下に動かし、しがみつく彼の形の良い顎や、目元にキスをした。唇を耳元に這わせて、そこから首筋にかけて一度も唇を離さないように少しずつ舌で膚を辿ると、フリードリヒの引き締まった体が震えた。俺にすがるように両腕を廻して、まるできつくしないでとせがむようだった。
「痛いことも無理なこともしない。俺を信用してくれ。
フリードリヒ。愛してるアンタを、わざわざ苦しめるのは俺の趣味じゃない」
フリードリヒの両脚を、腿を掴んで押し広げた。彼の両手がシーツをきつく掴む。
安心させるように緊張で震える彼の下腹にキスをしてから、俺は彼のコックを深く銜え込んだ。自分の喉の奥までそれを受け入れても、苦痛だとは少しも思わなかった。コックに舌を這わせ、思うままに吸い上げると、ずっと押し殺して居た声が途切れることなくフリードリヒの喉の奥から漏れる。まるですすり泣く様なそれは、聞いているだけで腰の奥が疼いた。フリードリヒのコックは俺の口の中でそそり立っていた。俺は自分のコックに手を伸ばし、扱きながら、彼の尻の穴に指を這わせた。途端に彼の体が怯える様にびくりと跳ねる。
「ああ、なんていうことだ。すまない―。本当に、慣れていなくて」
彼をたっぷりと味わってから俺は頭を上げた。
「謝るな。俺のことだけ考えててくれ。楽にするんだ」
彼が唾を飲み込むたびに上下する喉仏にキスをして、ベッドの脇においてあるサイドテーブルの引き出しを乱暴にまさぐる。一番上の引き出しに入っているファックする時の為のチューブ入りのゼリーとコンドームを掴んだ。慣れている動作なのに、何もかもがもどかしかった。彼だけに触れていたかった。俺の腕の中で、俺が身動きするたびに不安げにフリードリヒの視線が揺れる。緊張に身を硬くしながら次に何が起こるのかを待つ彼は、息を乱して俺を待っていた。俺がこれからすることを受け入れてくれようとしていたんだ。
「クリストフ」
「アンタが好きだ。セックスで満たされるのが身体だけじゃないことを知ってほしい。俺はあんたとずっと一緒にいたい。もっとアンタのことを知りたい」
ゼリーのチューブを乱暴に絞って中指と人差し指に透明の粘つく中身をまとわりつかせ、その指の腹で彼の尻の穴を撫でてから、中指をゆっくりとまだ男を知らない其処にもぐりこませた。
彼の体が強張り、喉の奥からうっと言う低いうめきが上がった。
「声を殺さないで、息を吐いて。楽になる」
俺の指が埋まっている違和感だろう。彼は声を出すことができない。ただ、一度、俺の言葉に首を縦に振った。俺の指は彼の尻の穴の中のうごめくような粘膜に締め上げられる。もっと彼の中に触れたかった。ゼリーで粘つく人差し指を中指に添えて、一息に彼の中にもぐりこませた。バージンのアナルのギャザーをゆっくりと伸ばして、ちょうどボールの裏辺りを内側から強く指先で押し上げた。
まるで電流が走ったみたいに彼の体がそり返る。俺は“良い箇所”を探り当てたんだ。
フリードリヒは、今までの直接的な快感とは違う、内部から徐々に昂ぶるじれったい、少しずつ燃え上がって行くようなそれに翻弄されていた。唇から漏れる声の質が変わり始めていたからすぐに分かった。汗の滲む体を俺に魅せつけるようにしならせる。白い膚を興奮で上気させ、半ばに開いた唇から白い歯が覗いていた。
俺はシーツの上に放り投げていたコンドームのパッケージを掴んで唇と片手で破る。
あと1分だって我慢ができなかった。
「俺は幸せだよ。俺がアンタを抱く最初で最後の男になるんだ。
他の誰にも触らせない。フリードリヒ、絶対にだ」
震える目元に唇を這わせ、愛している、と囁いた。
初めての身体を傷つけない様に、こんなにも丁寧にしたことが無いっていう程俺は慎重にことを進めた。俺の指を飲み込んでいたフリードリヒの尻の穴は俺のコックに吸い付きながらやわらかく受け入れてくれた。彼の身体を抱きすくめて逃さない様にして、彼が俺のコックに慣れる迄、俺は耐えた。俺の体にもじっとりと汗が滲み、息をする度に腹筋が震えるのが自分でも分かった。
「フリードリヒ-。もう大丈夫か?動いても、平気か?」
「ああ、クリストフ―。構わない。もっと、お前が、欲しい―」
フリードリヒが俺のことを“君”と呼ばなかった最初の会話さ。俺は永遠に忘れない。
大きく腰を使う。彼の上品な唇はいまや唾液に濡れて、喘ぐことしかできない。俺がそうさせたんだ、そう思うだけで心から満足だった。
突き上げると、フリードリヒは首を左右に振ってそこは嫌だとせがんだ。腰をしっかりと抱いて逃げ場を無くし思い切り彼が嫌がるところばかりを狙って身体を使うと彼はよがって泣いた。俺の背中に廻した彼の指が痕になるほど強く俺に抱きつく姿は見ているだけでいってしまいそうになる。俺は何度も息を深く吸って耐えた。薄いゴム越しに伝わる感覚は最高だった。生まれてはじめての男とするファックに震えるフリードリヒ本人とはまるで別の生き物のように、其処は俺を締め上げ、いやらしく蠢いていた。何度も腰を使い、強くゆすった。彼のコックを掴んで上下に激しく扱いた。フリードリヒが永遠に俺以外の男に目など向けないように、彼に彼が俺のものであることを教え込む為に、俺たちは深く深く繋がった。
フリードリヒは身体を仰け反らせ、彼の内壁は俺を締め上げ続けた。
「フリードリヒ!ああ、すごく良いよ!あんたを愛してる!」
「クリストフ、クリストフ!-俺も、お前を―!」
互いの名前を繰り返し呼んだ。俺がコンドームの中に熱い精液をぶちまけたのと、俺の下腹が彼の精液で熱く濡れたのは同じ瞬間だった。彼のきつい締め上げに導かれるままに大量の精液を吐き出した俺は、彼の汗ばむ首筋に顔を埋めた。
すぐには指一本動かせそうに無かった。
*
それから、どれくらいが経ったんだろう。
身体を解いた後、俺たちはぴったりと寄り添っていた。
「不思議だな。まさかアンタが男が好きなんて思ってもいなかった」
「私は女性をそういう行為の対象にも、自分の気持ちを向けることもできない。
だが私はそれを必死に忘れようとしていた。正確には、目を逸らしていたんだ。それは私を縛っているルールからは逸脱したものだったからね。
だが、夕べ初めてお前を見て、気づいたんだ。もう一度、自分を見つめなおさなければいけない。このまま目を逸らし続けてはいけない。
夕べ、君に会って、それを思い出したよ。
君達はとても自由だった。それに比べてこの私は、がんじがらめさ。それが当たり前なんだとずっと思って来たが、自分が大切なものを失いつつあるんだと、夕べ奔放で気まぐれなマリールイーズと出会ってやっと分かった。
私は自分自身に関心を無くしかけていたんだ。一人で居ることにも、自分がなぜ一人でいるのかということにも無頓着になっていたんだ」
俺とフリードリヒはもしかしたら本当に対になるように対照的なんだと思った。
俺はずっと自分が一人ぼっちだってことに執着し続けて、周りに大事な仲間や、こんな風にありえない偶然で運命の相手に出会えることがあるってことを見失っていたんだから。
「夕べ?あんなドレス姿の俺が良かったったなんてどうかしてるぜ。わざと悪趣味にしてるっていうのに」
「どんな格好をしていようが本質の美しさは変えられない。その逆も然りだ。
私の隣に座るお前の横顔を見たとき、なんという綺麗な若者が居るものだと思ったんだ。お前もジュスティーンも、あらゆる規範から解放されて美しかった」
ファックの後の疲れが浮かぶ顔で俺を抱きしめるフリードリヒの腕は優しく、今までこうして一緒に寝た誰よりも俺を守ってくれるんだろうという安心感があった。
「あんたの方がよっぽど良い男なのに。やっぱり変わってる」
「自己判断というのは過小評価か過大評価かどちらかに偏るものだ、クリストフ。
私の判断は正しかった。私の知らない世界を私に見せてくれるお前は勇敢で、タフで、優しかった。そしてあの時、映画館でお前と別れた後にはっきりと悟ったんだ。君が好きなんだと」
俺は彼の胸元に甘えるように頭をもたれていた。自分のベッドがこんなに暖かいことを知らなかった。彼は俺の髪に指を差し入れて梳きながら言葉を続ける。美しい横顔に見惚れながら俺は彼の言葉を聞いていた。
「君に会ったことは、もしかしたら本当にずっと以前から決まっていたのではないかと思っている。私の気持ちは真剣だ。クリストフ」
彼の唇が俺の額に触れた。彼が低い声で愛している、クリストフ、と言ったのがはっきりと聞こえた。
「まるでこれじゃ出来過ぎたB級映画だ」
照れ臭いというだけじゃない。胸の中に暖かい気持ちが溢れていた。俺は自分が涙をこぼしていることに気づかなかった。フリードリヒも泣いていた。彼が愛しい、その思いが俺を泣かせていたんだ。人を愛するということがこんなにも自分を動かすなんて、俺は知らなかった。
「B級映画は趣味じゃないかな?私はそんなに、嫌いじゃないんだ」
その言葉には俺も賛成だった。俺達はまるでどこかの映画のワンシーンみたいに互いに抱き合い、キスをした。
夜が更ける迄、俺達はもう一度お互いの温もりを求め合ったんだ。