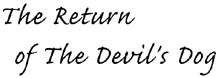Coral Fung -07
20分後、俺達はこの街のメインストリートを歩いていた。
俺がおそらく”AMERIKA”という言葉からまず連想する、マルボロの匂いと味。ジュスティーンにゴロワーズを貰ったことがあったけど、結局匂いがきつい紙巻は俺の口には全く合わなくて、吸い口の端についた口紅の交換をしただけで終わった。そんな事を思い出しながら、煙草のフィルターを唇に挟んだ。店には持っていかない俺の気に入りの使い古したジッポで火をつける。週末のセコンドハンド・マーケットで見つけた掘り出し物さ。
「自由が欲しい、だって?金も地位も、取り巻きも。アンタ、何もかも持ってる。アンタ、将校さんだろ。何の不自由も無く暮らしてる筈だ。それは自由ってことだろ?」
「それは違うな」
「何が違うんだよ。この街に居る奴らは俺も含めてアンタら金持ち連中からみれば何も無い。金も地位も、仕事もだ。アンタが買おうとしたさっきの画集って奴だってそうさ。あんなもの、買える奴がこの街に居ると思うか?アンタ、それでももまだ自分が自由じゃないって言えるのかよ」
俺は語気を鋭くして言い返した。胸の中にあったどす黒いものが全部言葉になってあふれ出る。まさしくそんな感じだった。そんなの金持ち連中の贅沢すぎる愚痴に過ぎない。そうじゃなきゃ、俺達が、いや、こんなクソみたいな場所から這い登ろうと必死になってる俺があまりにも悲しすぎる。
「クリストフ。聞いてくれ」
「何を聞けって言うんだ」
不意に俺の髪をやわらかいぬくもりが包んだ。それがベルンハルトの革手袋に包まれた手だと認識するのに数秒を必要とした。革の手袋ってやつはもっと硬くて冷たいものだと思い込んでいたから。そしてまさか、自分がそんな風に髪に指を差し入れられた時にいやだ、と思わないなんて予想もしていなかった。
「不愉快にさせてしまっているなら謝る」
「謝られたって何も変わらないさ。ここには俺の必要なものは何ひとつない。俺は、アンタが持ってるものが欲しい。金と地位さ。もっと言おうか?俺にはアンタが言う自由すらままならない。アンタの言う自由ってものがここにあって、それと引き換えになるっていうなら俺は俺の自由をいくらでも差し出すね」
そうさ、俺は東ベルリンでもここでも、ずっと一人ぼっちなんだ。その一言を言わなかったのは俺に残された最後のプライドだったのかもしれない。
「クリストフ、私の世界にはどうやらその自由だけが無い。そしてそれは、とても不幸なことなんだ。君にもいつか分かる日が来る」
俺は肩をすくめて煙草の煙を吐き出した。俺達の言葉と、空気に混じって消えていく紫煙だけがこの通りには在った。他にあるものといえば割れた酒瓶と雨に濡れたぼろぼろのゲイポルノ雑誌くらいなものだった。
不意にベルンハルトが俺の手首を掴む。
「会話を途中で終わらせる無粋を許してくれ。
クリストフ、私の方を見ないで、ショウウインドーの方に顔を向けるんだ。
向こうの角だ。私と同じような格好をした若いのが二人、いるだろう」
果たしてそこにはベルンハルトのいうとおり、生真面目を絵にかいて上からコールタールを流し込んだような堅物そうな将校が二人、辺りを見回しながら歩いてくるのが見えた。ベルンハルトは穏やかな笑みを絶やすことなく続けた。
「私の部下だ。私の休日を愚かにもつかんパーティで終わらせるのをまだ諦めんらしい」
若い二人がこちらに気がついたのと、俺の手をとって-クソ重そうなブーツで走り出したベルンハルトは足音をひとつもあげなかった-ベルンハルトが走り出したのは同じタイミングだった。
「おい、ベルンハルト!」
「君がガイドを引き受けてくれて、助かった」
つられて走る。
ベルンハルトの横顔が今までイメージしていた軍部の連中とかけ離れていて、俺は純粋に驚いた。血相を変えた自分の部下に追いかけられてるって言うのに、奴の顔はまるで無邪気だった。新しい遊びを見つけた子供の顔みたいに。
「よく言うよ!おい、そこの路地だ、そこに隠れてろ」
ベルンハルトは俺の指差したクソ狭いビルとビルの隙間の路地裏に駆け込む。俺は吸いかけの煙草をもみ消すと、その路地の入り口すぐのビルの外壁にもたれ、空を見上げた。地面の小石をつま先で蹴る俺は、通りで何が起こってるのか、誰が出入りしてるのかを眺めるしか能の無いボンクラにしか見えない筈だ。特に多少荒っぽい手段を使ってでも、情報をかき集めたい連中にとっては。
「お前、このあたりで軍服を着た男を見かけなかったか?」
案の定、例の堅物たちは、奴らから見れば完璧な不審者そのものである俺を左右に取り囲む。帽子の影から覗く目からは自分達より下の世界の人間に話しかけてるっていう意思があからさまに見て取れた。それは、東ベルリンでずっと恐れていた秘密警察を思い出させる。俺がこの世で一番嫌いなものだ。
こういうときにどうすればいいのか、有効な方法は分かっていた。
俺は奴らの方に身体を向けて、首をゆっくりとかしげた。そして手首をくねらせて腰に当てる。
「軍服の男?あら、それなら見てるわよ。目の前に二人もね」
二人の将校が明らかに動揺している。目の前のクズ野郎がクズ野郎じゃなくてカマ野郎だった時の対処法、なんて教育は受けたことが無いらしい。俺はまるで自分が店に居る時のように顔を斜めに向け、上目遣いに将校の顔を品定めするように交互に見遣る。こういう頭の固い連中には、俺がクズ野郎じゃなくてカマ野郎だって分からせるのが一番手っ取り早い。
「オカマか?」
「だったら何だって言うのよ、デートにでも誘ってくれるの?」
帽子の下の素顔は、ただ若いってだけだった。おそらく俺より20歳は年上だろう、路地裏のベルンハルトの方がずっと良い男のように思えた。
「痛い目を見たくないなら、質問に答えろ。軍服を着た男を見なかったか」
「軍服の色男なんてこの街でそうそう見かけると思う?
アタシ、もしそんな人がもし他にいれば絶対見逃すはず無いわ。誓ったって良い」
「ゲネラーレはお前のようなゲスな人間には目もくれずに歩かれるだろうが、お前はその目をよく使え。目の奥にだってどうせ男を追いかける事にしか使わないスカスカの脳みそが詰まってるんだろうが。軍服姿の男を見かけたら俺達に知らせること位はお前みたいなカマ野郎でもできるな?」
火のついてないタバコの銜えて、顔を先を将校の方に向けてひげ面のいかつい方にウインクを一つくれてやる。二人のうち、眼鏡をかけた神経質そうな野郎がおそるおそる高そうなガスライターを取り出した。
「ありがとう。やさしいのね。アタシの好みよ。あなた、名前は?」
何かスポーツをしなきゃどやされるって理由で15の頃から続けてたウェイトリフティングの成果でたくましく筋肉のついた両腕でわざと自分で抱きしめながら俺は嘯いてやった。鼻歌を歌いながら身を揺らす。おそらく二人にとってはじめて見る光景だろう。俺だって店でもこんな風に機嫌よく振舞ったことははないんだから。
「いいか!軍服の男がお前のそばにあらわれたらすぐここに連絡しろ。僕はシュナイダー秘書官、こっちはハルトヴィック少尉だ」
計算どおり、暖かいハグの代わりにメモをつき返される。そのメモをわざと人差し指と中指で挟んで、紙の端にキスをした。二人の顔には生まれてはじめてまともに会話をしたカマ野郎が自分達の予想と1ミリだってずれていなかったことに対する嫌悪がありありと浮かんでいた。
「アタシはマリールイーズ。見ての通りこの街一番の良い女よ。」
「こいつ、いかれてるよ。ハルトヴィック。薬をやりすぎた麻薬中毒者だ」
「ああ。毎晩ベッドに違う男を引っ張り込んでヒイヒイ泣いてる薄汚いカマ野郎な上に、だ。救いようが無いな」
ドラッグには一度も手を出したことは無いが、どうやらこの二人には俺が立派なジャンキーに見えるらしい。こみ上げそうになる笑いを必死にこらえる。
「シュナイダー。あなたのお友達は怖いのね。ねえ、あなた達が追いかけてるその人も同じくらい怖いの?アタシ、面倒ごとに巻き込まれるのはごめんなのよね」
むさくるしいひげ面のハルトヴィックの襟元の勲章に指を伸ばすと案の定、その手は叩き落される。
「俺に触るな!汚らわしいホモ野郎め。いちいちうるさい奴だ。秘書官と俺はゲネラーレ・ベルンハルトという方を探している。いいな、ゲネラーレをお見かけしたら俺たちにすぐに知らせるんだ。それから、分かってると思うが―」
「アンタたち二人が探してるそのゲネラーレってのに指一本触れたらぶちのめしてやるからな、このカマ野郎?って言いたいんでしょ。悪いけど、そこまで男に飢えてないわよ。おあいにく様!」
「どうだかな、どうせ尻に男のものをぶち込まれたくてたまらないんだろう」
「ゲネラーレに余計な事を一つでもしてみろ。裁判なんて面倒くさいことはすっ飛ばしてお前を刑務所に送り込んでやる。お前と同じくらい腐ったクズどものあれを咥えて死ぬまで過ごすことになってから後悔しでも遅いぞ。せいぜい気をつけるんだな」
タバコの煙を二人の顔に挑発的に吐き出してごめんなさい?と身をくねらせて笑った。
これ以上俺に関わっても何も出てこないとやっと判断したのだろう。このカマ野郎!と毒づくと、将校達は俺の予想通り、踵を返た。ハルトヴィックの野郎はご丁寧に俺の足元の地面に唾をはくことも忘れなかった。
二人が見えなくなるまで、俺は手を振り続けてやった。
*
「ベルンハルト。アンタ、あいつらから逃げてるのかよ?奴らを見たかよ、これって少々揉めたってレベルじゃ無い!あいつら、アンタのこと探し出すのに躍起になってるぜ」
この街に来てから警官に追い廻されるような事は何度かあったし、それ以外にも多少の荒っぽい場面だって経験はあった。だが、軍人に追われるとなると話は別だ。
息ひとつ乱さずに涼しい顔をして、表通りに目を向けているベルンハルトの足元にへたりこんで、恨めしい顔を向けた。
「だが、彼らから離れて一人で行動するなど一体何年ぶりになるのか。束の間の自由なひと時を夢見て、それを実現させた私の努力は認めて欲しいね。いつもはおとなしく彼らの言うことを聞いているんだからな。
だがそれよりも、クリストフ、いや、マリールイーズ。私の部下が君に言ったひどい言葉について私は侘びなければばいけない。彼らは君という人間を貶めた。本当にすまなかった」
部下の言葉についてこの偉大なる陸軍大佐が謝罪するなんて、想像もしていなかった。だが、それよりも俺を驚かせたのは俺のことをクリストフではなくはっきりとマリールイーズと、そう呼んだ事だった。
「アンタ、俺の名前、覚えてたのか?」
「当たり前さ。生まれてはじめてみたが、最高に面白いショーだったからね。もっとも、つい今しがたまで、気がつかなかったが。まったく化粧というのは人を変えるものだな」
面白かったって?
それって、このベルンハルトが夕べ俺のショーをまともに見てたってことか?
俺は唖然とした。
俺達のショーなんて、あの忌まわしいVIPシートに座る連中の誰一人だってまともに見てるわけが無いと思っていたから。
「夕べの君とジュスティーンは刺激的だったな。個人的な好みを言わせて貰えば私は君に釘付けだったが」
「アンタの、アンタの部下と同じで、どうせアンタも俺の事をクズのカマ野郎だって軽蔑してたんじゃないのかよ」
そうに決まってる。
俺は見世物で、こいつらはそれを高みの見物としゃれ込んでるだけなんだ。
俺はベルンハルトがさっきの将校達みたいに俺のことを思っていてくれれば良いと思った。その方がずっと気持ちが楽だと-ベルンハルトは所詮、俺が思っていた通りの胸糞の悪い野郎だと思えると-思った。
「それについてはNein、だな。私は君らをカマ野郎と呼ぶような考えは持っていない。
君がマリールイーズだと知って、ますます今日のガイドを君に頼んで正解だと思ったよ。変わらず俺のガイドを引き受けてくれるか?マリールイーズ…いや、クリストフ」
「どうして、俺なんだ。俺はカマ野郎で、アンタらみたいなマッチョ男の集団から見たら軽蔑の対象じゃないのかよ」
「それこそ君が言うところの私たちみたいなマッチョ男の集団に対する偏見だな。私は君のショーを心から楽しんだ、いうなれば君のファンさ。君はファン心理というのを考えたことがないのかい?それとも私の様なにわかなファンじゃ人気者の君には物足りないかな?」
その言葉は酷く意外だった。俺があのベルリンのビッチ・マリールイーズだとばれたら、その瞬間この男は他の将校同様、俺の足元に唾をかけて俺から離れると思っていた。それが、俺のファンだって?
皆酒の肴に俺達を眺めて、笑って、そしてまた日のあたる場所に帰っていく。それだけだと思っていた。その言葉は衝撃的だった。俺にファンが居る?悪い冗談にしか思えなかった。
「だったら」
だからこそ俺は自分が次に言おうとしてる言葉に自分が躊躇していないことに戸惑っていた。同時に、今までこのベルンハルトに対して持っていた嫌悪にも似た感情がほぼゼロと言っていいほど、薄くなっていることにも。
「俺がガイドするってんなら、まずアンタを連れて行かなくちゃならない場所がある。
ゲネラーレ・ベルンハルト。アンタ、その格好じゃ目立ちすぎるんだよ」