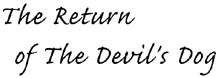Coral Fung -09
その後の俺はこれまでに無いほど手際良く立ち回った。床に崩れ落ちた男の鳩尾を蹴り上げながらベルンハルトを突き飛ばし”あたかも見知らぬ男2人のクソくだらない喧嘩沙汰”を完璧に演出したんだ。ベルンハルトは俺を止めようとしたが、俺はその手を振り払いアンドレアスのところに戻るように伝えた。
つまり、この喧嘩はあくまでも俺が見知らぬ男に一方的にふっかけた騒動だって事にしたわけさ。
狙い通り、十分ほど経った後でようやく駆けつけた警官2人に取り押さえられた俺は警察署に連行された。待ち受けていた刑事は俺のおざなりな供述を更におざなりにたった数分で調書にまとめ、俺をブタ箱にぶち込むための書類を作りにオフィスに戻った。俺は明日は店に出られないな、と思ったが、ベルンハルトが楽しそうにしていた顔を思い出すと、不思議と俺が取った行動のどれ一つに対しても後悔の気持ちが沸かなかった。
それから1時間か、2時間。俺は一人で取調室の薄汚い壁を眺めていた。
今日という日を締めくくるにはあまりにもクソ忌々しい場所だ。それが俺にはお似合いということなんだろうか、もしそうだとしたらこんな目にあう様なことを俺は本当にしでかしたんだろうか。
街でばったり出逢ったベルンハルトのガイドを引き受けただけじゃないか。そうして街を眺め、ケバブを食い―ケバブを食うベルンハルトの手つきは本当に不器用だった―、窮屈な軍服から着替えさせただけじゃないか。アンドレアスの店でドレスアップしたあとで街をうろついて―。
今なら素直に言える。
俺は、いや、俺達は今日一日を、まるで恋人みたいに楽しんだ。ほんの束の間の自由を二人で精一杯楽しんだ。その一日の終わりに何も知らずに割って入ってきやがったクズを叩きのめすことがそんなにいけないことだったのだろうか。あるいは、俺がベルンハルトの為にそこまでしたことがそんなにいけないことだったのだろうか。
だが、いずれにしたって、これでおそらくもうベルンハルトには会うことはないだろう。そう思った途端、俺はひどくつらい気分になった。あの不器用な、それでいて妙なところで機転の利く掴めない年上の男のことが頭を離れなかった。
ベルンハルトは俺のことをマリールイーズとしても、クリストフとしても受け入れてくれた、たった一人の男なんだ。
そして俺がこの街で、あの店を出たらたった一人なんだってことが勘違いだって教えてくれた。
怒りっぽいウルフガング。調子のよいオマム。カフェで馬鹿騒ぎした友達。おせっかいだが憎めないミゲル。そしていつだって俺に朝まで付き合って飲み明かしてくれるジュスティーン。
みんなの顔が頭に浮かんだ。まるでみんなが家族みたいに思えた。キンダーハウス育ちの俺にとっては、そんなこと、生まれて初めてだった。
映画館でベルンハルトを突き飛ばしたときのことが蘇る。
交わす言葉もなくその場を去らざるを得なかったベルンハルト。俺は一人になった映画館でとてつもなく寂しかった。
俺は自分の鈍感さを呪った。何でいまさら、気づいたんだ。
俺はベルンハルトに恋をしてる。
許されるのなら、もう一度会って話がしたい。心からそう思った。
その時だった。
「おい、クリストフ。出ろ。釈放だ。お前は何もしていない。映画館では何も起きていなかった」
くたびれた背広が身体の一部みたいになっている刑事がノックも無しに取調室のドアを開け、言った。
「何言ってんだ。ブタ箱にぶち込むの間違いだろ、刑事さん」
意味が分からなかった。
俺はこの後1日か2日、吹きさらしじゃないだけマシってだけのクソ溜めみたいなブタ箱に放り込まれるんじゃなかったのか?
「いいから立て。陸軍大佐をお待たせするとこっちがやばい目にあうんだ。さっさとしろ」
一日のうちに何回馬鹿面をさらせばいいんだろう。
俺は自分に何が起こっているのか理解できないまま、安っぽいパイプ製の椅子を押しのけて立ち上がった。
取調室と同じくらい殺風景な玄関ホールに出ると、そこには4人の男達が俺を待ち受けていた。軍服姿のベルンハルトと、ミゲル。そして、シュナイダーとハルトヴィックだ。
「クリストフ、待たせてしまったな」
ベルンハルトは俺を見るなり言った。その顔は―俺が楽観主義者だと思うなら、そう思ってくれて構わない―俺のことが心配で堪らなかった様に見えた。
「こっちの素敵なゲネラーレがどうしてもって言うから、大嫌いな場所だけど特別に道案内してあげたわ。途中で会ったゲネラーレのお友達も一緒にね」
「フリードリヒ!アンタ、来てくれたのか」
俺はベルンハルトの身体をきつく抱きすくめた。何の抵抗も、躊躇も無かった。
血の気の多そうなハルトヴィックが気色ばんで俺を引き剥がそうとしたが、ベルンハルトが片腕を振り上げてそれを制した。彼の腕が俺の背中に回されるのを感じたとき、俺は眩暈にも似た嬉しさを感じた。
ミゲルは俺たちに向かってウインクをした。それも背後に控える二人の部下に見せ付ける様にだ。案の定、シュナイダーとハルトヴィックは苦虫を噛み潰した様な顔をしていた。俺はつい数分前までブタ箱にぶち込まれるかもしれなかったというのに、そんなことはどうでも良くなっていた。
ついでに明日から奴のことをフラウ・ミケイラと呼んでやってもいいかな、と思った。
「会いたかった。もう会えないんじゃないかって、さっきからずっと思ってた」
「そんなことは誰にもさせない。二度とクリストフに会えないなど、考えられん」
どちらからしかけたのかは、良く覚えていない。
俺とベルンハルトは、お廻りや刑事達が行き交う警察署の玄関ホールのど真ん中で深いキスを交わした。
誰に見られていても気にならなかった。
*
俺が連行されたあとの事の顛末は、こういうことだ。
ベルンハルトはミゲルの店に戻り何が起こったのか、俺がしでかしたことを奴に伝えた。それを聞いた奴がしたことはベルンハルトを元の立派な軍人の姿に戻して、警察まで行くってことだった。権威には権威を、シンプルだけどこれ以上有効な方法は無い。こういう時のミゲルは本当に信頼できる男だ。貞操観念を除いての話だが。
とにかく、奴の機転で警察署までやって来た偉大なるゲネラーレ・ベルンハルトに、俺をブタ箱にぶち込む気で居た刑事は真っ青になったって訳だ。ゲイシアターで喧嘩沙汰を起こしたチンピラの身元引受人が陸軍大佐だとしたら?もしも俺が刑事だとしても同じ反応をすると思う。
ただし、それにはあきらめずにまだこの街をくまなく探し回っていたシュナイダーとハルトヴィックにも見つかるという代償を伴った。
その代わりとして偉大なるゲネラーレの忠実な部下達は、親愛なるカマ野郎ミゲルの案内でこの俺を警察から引き取るという、奴ら二人からしてみれば世にも屈辱的な場面に立ち会うことになった訳さ。だが、俺が奴らに言われたことを考えればそれくらいの思いはして貰ってもお相子ってところだろう。
*
俺達はとにかく、フラウ・アンドレアのお陰で再開を果たした。
いままのでの俺の心の中にあったわだかまりは日なたに置いた氷の塊みたいに溶けていた。目の前のこのベルンハルトに対して昨日から抱いていた自分の気持ちが何であったのか漸く片付いた俺は信じられないくらいストレートに行動した。何度も何度も唇をかさね、お互いの舌の暖かさを確かめてから、互いの額を押し当てる。
ミゲルは嬉しそうだった。それとは正反対に例の二人は尊敬するゲネラーレが今こうしてこのカマ野郎と熱いハグとキスを交わしている光景にこの世に生まれてきた以上のショックを受けているようだったが。
「クリストフ 、またあの席に君を見に行っても構わないか。そして、君さえ許せば、ショーの後に食事に誘っても?」
初めて間近に聞くベルンハルトの声は低く、そして甘かった。聞いてるとそれだけでファックしたくなるくらいにセクシーだった。
「仕事とプライベートはきっちり分けるのが俺の流儀だけど、アンタがどうしてもっていうなら、良いぜ」
「ゲネラーレ。すでに3件のパーティをキャンセルしているんですよ」
水を差すのは得意なのかそれとも偉大なる教育の賜物なんだろうか、ハルトヴィックとシュナイダーの奴らは。
ベルンハルトもさすがに肩を竦めると、彼の忠実な部下の方に振り返る。その横顔には、彼が通りで見せたあの笑みが―俺が好きなまるで新しい遊びを見つけた子供みたいな顔さ―浮かんでいて、俺は嬉しくなった。
「私は此処に残る。
その調子で他の予定もキャンセルしておいてくれ、シュナイダー、ハルトヴィック。
有能なお前たちだ。それくらい何の造作もないだろう?」
陸軍大佐の言葉ってのは、奴らにとってはどうやら絶対に逆らうことのできないものらしい。
「しかし、ゲネラーレ!」 ハルトヴィックの抗議の言葉は歯切れが悪かった。俺を取り囲んで散々好き勝手言ってくれた奴とはまるで別人さ。
パーティのキャンセルと謝罪を偉大なるゲネラーレから直々におおせつかったシュナイダーとハルトヴィックは、俺とミゲルに恨めしい顔を向けると、警察署から足早に立ち去った。
特別任務を与えられたんだから、仕方が無い。それが仕事って奴さ。
*
その後、俺たちのいちゃつく様子にうんざりした顔をしたミゲルが後は好きにしろと―そういう意味だと俺はいまだに信じている。スペイン語は一言も分からないんだ―言い残して店に戻り、ホールには俺達だけが残った。
「さて、と。ベルンハルト。残ったのは俺とアンタだ。此処に残るって、アンタ、まだどこか何か行きたい場所でもあるのか?どこだっていいさ。俺が連れてってやる」
「違うんだ。クリストフ」
彼は口ごもる。それは自分が何を言うべきか、言葉を捜しながら考えを組み立てようとしている様だった。落ち着いた、飄々としたゲネラーレとは程遠い、ある意味ではとても人間臭いためらいがちな物言いに、俺は少しばかり驚いた。
「クリストフ。なぜ私の部下が夕べ君達のショーを予約したのか、その理由は覚えているか?」
「覚えてるぜ?明日がフリードリヒの誕生日で、その前祝いだって」
「その通り。つまり、今日が私の誕生日だ。
毎年、この日が来るたび私は、私の部下達が勝手に組んだスケジュール通りに、あちこち駆けずり回っていた。
だが、今年は少しばかり状況が変わってね」
不意に彼のたくましい腕が俺の身体をぎゅっと抱きすくめる。
温もりが愛しかった。
「一緒にいて欲しいんだ。クリストフ」
誓ったって良い。そんな台詞を言い慣れている様子じゃなかった。
ベルンハルトの顔には躊躇や、恥じらいや、たくさんの感情が入り混じっていた。伏せた睫がかすかに震えていた。
「俺もさ。さっきアンタとキスしてから、二人きりになりたくて堪らなかったんだ。ベルンハルト」
彼は答えの代わりに俺の手を取ると、指先を彼の形の良い唇を押し当てた。彼は夕べの俺の考えどおり、俺が今まで出会った誰よりもきれいだった。
まるで出来過ぎたB級映画のワンシーンみたいじゃないか。
だけど俺は、そんなB級映画が嫌いじゃないんだ。