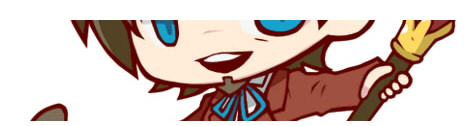
!! R-18 !!
現パロ同棲設定
現パロ同棲設定
君と迎える新年
君と繋がって年を越したい、と言ったのは私だった。きょとんとした彼に強引に口付け、いいだろう?と言えば、やっとその気になったのか、私を抱き寄せてくれた。
その力強い腕に身を任せるのが、私は大好きだった。
背後のテレビでは、俳優や芸人がやかましく騒いでいる。先ほどまでは音楽の番組をつけていたはずだがいつの間に番組が変わったのだろうか。だが、そんなことはどうでもいいことだ。ただ目の前の肩にしがみついて荒い息を吐く。吐けばその分だけ腹の中の肉全てで自身を貫く男の器官を感じられる気がした。
少しだけ腰を揺らして切なさを沈める。もう何度も何度も繋がって慣れた場所は含まされたローションと綺礼の先走りでちゅぷちゅぷと音を立て、それが卑猥で好きだった。今、私は綺礼と、いやらしいことをしている。そう思えるので。
その仕草が、綺礼にはねだるように伝わったのだろうか。綺礼は太い腕で私の腰を抱え直し、緩やかに突き上げてくれた。ああ、と喉から意識しない声が出る。力が抜けてかくん、とのけぞった喉に、綺礼は唇を押し当ててくれる。ひんやりとしたそれがむちりと押し付けられて、その後に一瞬吸い上げられる感覚。跡を残されたのだ。
その唇は私の喉にいくつかの跡を残したあと、そのまま下って鎖骨や胸元にも同じことを繰り返す。何だか悔しくなったので、その頭を押し返して私も綺礼の首元に吸い付いた。真っ赤な跡を残せたことを確認すると、同じように肩や喉に同じものを残す。
彼があぐらをかいた足の上に私は座っているので、胸元まで口は届かない。仕方ないのでしがみついていた腕を一旦解いて綺礼の胸元をまさぐった。寒さに硬くなったその突起の上へ手のひらを当てると、何だかむっとした視線を向けられる。綺礼が私のものをいじるのはいいのに、私が綺礼のものをいじるのは駄目らしい。殆ど見せない彼のわがままを垣間見たような気がして、私は吐息だけで笑った。
それもどうやら気に食わなかったのか、私の腰を抱いていた腕を外して、綺礼が私の胸の突起を強く摘んできた。両側ともぎゅうぎゅうとひっぱられて、痛いはずなのにそれも全て快感に変わる。体内にくわえ込んだ綺礼を胸を引かれるほどに締め付けながら私は痛みを訴え続けた。
それは、嫌になるくらい甘い声。それが綺礼は好きだという。そんな声、私以外に聞かせないでしょう?と。
テレビからやかましい声がする。59、58、どうやらカウントダウンが始まったようだ。
絶頂が近い。また彼の首元にしがみついて、耳元で「イキそう」と囁いた。腹の中の綺礼がぐんと体積を増したのはどういうことだろうか。腸をさらに広げられる感覚に私はあえいだ。
44、43、知らない騒がしい声のタイミングとはずらして、綺礼が突き上げてくる。がくんがくんと体を揺すぶられ、力の入らない手足で必死に彼にしがみついた。突き上げられた反動で半ばまで抜け、私の体が落ちるタイミングで奥の奥まで突き上げて。その繰り返しだ。耳元で響く綺礼の吐息も荒くて、それが私にはとても嬉しい。
25、24、数字は小さくなって、テレビの中の騒がしさも増しているようだった。綺礼と私の吐息と、そのざわざわした声しか聞こえなくなる。
18、17、ぼんやりとその数字を耳で追っていた私の頬に、ふと触れるものがあった。綺礼の、綺礼の指だ。霞む焦点をなんとか合わせると、綺礼が私を見ていた。火照った頬、潤んだ黒い瞳、汗に濡れた髪。それがとてもとても愛おしくて、胸が締め付けられるようだった。激しくぶつけるようにキスを贈られる。その頭を掻き抱いて、私もそれに答えた。綺礼、綺礼。声にならない声で呼び続ける。こみ上げる愛おしさに涙がこぼれた。
震える膝を叱咤して、私も腰を揺らす。下半身も唇も激しく求め合って、もう互い以外のなにも見えなくなる。互い以外の何も聞こえず、互いだけが世界の全てになり、深く深くまで落ちていくようで。
「〜〜〜ッ!!」
「うぁ―――ッ」
綺礼の硬い先端が私の中の弱いところを強くえぐって、その刺激で私は達した。同時に綺礼がうめき声を上げ、ひときわ大きく内蔵が押し上げられて温かいもので満たされる。彼が、私の中で達したのだ。力の入らない足で必死に腰を押し付けて、最後の一滴までも注ぎ込まれる感覚に酔う。絶頂の余韻に震える体を抱きしめ合う。
音が、戻ってきた。騒がしい声は口々におめでとうおめでとうと繰り返している。拙い日本語の発音でハッピーニューイヤーと言うのに、もう年は明けたのだと知る。
ちらりと綺礼を伺えば、彼はまだ瞳を閉じたままはあはあと荒い息を付いている。私を膝の上に抱えて動いていたのだから、疲れたのだろう。
「――あけまして、おめでとう」
正面から見つめて声をかければ、そのまぶたがゆっくり開く。覗く漆黒の瞳に映されれば、心臓がとくりと暖かく脈打つのを感じた。
「――おめでとう、ございます」
「今年も宜しく」
「こちらこそ」
後頭部に添えられた手に従って頭を落とせば、柔らかく唇が迎えてくれた。ちゅ、ちゅ、と触れ合うだけの、優しいキス。前髪が触れ合ってさらさらと音を立てるのも楽しい。胸をすり寄せ目を閉じて、優しいキスに夢中になった。
テレビからは騒がしい声と笑い声が聞こえてくる。背を向けているので何を言っているのかは分からないが、きっと新しい年になったことが嬉しいのだろう。きっと世界中も、私のように。
ふと綺礼が動き、少し置いてその音がぷつりと消えた。
「綺礼?」
「私だけに、集中していただきたかったので」
「きれ、うわっ!」
テレビを消されたのだ、ということに気付いた時には、私は炬燵の天板の上に倒されていた。繋がったままのところが刺激されて、軽く達する。足を大きく広げたまま見上げれば、電灯を背に、真っ黒なシルエットになった綺礼がそこにいた。
「――きれい」
「時臣さん」
ぎゅうと抱き寄せると、また綺礼が腰を使い出した。揺さぶられて、また私は甘い声を上げる。裸なのに寒くないのが不思議だった。抱き合った体を離され、改めて指を絡められる。こいびと、という感じがして気恥ずかしくなり、私は口を開く。
「ね、きれい」
「何ですか」
「ひめはじめ、は、2日の行事、だよ」
「……集中して下さいと、言ったはずです」
「あんっ!」
大きく突き上げられて、その分大きな声が出た。今の声は少し、好きじゃない。優雅じゃないから。だからもうそんな声を上げさせられないように、私は綺礼に集中することにする。
強く指を絡めて、繋がったところを揺らしあって、時々名前を呼んで口づけて。
二人以外の音がなくなった部屋の中で、私は酷く幸福を感じていた。
願わくば、綺礼もその幸福を感じていますように。
そんなことを考えながら、私は彼に口づけをせがんだ。
あけおめ師弟ちゃん。
らぶらぶと見せかけて
時臣の片思いかもしれない。
そもそもほとんど名前が出てないので
師弟かどうかもあやしい。
らぶらぶと見せかけて
時臣の片思いかもしれない。
そもそもほとんど名前が出てないので
師弟かどうかもあやしい。