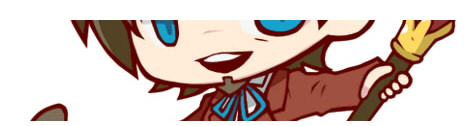
!! R-18 !!
遠坂邸にギルガメと凛が同時にいるので
花札かなんかの平和時空だと思います。
遠坂邸にギルガメと凛が同時にいるので
花札かなんかの平和時空だと思います。
リボンの似合う貴方
数日前に父から欲しいものはあるかと聞かれ、綺礼は特にありませんと答えた。そうか、と彼の父は言い、少し考えこんでから、それでは今年も酒を選んで贈ろうと言ってくれた。
その後師からも同じ問いをかけられ、綺礼は不思議に思いながらも同じ答えを返した。
そうか、と師も言い、少し考えこんでから、それでは何か考えておこうと言ってくれた。
そしてその数日後、すっかりその問答のことを忘れていた綺礼へ、彼の父は1本のワインを贈ってくれた。
お前の生まれ年のものだそうだと差し出された瓶には真っ赤なサテンのリボンが巻かれており、父はそれを渡す際、「誕生日おめでとう」という言葉を添えてくれた。
(そうか、私は今日誕生日だったのだ)
その瞬間ようやく、綺礼は数日前の二人からの問いの意味を理解したのだった。
(つまり、師も私へ、何かを贈ってくれるつもりだったのか)
そう思い至った綺礼の足は、師である時臣の邸宅へと向かっていた。
数日前の問いかけ、あれが綺礼の誕生日を祝うためのものであるならば、「なにか考えておこう」と言ってくれた真面目な師のことである、その言葉のとおりに何かを用意してくれているに違いない。
綺礼と時臣は魔術の師弟というだけでなく、恋人のような関係でもあった。
そんな相手が何か贈ってくれるというのだ、期待しないわけがない。
自然ウキウキとした足取りになるのを宥めながらも、柄にもなく胸が高鳴るのを感じた。
「あら、言峰さん」
しかし尋ねた綺礼を迎えてくれたのは、師ではなくその妻の葵であった。
誰に対してもにこやかな彼女は、綺礼に対しても例外ではなく優しく微笑み、ようこそ、と会釈をする。
「お越しになるなら言ってくだされば良かったのに。時臣に用事ですか?」
「ええ。師はいらっしゃいますか?」
「ごめんなさい、先ほど出かけてしまったの。ギルガメッシュさんと一緒にね」
あの金ピカと。
跳ね上がった綺礼の眉をどのように受け取ったのだろう、葵は苦笑を浮かべた。
「時臣は、凛と一緒に貴方の家に行ってからって言っていたのですけれど、あの方は強引だから……」
時臣のサーヴァントは、どうやら時臣の家族に対してもあの暴君ぶりを発揮しているらしい。
とはいえ葵の苦笑を見る限り、それは手のかかる息子のように扱われているようだが。
「二人はどこへ?」
「それがわからないんですよ。一晩帰らんかもしれん、なんて言っていたから、すぐには戻らないと思うのですけれど……」
「……そうですか」
帰るのを待つ、という選択肢も、どうやら却下するしかないらしい。
嘆息する綺礼へ、すみません、ともう一度葵が頭を下げた。
と、そこへ。
「きっ、綺礼!? 何でここにいるのよ!」
高い声がかけられ、綺礼は振り向いた。
果たしてそこに立っていたのは師と葵の娘、凛である。
「聞いてないわよ、今日来るなん……あっ」
怒ったような顔でそこまで言いかけ、そこに母もいることに気がついたのだろう。はっとしたように口元に手を当て、うろうろと視線を彷徨わせた挙句に、こんにちは綺礼、と少しスカートを摘んで優雅なお辞儀をしてみせた。
その視線には、変わらず険を含んだままであったが。
「こんにちは、凛」
「……何でここにいるんですか?」
「師に用があってね」
「お父様はお出かけでいません。他に何か用があるんですか?」
つん、とした言い方と睨むような目を見ているとどうにもからかいたくなってしまうが、ここには葵がいる。彼女の存在は凛だけでなく、どうやら綺礼の立ち居振る舞いに対しても影響があるようだった。
「……いや、師がいないのならば特に用はない。帰るとしよう」
「ええ、それがいいと思いますわ!」
「あら、凛!どうしたの?」
普段ならば絶対にしないようなお嬢様口調で言い放ち、凛はまた屋内に引っ込んでしまった。
その勢いに驚いたのか葵が声をかけるが、凛は帰ってこない。綺礼と葵は目を見合わせ、苦笑するしかなかった。
「それでは、失礼します」
「ええ。時臣が帰ってきたら、連絡しますね」
「是非」
では、と言って一つお辞儀をし、邸から辞去しようとしたその時。
「綺礼!!」
振り向くと同時に、顔めがけて飛んできたなにかを片手で受け止める。
「お誕生日おめでとうございます!!」
受け止めたものが何なのか、と確かめていたので、凛がそれを言った時どんな顔をしていたのかは見逃してしまった。顔を上げた綺礼が見たものは、見たこともないほど荒々しく邸の扉が閉じられるその瞬間だけ。
だが、おそらくその瞬間の彼女は、舌を出すか思いっきり睨みつけるかのどちらかだっただろう。
何とも微笑ましいことだ。
綺礼が手のひらの上で開いた淡い赤の包みの中には、シンプルなデザインのボールペンが二本。赤と黒のインク色のそれの柄には、子供の小遣いで買うには少々値の張るブランドのロゴが踊っている。
きっと、父や母に相談に乗ってもらって選んだのだろう。
「……凛!ありがとう!」
「ちょ……っ、うるさいわよ、綺礼!」
「大事に使わせてもらおう!」
「うるさいってば!!」
声を張り上げて礼を言ってみれば、閉じていた扉が開いて凛が慌てた声を出した。
そのあわあわした姿を見てとりあえずの満足を得た綺礼は、ようやく自宅へと足を向けたのであった。
■ ■ ■
自宅に帰り着くと、どうやら父は出かけたようだった。
「どうやら聖堂教会とやらからの呼び出しがあったそうだ。一緒に飯を食えなくてすまないと伝えてくれ、と言われたぞ」
「……なぜお前がここにいる」
「あと風呂を沸かしておいた、だと。一応、ガスがもったいなくないかと言いはしたのだがな、お前が帰ってすぐにあたたまれるようにしたいとか言っておったぞ。全く、良い人間だ」
「答えろ。なぜお前がここにいるのだ」
代わりに聖堂にいたのは、何故かギルガメッシュであった。
誰もいない信徒席の真ん中辺りに座って、何をするでもなく祭壇の方を眺めている。
高いところにあるステンドグラスから色のついた光が降り注ぎ、金の王の髪を鮮やかに染めていた。
「いや、今日はお前の誕生日だと言うだろう。だから祝いに来てやったのだ」
「頼んではいないが」
「祝い事は頼まれてするものでもあるまい?」
振り返ったその手には酒の瓶がある。
一瞬、今朝父からもらったものかと身構えたがどうやら違うようだった。だがラベルに見覚えがあるので、おそらくは綺礼の私室から勝手に持ちだしたものだろう。
「しかし、折角我が来てやったというのに出かけているとはな!出かけるなら先に言え!」
「……それは、先ほど別の人にも言われたな」
「だがまあ、その御蔭で面白い趣向を思いついたから、良しとしよう」
「……」
嫌な予感しかしないことを言うものである。
眉根を寄せた綺礼に、ギルガメッシュはにやにやと笑うだけであった。
「……ところでギルガメッシュ。師と出かけたと聞いたが」
「ああ、そうだな」
「師はどこだ?」
「さあて、どこだかな。少なくても、今は一緒におらぬよ」
「見れば判る」
「クク、だろうな!」
何が面白いのか、彼は腹を抱えてけらけらと笑った。
「――そんなことより綺礼、我からのプレゼントをお前の部屋に置いておいた。鮮度が落ちるから早めに開けると良いぞ」
「鮮度?食べ物かなにかか?」
「まあ似たようなものだな。我が最後に見た時は随分活きが良かったが、今頃はどうだか」
「……生魚か何かか?」
「問うより礼はないのか?」
「欲しいとも言っていないのに押し付けられるものに、礼など言うつもりはない」
「――ほう?」
その粘るような視線に、またもや嫌な予感が沸き起こる。
「一つ予言をしようじゃあないか、綺礼」
「……何だ」
「次にお前が我と顔を合わせる時、お前は我に礼を言いたくて仕方なくなるだろう」
「……何だ、その予言は……」
どうやら、何の根拠もなく言っているわけではないらしい。
ニヤついた視線は何かを知っているらしく、綺礼を上から下まで眺めるも、その先の何処かを見ているようだった。
首を振って、綺礼はその視線を振り払う。
ここで彼と話している時間は、余り有意義なものではない。
ギルガメッシュと共に出かけたという時臣の行方も気にかかるから、とりあえずはギルガメッシュが置いたというそのプレゼントだけ確認して、師を探しに行こう。
そう考え足を巡らせた綺礼を、ギルガメッシュは見咎めた。
「ん? 部屋に行くのか?」
「ああ。……お前はそろそろ帰れ」
「つれないな」
そう言いながらも、ギルガメッシュは立ち上がった。
「まあ、プレゼントは大事にしろよ。我が心を込めて包んでやったのだ」
「お前がやったのは包んだだけか」
選んだり買ったりしたのはお前ではないのか、と言う意味での問いだったが、ギルガメッシュは含蓄を含んだ視線をこちらへ投げてにんまりと笑っただけだった。
「ではな! 良い誕生日を過ごせよ!」
言いおいて、ギルガメッシュは去っていく。
その手に酒瓶が持たれたままであることに気付いたのは、彼の姿が完全に見えなくなってからだった。
■ ■ ■
(……ふう……)
自室への道を歩きながら、綺礼はため息をつく。
師はいないしギルガメッシュは面倒くさいし、散々だった。
凛の慌てたり照れたりする姿が見られたのは良かったし、父からプレゼントをもらえたのも良かったが、その後のせいで随分と疲れてしまった。
師の行方は気になるが、探しに行くのは少し休んでからにしよう。父が風呂を沸かしてくれているというが、それは後にしたほうがいいだろう。
そう考えて、たどり着いた自室の扉に手をかけた時。
(……?)
中から音がすることに気付く。
衣擦れ程度のかすかな音だが、それは随分とせわしない。
(……ギルガメッシュのプレゼントとやらか……)
活きが良いだの鮮度が落ちるだの言っていた、それだろう。
――そうだ、それを片付けるという用事がまだあったのだ。
もうこのまま扉を開けずに回れ右したいところだが、そうも行くまい。鮮度が落ちるようなものをこのままにしておけばさらに片付けるのが面倒くさくなるのは、火を見るより明らかだ。
「はあ……」
今度ははっきりと声を出してため息を付きながら、綺礼は自室の扉を開いた。
キィときしむ蝶番の音に、油をささねば、と、そんなことを考えながら。
「……」
「あ、綺礼……」
「…………」
「…………」
今日、いないはずの人間がそこにいることで驚くのは二度目である。
一度目は先程のギルガメッシュ。
そしてもう一度は現在。
そのギルガメッシュが連れ去った時臣が、綺礼の私室にいると言うこの状況。
「………………」
「………………え、ええと、た、誕生日、おめでとう」
「……………………」
「……………………」
だがこれは、ギルガメッシュの時とは異なる驚きだ。
そこにいないはずの人間がいるというだけではない。
そこに『そんな格好で』いるはずがない人間がいる、というものも加えての驚きだった。
「…………………………」
「…………………………」
「………………………………」
「………………………………何か、言ってくれないか……」
入り口に立ち尽くした綺礼と暫く見つめ合った時臣は、消え入りそうな声を出してとうとう目を伏せた。
その頬は羞恥に赤くなり、泣きそうに白目が赤くなっているのが見えた。腰と足をもじりと動かしたことで、座っているベッドのシーツにしわが寄る。
「……あ、すみません…………」
綺礼は謝ってみたものの、その先に続ける言葉を失っていた。
何故ならば、その時臣の格好。
彼は、12月も末の冬だというのに、風呂に入るというわけでもないのに、全裸だったのだ。
いや、正確には全裸ではない――かもしれない。
その体に巻き付いたリボンを、服のうちにカウントするというのならば、だが。
「……何ですか、その格好」
「いや……王が、無理矢理。誕生日を祝うならこれくらいせよと……」
立てた膝を、時臣は内股に寄せる。
幅広の真っ赤なリボンが、その体にぐるぐると巻き付けられていた。
手首や腰にふんわりと綺麗に整えられた蝶々がいくつか見えるから、おそらくそれは一本ではないのだろう。
股間や胸といった際どいところを隠すようにして、しかし巧妙に手足を拘束している。そのせいで時臣はうまく動けないようで、まとめられた手首を胸元にやったまま柔らかいベッドの上でバランスを取ることに必死になっていた。
そのリボンの色は、いつも彼が身につけているのと同じ真紅。
なのにその隙間から見える肌の箇所はいつもと異なり、ぴっちりと巻き付いているせいで、普段は隠された体のラインもよく見えた。
「……そそりますね」
「そうかい? 私にはよくわからないな……」
逸らしていた視線をそろそろと綺礼に合わせながら、時臣は答えた。
なるほど、これがプレゼントというのなら、面白い趣向だの活きがどうとか言うのも理解できる。
おそらくギルガメッシュに無体を働かれた時に抵抗したのだろう、よく見ればベッドの上にあったはずの枕やベッドサイドに置いてあった時計が床に落ち、毛布もぐしゃぐしゃになっている。
ギルガメッシュが去るまでさんざん暴れて、今は少し疲れて鮮度が落ちている状態なのだ。
(……ふむ)
目的であった時臣も見つかったのだから、もう出る必要もないだろう。
綺礼はとりあえず部屋の内部へ足を進め、羽織っていたコートを脱いで壁にかけた。
時臣はそんな綺礼の行動をどこかそわそわした雰囲気を漂わせながら眺めている。拘束されていて動けないのだから、それしか出来ないのは当たり前だろうが。
しかし、随分とすごい格好だ。
恋人であるからして彼の素肌というのは見慣れたものではあるが、イレギュラーなもので隠されているだけでここまでそそるとは。
だが今は冬。屋内とはいえ綺礼の部屋には空調がないからこの格好ではずいぶん寒いに違いない。ちらりと視線をやれば、唇の色が悪いように思えた。
「……冷えていますね」
歩み寄りその腕に触れると、思った通りの冷たさが伝わってきた。
綺礼も今外から帰ってきたばかりだから指は冷えているはずなのに、まるで氷のような冷たさが指を登ってくる。
「王が、毛布などかぶらずこのままの姿のほうが、きっと喜ぶからと……」
「……そうですか」
よく考えれば、仕掛け人である英雄王は、綺礼よりも先にこんな彼の姿を見ているのだ。いや、やったのはやつだというから、もしかしたら裸体まで眺めているかもしれない。
先ほどまでは礼を言ってもいいかもしれないとも思ったが、やはり撤回だ。
そんな物思いに沈む綺礼を不思議そうに眺めていた時臣は、ぽつりと。
「――綺礼。これは嬉しいのかい?」
「え?」
「王は良いものだと言っていたのだが、私には寒いし動けないから不便なだけで……。綺礼はどうだろう?私がこんな格好をすると、嬉しいかい?」
自身の手首を戒める蝶々へと視線を移し、彼は小首を傾げる。
真紅のリボン、その隙間から覗く色の濃い肌の色、戒める力が強いのかリボンが食い込んで盛り上がった肉、見えそうで見えない体の一部。そして何より、その格好が良いものかはわからなくても羞恥を覚え、真っ赤になった頬。
「――ええ、とても。私は、好きですよ」
「そうか。……君が喜んでくれたのなら、良かった」
頬を赤くしたままくしゃりと微笑む時臣。
「――私が、プレゼントだよ。受け取ってくれるかい?」
「ええ。――もちろんです」
人に言われたからとはいえ、不安を抱いたままこんな格好まで彼はしてくれる。そんな事実に愛おしさが募り、綺礼は時臣の頬を両手で支えて唇を近づけた。
察した時臣も目を閉じてその口づけを受け入れる。柔らかい接触は冷たかったが、それでも愛おしい人に触れているという満足感が勝り、二人は何度も角度を変えてくちづけを交わした。
綺礼が舌先で時臣の唇をつつけば、彼のまつげが一度震えた後恐る恐る唇が開かれる。そこへ綺礼は性急に舌を差し込み、キスを深くした。
「んっ、あ……っ」
「ふ……」
息継ぎの間だけほんの少し唇を離し、長い長いキスを交わす。抱きしめるように舌を絡め、慈しむように頬を撫で。
その内に、触れ合う唇や綺礼が支える頬に体温が戻ってきた。
「……時臣師」
「綺礼……」
やっと唇を離した時には、二人共息が上がっていた。
息継ぎはちゃんとしていたはずだが、高ぶって上手く酸素を取り込めていなかったのだろう。
見つめ合う碧には黒が、黒には碧が、鏡のように映り合っている。
「――――良い、ですか?」
「私は、こんな恰好なんだよ。嫌だと言うとでも思うかい?」
「いいえ」
綺礼はくすりと笑い、少々お待ちください、と言って服を脱ぎ始めた。
筋肉のついた、うつくしい裸体がすぐにあらわになる。これを見る度時臣は、自身が絶対に辿りつけぬであろう力強い体を羨ましく思い、ため息をつくのであった。
「それでは失礼して」
下着までを脱ぎ捨てた綺礼は、そう声をかけて時臣をシーツの上へと倒した。
注意は払っていたが、ぼすりとシーツに沈む感覚に一瞬時臣が目をぎゅっと閉じる。体を支えようと思ったのだが、両手はリボンで戒められていたのだ。
「大丈夫ですか?」
「ああ。――でも、これはほどいてほしいな」
天井の電灯を背にのしかかってくる綺礼に、時臣は手首の蝶々を示す。ここだけではない。両足や腰にも何本もリボンが巻かれている。くすぐったいし、何より動きづらくて不便だ。
だが、きっと了解してくれるだろうと思っていた弟子は首を振った。
「それは出来ない問題です」
「な、何故だい?」
「貴方は私へのプレゼントなのでしょう? 私が貰ったものを開封するタイミングは、私が決めます」
「きれ、あっ」
咄嗟に綺礼の体を押しのけようとしたが、戒められた体は不自由で、のしかかられた体勢は不利だった。
上体を倒した綺礼は時臣の鎖骨を軽く噛む。上手く残った歯型をぺろりと舐め、時臣の体に落とすくちづけの位置を段々と下げていく。
「駄目、駄目だ、そこは……! ほどいてくれっ!」
時臣の懇願は届かず。綺礼が口をつけたのは右の乳首だった。
寒さのせいでか固く立ち上がっていたそこは、かぶさったリボンを押し上げるようにして主張していた。それが、とても美味しそうに見えたのだ。
滑らかなリボンの上から舌で押しつぶし、輪郭に沿うようにして軽く噛む。
「……っぁ、はぁっ……」
言葉にならない吐息を漏らし、時臣が体をこわばらせる。生命維持にも繁殖行為にも用をなさぬはずのそこは、度重なる行為と綺礼の指先によって、立派な性感帯へと育て上げられているのだ。
綺礼はさらに、空いている方の乳首へと片手を伸ばす。
こちらは先端に指先を当ててくりくりと回せば、ぶるりと時臣の体が震えた。それは冷たさにだったかもしれないが、じんわりと広がる快には体の熱が上がる。
戒められている手首は綺礼の体と時臣の腹の間で潰されているから、口を抑えることができない。せわしなくなっていく呼吸も隠すことはできないようだった。
「んっ、ふ、ぅ……」
「――っは……、いやらしい色に、なりましたね」
ぢゅ、と最後に音を立てて綺礼が唇を離す。綺礼の唾液に濡れたリボンは赤い色を濃くし、それを下から押し上げる部位もさらに固く尖っていた。
指で弄くられた方も同じように尖ってはいるが、リボンの色は変わっていない。
綺礼が両方のそこへ同時に指を伸ばせば、片方はリボンがペタリと張り付き片方はサラリと離れ、異なる快感が時臣の体を苛む。
「逆も舐めてほしいですか?」
「……っ」
言い当てられ、時臣の顔がまた赤くなる。
サラリとした感覚は嫌だった。それに、冷たいのも。指先は冷たくて、口内は温かい。それに、柔らかく噛まれるのはとても気持ちがいい。
「……なめて、ほしい」
「わかりました」
素直な態度に、よく出来ましたとでも言うように綺礼が時臣の額を撫でる。
そして再度頭を下ろし、先ほどとは逆の乳首をくわえ込んだ。びくんと大きく時臣の体が震えるが、気にせず舌を押し付ける。
片手でもう片方の突起をいじるのも忘れない。既に濡れたリボンの上からつままれるのはまた感覚が違うのか、時臣は胸をつきだしたままさかんに首を振って快楽から逃れようとしている。はあはあとせわしない吐息が、その口からは絶えず漏れていた。
やがてこちらも同じように濡れた色に染まり、ツンと尖る。
そろそろ、ここはいいだろう。そう考えた綺礼はおもむろに手を下に伸ばした。
「うあっ!?」
「お――っと」
時臣の体が跳ねる。咄嗟に綺礼が身を引かなければぶつかりそうな勢いだった。
そのまま体をよじり、不自由な腕をベッドに付きながら時臣が体を起こす。
「きゅ、急に触るなんて反則ではないかね!?」
「すみません、ルールがあるとは知らなかったもので」
「デリカシーが無いよ、綺礼」
ぷうと膨れる時臣の戒められた手首を持ち上げ、もう一度すみませんと言いながら綺礼はくちづけた。
「それではデリカシーのない弟子に、触れ方を教えていただけますか?」
「え?」
思ってもみない切り返しに時臣がぽかんとしている間に、綺礼は座り込んだ時臣の両足の間に割り込む。
足首にも蝶々があるので戒められているのだと思っていたが、どうやら脛から下にくるくる巻きつけられただけの飾りだったらしい。しかし股の間をくぐるような形で一本リボンが巻かれていたので、それはしゅるりと手早く解く。
「あっ!」
綺礼は時臣の足を割広げて挟まるような形で腰を近づけると、こぼれだした時臣の陰茎と既に露出していた自身の陰茎とを合わせ、時臣に握らせたのであった。
触れられるだけで感じるところがあるのか、時臣がふる、と体を震わせた。
「さあお願いします、時臣師」
「意地悪だな、君は」
「先程はいっぱい舐めてさし上げたでしょう?」
「っ……、はぁ、わかったよ」
握った手を、時臣がおずおずと動かしだす。
二本分をまとめてというのは掴みにくいのか、上下に扱くだけの動きもどこかぎこちない。
だがその拙さが逆に性感を煽るものだ。
「は……」
思わず綺礼が吐息を漏らせば、ちらりと時臣が視線を上げた。
続けて下さい、という意図を込めて視線を返せば、少しだけ微笑んで時臣が頷いた。
基本的には二本をまとめて強く握って両手を上下させて扱き、時々指先を血管に沿わせたり先端をくるくると撫でたりして、綺礼を追い詰めていく。
二人分の先端から溢れだした先走りが時臣の手を濡らし、その動きを助けた。
「ふ……っ、君のは、大きいな……」
「光栄、です……っ」
じゅぷじゅぷ鳴る水音を隠すかのように時臣が軽口をたたき、綺礼も答える。どちらも直接的な快楽に溶けた声ではあったが、自分だけが先に達してたまるかとでも言うような意地のようなものが込められていた。
時臣の手の動きだけでなく、擦れ合う二本の接しているところがそれぞれびくびくと震えたりぬるぬると擦れ合うのも、たまらなく気持ちがいい。
最初は柔らかかったものがどんどんと固くなり、固くなればなるほど擦れる時の刺激が強くなる。刺激を得てさらに固くなり、それがさらに刺激を与え、快楽は底のない沼のようだ。
「……師よ、少しそのままに」
「? ――――あっ!」
時臣に陰茎を握らせたまま、綺礼は大きく腰を動かした。
まとめられたそれがずるりと大きく擦れ、これまでと違う感覚に時臣が高い声を上げる。
そのまま何度か腰をグラインドさせれば、時臣は二本が離れないように握ることしかできなくなる。あ、あ、ととぎれとぎれの声が間断なく上がり、綺礼の耳を楽しませた。
「くぅ……っ、だ、駄目だっ……!」
「イきそうですか? どうぞ、出して下さい」
そろそろ綺礼も絶頂が近い。力の抜けかけた時臣の指を上から握り、腰を押し付けるように揺する。二人分の手のひらの下で二人分の陰茎が跳ね、先走りをどっとこぼす。
いつしか時臣も大きく足を開いて綺礼の動きに合わせるように腰を揺らめかせ、いつもの交合とは違う快楽に夢中になっているようだった。
「――――ッ!!」
先にはじけたのは時臣で、ひときわ強く跳ねたそれに刺激された綺礼も弾ける。
二人分の手のひらが先端を包み込んでいたせいで射精の勢いは殺され、長引くような快感を二人の体へともたらした。ぴんとつま先を伸ばしてがくがくと二三度体を震わせた時臣は、はあ、と一つ息を吐いて全身から力を抜く。二人は凭れあうようにして、暫く荒い息をついていた。
気だるさを押さえて陰茎にかぶせていた手を外せば、大量の精液が指先に粘っこくまとわりつく。力の抜けた二本の陰茎がくたりと寄り添い、濡れて冷えそうな肌を温めているように見えた。
いつの間にか、体は程よく温まっている。時臣など汗すらかいているようだ。やはり寒い時には体を動かして温めるに限る、と、雰囲気にそぐわないことを脳内で考えてしまい、綺礼は一人頭を振った。
「……失礼します、師よ」
「ん……」
ちゅ、と額にキスを落として、その体を再度横たえる。一度上り詰めた体は抵抗せずシーツに沈んだ。
体に巻き付けられていたリボンはところどころ解けたりずれたりし、だらしなく絡まっている。先ほど綺礼の責めた乳首もリボンからはみ出して、赤い色と腫れて尖った形を主張していた。乳首や陰茎や、そう言ったところが見えるようになったせいで、最初よりずっと卑猥な姿だ。もちろん、達した後の気だるそうな表情や下半身を汚す白濁液も、それに拍車をかけているのだろうが。
横たわった体の膝を割り広げても抵抗らしい抵抗はせず、奥まったところへ手を伸ばしても、その手首を緩く掴む程度の抵抗しかない。
綺礼のやりたいようにさせてくれるというのであれば、わざわざお伺いを立てる必要もないだろう。とは言え、先ほどのようにデリカシーが無いと言われるのも癪なので、触れますよ、とひと声かけてから綺礼はそこへと指を差し入れた。
「あ……」
精液の絡んだ指先は、狭い穴をこじ開けるようにして侵入を果たす。その筋肉すらも抵抗を見せないので、よほどもう、彼の体は準備が整っているということなのだろう。
「師よ、足を広げていただけますか」
「うん……」
つぅ、とシーツに皺を描きながらさらに膝が開き、全てがよく見えるようになる。
素直さを褒めるように、綺礼は優しく指を抜き差ししてやった。
「あっ、んんっ……」
内壁のどこを擦られても気持ちが良いのだろう。甘く低い声が途切れがちに上がった。
手首を返しながら二本目の指も挿入する。片方の指を曲げて浅いところにある弱いところを押し上げながら奥も同時に刺激すれば、ああ!と大きな声を上げて時臣の体が弓なりに反った。
快感が大きすぎるのか逃げようとする腰を押さえつけ、激しく指を出し入れする。
「んああっ! あぁッ!!」
さらに引き寄せるために太ももに絡むリボンを強く引けば、足首まで一本で繋がっていたようでM字開脚のような体勢を強いることになった。時臣は嫌がって足をばたつかせようとしたが綺礼の力の方が強く、抵抗は上手く行かなかった。リボンが食い込んでももの肉が盛り上がり、いやらしい凹凸を描く。
絡んだ精液が白く泡立ち、緩んだ後孔がはくはくと力なく綺礼の指を食んだ。一端は萎えていた陰茎もまた力を取り戻し、ふるふると震えている。
一度達しているからすぐに達することはないだろうが、余り前戯に時間をかけすぎて疲れさせるのも本意ではない。
弱いところを攻める動きから慣らすだけの動きに変えれば、時臣の全身からほっと力が抜けるのがわかった。
激しい抽送に緩んだ場所へと三本目を差し込んで中の方まで開く。
「辛いですか?」
「……」
問いかけには、首をふるという弱々しい否定が返ってきた。
止まった指の動きを責める用にゆらゆらと腰を揺らし催促をする姿からは、その否定が心からのものだということがわかるだろう。
綺礼は身をかがめて唇へと唇を落とす。
「もう少し、ご容赦ください」
間近で見つめ合ったまま、綺礼は四本目の指を揃えて、再度時臣の体の中へと差し込んだ。
至近距離で綺礼と目を合わせたまま、時臣の表情がとろりと溶ける。手を動かせば、こらえきれないように口が小さく開いて、熱い息を吐き出す。
胸の上でぎゅうと握られた両手に片手をかぶせて指を絡めながら、綺礼はもう一度キスを贈り、手を動かした。半ば作業のようだが、下準備をしっかりと行わなければつながることは出来まい。
時臣の手を離し、空いた手で同時に綺礼は自身の陰茎も扱きあげる。こちらは先程の一回では全然足りなかったらしく、すぐに元気を取り戻した。
「……そろそろ」
「時臣師?」
「もう、大丈夫だから、……挿れて欲しい」
吐息がかかるほどの近さで、時臣がぽつりとこぼす。
言葉の通り綺礼の指を包む内蔵は程よくとろけていて、四本もの指を咥えこんでいるというのにその締め付けはふわふわと優しい。
最後に指先で内壁をするりと撫で、全ての指をそこから抜く。一瞬だけぽかりと空いた孔はすぐに収縮するが、その縁は腫れて膨らみ、見るからに柔らかそうだ。それがひくひくと震えて誘うのだから、綺礼の欲望がさらに膨らんでしまうのも仕方のないことである。
時臣の開いた足を肩にかけ腰を持ち上げながら、柔らかいそこへ先端を押し付けた。
「それでは、お言葉のとおりに」
「っ、あ、あ、」
ぬっ、と先端が侵入を果たし、続いて幹も飲み込んでいく。
泣きそうに顔を歪めた時臣は、自身の体が綺礼を飲み込んでいく様から目を離せないようだった。
頭と幹の大きく膨らんだところを通過する度に限界まで縁が広がりぴりりとした感覚が走るが、それは痛みでは無く、快感だ。
やがて全てを飲み込ませ、ほう、と綺礼が大きく息をつく。その満足気な吐息の音に、時臣は胸を締め付けられるのを感じた。
「やっ、やだ、綺礼、ほど、ほどいて……」
「そうですね……、ええ、わかりました」
うわ言のように呟きながら差し出した震える手首は、やっと綺礼の手が受け止めてくれた。しゅるりと解かれるリボンは精液や汗で濡れて、綺礼の手から離れてシーツへと重たげに落ちる。
「きれいっ」
とたんに抱きつかれ、綺礼は体勢を崩しそうになるのを慌ててこらえた。
時臣は両手と両足の全てを使って綺礼をぎゅうぎゅうと抱きしめる。ついでに内蔵にも力が篭っているようで、綺礼は首と腰を締め付ける力だけでなく自身の陰茎を思いっきり食い締められる苦しみと戦う羽目になった。
「どう――どうされたのですか、師よ。苦しいので、力を――」
「――すきだ、綺礼」
その体を引き剥がそうとした手が、止まる。
間近にある濡れた碧が綺礼をまっすぐに映していた。
「それを言いたかったんだ、綺礼。君がうまれた日に何を贈っていいかわからなくて、でもこれだけは伝えたかった。綺礼、愛して――」
唐突に饒舌になった唇を、己のそれで塞いた。
照れ隠しのようなその行為に時臣も応え、激しく二枚の舌は絡み合った。ぷは、と離れた唇から零れる唾液を指先で拭ってその指先を咥えさせる。指に吸い付く唇の上から唇を重ねれば時臣の体からは徐々に力が抜け、綺礼もようやく楽に息がつけるようになった。
「あんっ!」
そのまま反動をつけて腰を打ち付ければ唇が外れ、高い嬌声が漏れた。
かくんとのけぞる喉に喰らいつき、反った腰の下に手を入れてさらに中をえぐるように穿つ。時臣の口からは有耶無耶になった言葉の続きが語られることはなく、意味のない言葉だけが飛び出していった。
浮いたつま先や足首に絡んだリボンが綺礼の背に落ちてくすぐる。その些細な刺激すらも背筋に快感を登らせるようだ。綺礼は目前の体を2つに折り曲げるような体勢で、さらに奥を目指して腰を振った。
「あっ、あっ、あ、――っあ、きれいっ」
弱々しくなった時臣の腕がもう一度首を引き寄せようとするのに、綺礼は抵抗はしない。
震える手のひらに誘われるように優しくくちづけを落とし、繋がった腰を揺する。ふさがった唇から満足気な呼気が吹き込まれ、指先は綺礼の耳の裏をなでた。
「時臣師」
「んっ、きれい――」
ぎ、ぎ、と鳴る寝台のスプリング。それに紛れて呼ぶ声と呼ぶ声。抱き合って快楽に融け合って、一つになっていくようだ。
「っ、すみません、師よ、もう――っ」
「いい、いいよ、綺礼、いいから、なかに――!!」
許可は得た。
直腸の行き止まりに先端を押し付け、綺礼はそこに欲を放つ。
「ふ――くっ、」
「あっ、――ッ!!」
脈打ち暴れる陰茎に腸をひときわ大きく押し広げられ、時臣も同じタイミングで射精していた。
がくがくと震える体を強く抱きしめ、綺礼は最後の一滴までもをその体に注ぎ込む。受精を望む獣のように。それを受け止める胎がないとわかっていながらも、愛と祈りを込めて。
「……」
「……、んっ」
時臣の弱々しい指先が綺礼の髪をくしゃりと撫で、綺礼は顔をうずめた時臣の胸元に触れるだけの口づけを落とし、暫くの間二人はぼんやりと、余韻に浸っていた。
そしてやっと、先に動き出したのは時臣。
拘束するように強く抱きしめてくる腕を軽く叩いて緩ませると、綺礼の肩にかけられたままだった足を下ろす。
が。
「……綺礼、抜いてくれないか」
「嫌です」
「……」
二度目の射精を遂げた綺礼の陰茎はまだ時臣の体の中にあり、多少は力を失っているものの、その硬度はまだ十分だ。
「まだ、したいかい? でも私はもう疲れて……」
「ですが、貴方がプレゼントなのでしょう?」
形は崩れたとはいえまだ足首に巻き付いているリボンをつまみ上げて示す。時臣の顔がさっと赤くなるのは、ようやくプレゼントになるということがどういうことなのか理解し始めたということなのだろうか。随分遅すぎることだが。
最初は綺麗に巻き付いていたリボンも、もうほとんど解けてしまっている。かろうじて足首のそれだけがリボンの体裁を整えている程度で、手首のものは綺礼が解いてしまったし、胸や腰に巻き付いていたものもずれたり緩んだりして、もう体に引っかかっているだけという状態だ。
しかし、昂揚し火照った体に巻き付く赤は、やはり淫靡に映えて見えた。
「先程はあんなに熱烈に抱きしめてくださったのに、心変わりですか?」
「あっ、あれは! ……その、気の迷いだ」
「貴方は気の迷いで愛をささやけるような方だったのですか?」
「……うぅ」
綺礼の口調は責めるようなものだが、覗きこんでくる視線はにやにやと悪戯なものを含んでいた。
言い返す言葉を探す時臣を、ダメ押しで緩やかに突き上げてみる。反射的に上がったのは甘い喘ぎ声で、さらに意地悪さを増したにやにや笑いに時臣はさらに顔を赤くすることしか出来なかった。
「酷いな、君は」
「私は今日が誕生日で、貴方は私のプレゼントなのですから」
頬や額、顔中にキスを降らせると、赤くなった渋面が徐々に和らいでいく。
「……仕方ないな。も、……もういちどだけ、だよ」
「ええ、ありがとうございます。――少し、体が冷えていますね」
落ち着いたからだろうか、体温が下がって、絡めた指先は冷たい。
綺礼の腿に乗っている膝から脛をたどって足裏に触れても、そこも随分冷えていた。
「そういえば、父が風呂を沸かしてくれていたと」
「ああ、言っていたね」
「それでは、続きは風呂でしましょうか」
「それは……、いや、うん、そうだな」
思ったよりもあっさりと時臣は頷いた。
驚きが顔に出てしまったのか、時臣は綺礼をじとっと睨みつける。
「何だい、その顔は。私は君のものなのだろう? 君の提案を受け入れるのは、当たり前じゃないか」
さらりと放たれたその発言に。
慌てて綺礼は顔をそむけるが、その耳が赤くなっているのを、時臣はしっかりと目にした。
「……それでは、風呂までお連れします」
「ああ、頼むよ」
埋まっていた陰茎をずるり引き抜き、綺礼は時臣を横抱きに抱き上げる。
引きぬいたその瞬間小さな嬌声が上がったが、時臣は思ったよりもしっかりとした力で綺礼の首筋にしがみついた。その体からほどけたリボンがはらはらと床の上に落ちて行く。
少し冷め出した体温をまた上げたいとでも言うように固く体をすり寄せ合い、綺礼は彼を抱く腕に力を込めた。
「――時臣師」
「なんだい?」
「素敵なプレゼントを、ありがとうございました」
酷く近い位置で囁けば、時臣は一瞬ぽかんとした表情を浮かべ、そしてくしゃりと破顔した。
「――喜んでもらえたなら、何よりだ」
その足から、最後のリボンがはらりとほどける。
プレゼントだった名残を全て失った時臣は、それでも綺礼の腕の中で静かに微笑んでいた。
綺礼さん誕生日おめでとうございます!
プレゼントは全裸リボンの時臣師です。
なんかどうしてもキャラクターをどこかに忘れてきたタイプの
イチャラブマボワしか書けないんですが
もう諦めようと思います。
プレゼントは全裸リボンの時臣師です。
なんかどうしてもキャラクターをどこかに忘れてきたタイプの
イチャラブマボワしか書けないんですが
もう諦めようと思います。