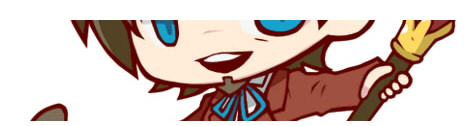
時臣師がファミレスでメニューを頼めない話
「師よ、すみません」開口一番、そんな謝罪を述べた弟子を、私はきょとんとして見つめる。
いつも通りの漆黒のカソックに金色のロザリオ。精悍な顔立ちはいくら眺めていても飽きないが、彼のそれは今、悲しそうに歪められている。
「ええと…何の話かな」
「今週末、デートの約束をしましたでしょう」
「デート…?デパートに一緒に行こうという話のことかい?」
「はい。師のぱんつを一緒に選ぼうという約束です」
なぜだか最近、自分の下着がよく駄目になってしまうのだ。洗濯を任せた綺礼が、生地が傷んでいたので捨てましたと言うのを、何度か聞いたと思う。余りにそのペースが早いので買い置きもなくなり、今日などは申し訳ないことに綺礼の下着を借りているくらいだ。
新品ではありませんがとすまなそうに黒いそれを渡してくれた優しい弟子を前に、もう同じメーカーの下着を買うのはやめようと私は誓った。1日2日で駄目になるなど、一体どんな基準で作っているというのだ全く。
…まあとにかく、下着がなければ生活にも支障が出る。だから週末にでも買いに行こうと思って、せっかく出かけるならばと綺礼を誘ったというわけだった。
「それがどうかしたかね」
「大変申し上げ難いのですが、少々予定が入ってしまいまして」
「予定?」
「父が、来いと」
璃正さんの用事なら、それは優先すべきことだろう。親子の時間も事情も、いつでもできる買い物なんかよりはずっと重要だ。
少々残念だが、仕方あるまい。
「しかし午前中で終わる予定なので。…師とのデートは、午後からにさせて頂けませんか」
「デートじゃなくてデパートだよ」
言い間違いを直してやって、だが、一緒に出かけられるということはやはり嬉しい。一旦駄目かと思ったからなおさらだ。思わず笑そうになるのをこらえる。
「教会かい?」
「はい」
「なら、終わる頃に迎えに行こうか。教会からデパートまでなら、一旦こちらへ寄ると遠回りになってしまうからね」
「いえ、それだと師の方が遠回りになってしまいます」
デパートは、我が邸宅からと教会からと、ちょうど同じ程度の場所にあるのだ。どちらかがどちらかへと迎えに行けば、その分無駄足になってしまう。
「それでは、こういうのはいかがでしょうか」
綺礼が少し首を傾けて、言う。
「デパートへ向かう道の真ん中辺りで待ち合わせをするというのは」
「なるほど、それはいい考えだね、綺礼」
どこか待ち合わせに良さそうな場所はあるだろうかと問えば、
「確か…ファミレスがあったような」
「ふぁみ…ああ、Family Restaurantか」
一度だけ、葵と凛とそれから綺礼と、4人で行った記憶がある。一つ一つのスペースは狭かったが、まあ、しばらく待つのに使うくらいならば問題ないだろう。
それに、とてもたくさんのメニューが揃っていたことが強く心に残っている。あれだけの種類ならば、鍋もボウルなどもたくさん使うだろうに、よくもあんなに狹い厨房に収まっているものだ。空間圧縮の魔術のようなものでも使っているのだろうかと思ったが、一般の人間にそんな高度な魔術が使えるはずもあるまい。単に収納技術が高いという事なのだろう。
あの時は肉料理を頼んだのだったか。想像していたよりもずっと美味しかったので驚いた記憶がある。
「昼食を私が作れないので、ついでにお昼を取られるといいと思いますよ」
「なるほど…。うん、そうだね」
様々な料理が乗っていたメニューを思い出す。綺礼の料理だって美味しいけれど、たまには、そういうのもいいかな、と、思った。
「そうしようかなあ」
「そうするとよいでしょう」
ふっと軽く息を吐いて、綺礼が微笑んだ。
「是非、麻婆豆腐丼を頼まれるといい。あそこの麻婆は絶品ですよ」
そして週末である。
肌寒くなった季節、私は外套とマフラーをしっかり身に着けて、とある建物の前に立っていた。
「…………」
ファミリーレストラン、である。
「…………」
年甲斐もなく緊張している自分に気づく。
全く、いくつになっても初めての挑戦というものは気を張ってしまうものだ。しかも、今は一人。葵も綺礼もいないのだ。自分で、なんとかするしかない。
入り口は狭く、そっと中を覗いてみると待合室のようになっていて、家族と思しき2組が談笑しているのが見えた。そこは記憶にある。確かそこに並んで、呼ばれるのを待つのだ。
私は意を決して、扉に手をかけた。足を踏み入れた瞬間ピンポーン!と何かの音が響き、私は驚いて足を止める。
「いらっしゃいませー!」
そんな私の前に、元気な声を上げて一人の店員が駆けてきた。制服の赤いエプロンに染めたらしい安っぽい金髪の青年だ。
「こちらにお名前をお書きくださァい」
指し示されたボードに歩み寄ると、既に複数人の名前が記載されている。先人たちに習い、トオサカ、とカナで記載した。
「トーサカ様。お一人さまですかァ?」
「あ、いや、後で連れが来るから、二人だ」
「おフタリ様。おタバコは吸われますゥ?」
「いや」
「承知いたしましたァ!それでは、こちらへどーぞォ」
にこやかな笑顔のまま、店員は私をどこかへ案内しようとする。え、いいのだろうか。私の前にまだ2組いるというのに。私はその2組を伺うが、後から来た私が先に案内されようとしていることを気にしている様子はない。
「お客様ー?」
「あ、ああ。すまない」
店員の不審な視線を受け、私は慌てて彼の後を追った。
どうやら、今現在丁度お昼時ということでかなり店内は混んでいるのだそうだ。特に家族連れなどの多人数席が混んでいるのだとか。それに、禁煙席より喫煙席の方が人気があるらしい。だから、一人…いや、二人連れである禁煙者の私が先に案内されても問題はないそうなのだ。店員の青年に聞いたら教えてくれた。
「お水とメニューでェす。あとこちら季節のメニューでェす」
「ああ、ありがとう」
更に何事か店員は言おうとしていたが、最近の若者独特の言葉を伸ばす喋り方が耳障りだったので、微笑んでそれ以上の言葉を拒絶する。 店員の青年は小さく会釈して去っていった。
(さてと…)
案内されたのは、一番奥の窓際の席だった。窓の外を伺えば、寒さにか肩をすくめて早足で歩いて行く人々。綺礼が通ればわかるだろう。
店内に視線を戻すと、低いパーティションで区切られてはいるが、各座席に様々な人達がいるのが見えた。家族連れだったりカップルだったり、友達同士なのだろうか、若い女性同士のグループなども伺えた。彼らの手元には様々な皿。本当に、不思議な空間だ。
外套を脱ぎ、畳んで座席の隅に置く。これは、この前来た時に葵に教えてもらった作法だ。あと、配膳された水は無料で勝手に飲んでいいそうだということも。
安っぽいプラスチックのグラスに注がれた水に口をつけ──喉が渇いていたから思わず飲んでしまったが、あまりいい味はしなかった──メニューを手に取る。
「ふむ…」
表紙には『旬の食材』のタイトルと、いくつかの料理が並んでいる。それらは全て、きのこを使った料理のようだった。ハンバーグにパスタ、器はグラスと同じく安っぽく見えるが、廉価で提供するにはしかたがないことなのだろう。どれも、見たことがないほど安かった。
ぺらりとめくると、そこにもたくさんの料理が乗っているのだ。匂いすら漂ってきそうな鮮やかな写真である。洋食、和食、中華。様々な料理。焼いた肉に無造作にかけられたソース、ふんわりと炊かれた白米。つややかなスープの色。
そのうち、一皿が目についた。麻婆豆腐丼。綺礼のオススメのそれだった。小さく腹がなって、慌てて押さえる。そっと辺りを伺うが、誰かの耳に届いた様子はない。
当たり前か。ここは、とても賑やかだ。
人の多さと普段の環境とは違うところにいるといる緊張感から気にも止めていなかったが、こんなに賑やかな場所に来るのはいつぶりだろうか。聖杯戦争が始まった後はもちろん、その前だって、こんなに賑やかな場所に行った記憶は思い出せなかった。
人がたくさんいる。笑っている。楽しいのだろうか。楽しいのだろうな。
ふいに綺礼に会いたくなった。理由は分からないが。綺礼と二人で、この席に向かい合って座って、このメニューの中からとても安いものを頼んで、行儀悪く喋りながら、笑いながら、食べたいと思った。
それはきっと、とても楽しいだろうと思う。
そんなもの思いにふけっていたが、ふいに視界に時計が入って現実に戻った。
針は、随分と進んでいた。
はた、と私は、まだ手にメニューを持っていることに気づく。
「………」
そういえば。
…………これは、どうやって頼むものなのだろうか。
「……………」
首筋に、汗が流れる気配。
店員が頃合いを見て注文を取りに来るのだと思っていたが、どうやら違うらしい。恐らく私がここに入ってから30分は経っている。なのに店員が来る気配がないから、そう推理できる。
「…………………」
なんということだ。こんなことはあってはならない…あってはならないことだ!混乱に視界が揺らいだところで、ここが外であることを思い出す。いけない、家訓を忘れそうになっている。
いかなるときでも優雅たれ、だ。私は、周囲に気取られないように首を振って小さく深呼吸をした。
そういえば、先程の店員は何かを言いかけていた。あれは、注文の仕方を教えようとしてくれていたのではないだろうか。だとしたら、私はなんと愚かなことをしてしまったのだろう。
わからないならば、周りと同じようにすればいいのではないか。そう思って辺りを伺うが、ここから見える範囲のテーブルはすでに料理が並んでいて、新たな注文をしそうな気配はない。
店員は忙しそうに店内を歩き回っている。せめて彼らの一人でも、こちらの注文したそうな気配に気付いてくれれば良いのだが、それを一方的に望むわけにもいくまい。しかも奥の角の席であることが仇となり、偶然こちらに向かって歩いてくるというのも考えにくい。
ならば大声で呼んでみるか?いや、しかし先程からそういった大声を聞いた記憶はない。なにか他のシステムがあるはずだ。
この前来た時、綺礼はどうやっていただろう。
(綺礼…)
葵がパスタを、凛がお子様ランチというプレート料理を、綺礼はそういえば、麻婆豆腐を頼んでいたのだったか。凛と綺礼が、美味しいと喋っていたことを思い出す。が、どうやって頼んでいたのかが、一向に思い出せない。
このままでは。
「………綺礼」
口の中で小さく彼の名を呼んだ、その時だった。
ふいに黒い影がさす。
「…?」
影は長い腕を伸ばして、私の前にあった小さな何かを取り上げる。
「お待たせいたしました、我が師よ」
影は私を呼んで、私の弟子の形になった。
このボタンを押せば店員が来て注文を聞いてくれるのですよ。綺礼はそう教えてくれた。
「へぇ」
こんな小さい機械で、そんなことが出来るのか。どういった仕組みになっているのかは全然わからないけれど、次の機会があるならば、押してみたいと少しだけ思う。
「ちょうどいい時に来てくれて助かったよ。ありがとう、綺礼」
「いいえ。私の役目は貴方の補佐ですから」
首を振る綺礼に、私は自分が情けなくて苦笑する。
「全く…私は、君がいないと何にもできないね」
「それで、貴方は良いのですよ。聖杯戦争中の私は、貴方のための存在ですから。
私に、貴方の全てを任せてください」
無口な弟子の、いつになく饒舌な言葉。真っ直ぐな言葉に思わず照れて、頬が熱くなるのを感じた。
「…ふふ、頼り甲斐のある言葉だ。ありがたいね」
これからも、ずっとずっと頼りにしているよ、と言えば、相変わらず表情が読みにくい顔で、だけど微かに綺礼は笑った。
「ずっと、貴方の側に」
お待たせいたしましたァー麻婆豆腐丼二人前でェーす、と軽い声が響き、香辛料の匂いにまた腹が鳴る。
クス、と笑う弟子に、聞かなかったことにしてくれたまえ、全く優雅じゃない、とむくれて見せる私。
この穏やかな日々が、聖杯戦争が終わったその後も、続いてゆけばいいと思う。
私と彼の前に並ぶ同じ料理、同じように手を合わせて、ひとまずは、頂きますを。
そして涙を流しながらむせる私から顔を背けたお前の肩は震えていたね!
笑っているのだと分かるよ。何が私に任せてくださいだ!
注文を取りに来た店員になにか言っているとは思ったが、辛さ5割増しだなんて聞いていないよ!!
いつか仕返しをしてやる、と、まずい水を一気飲みしながら、私はそう誓った。
友人にネタを頂きまして。
弟子がいないと何にもできない系時臣師ってすっごく良いものだとおもいます。
自分もあまりファミレス行かない人種なので
何か間違っていたらすみません。
弟子がいないと何にもできない系時臣師ってすっごく良いものだとおもいます。
自分もあまりファミレス行かない人種なので
何か間違っていたらすみません。