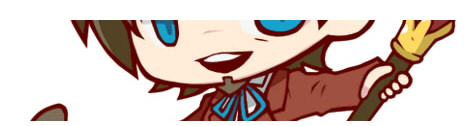
n番煎じのポケモンパロで、時臣さんがジムリーダーな設定
遠坂家がジムリーダー一家で綺礼は時臣の弟子
あと相当なエネコロロ推し
バトルフィールドに炎が巻き起こる。漢字の「大」の字に広がった炎は生き物のように、敵のミミロップを飲み込んだ。ミミロップは自慢の脚力で上空へ逃げようとするが、既に遅い。「だいもんじ」の主であるギャロップもまた地を蹴って空に居た。白い体躯は炎に包まれている。驚いたように目を見開くミミロップに、ギャロップ渾身のニトロチャージが炸裂した。遠坂家がジムリーダー一家で綺礼は時臣の弟子
あと相当なエネコロロ推し
「───そこまで!!」
凛とした少女の声が響く。
バトルフィールドから外れた審判席に立っていたのは、長い髪を両側に結った少女だった。彼女は小さな体で両手を大きく広げ、バトルフィールドの両端に立つトレーナー二人をけん制する。
もうもうと立った爆炎の中、目を回して倒れていたのはミミロップだった。
「勝者、ジムリーダー!」
その少女の声に、片方のトレーナーががくりと膝をつく。負けた挑戦者だ。彼はのろのろと腰からモンスターボールを取り出し、バトルフィールドで倒れているミミロップを戻す。
「…今回は私の勝利だったが、君と君のポケモンは随分とよくやった」
反対側から声が響く。ジムリーダーだ。彼も同じようにモンスターボールを取り出し、ギャロップを戻す。
思わず顔を上げた挑戦者が見たのは、穏やかに微笑むジムリーダーの姿だ。
「君の敗因は、主力であるそのミミロップに頼りすぎてしまったことだろう。力は重要だが、ポケモンバトルには相性も重要だ。相手のタイプと自分のタイプの相性を考えて見ることもおすすめするよ」
優しそうな声で語られるアドバイスに、敗北に落ち込んでいた挑戦者の顔は段々と明るくなっていく。そう、彼は炎タイプのジムに挑むというのに水や地面のポケモンを連れて来なかったのだ。相棒であるミミロップの強さに頼りすぎてしまった、というのは確かに、ジムリーダーの言うとおりなのである。
「…はい、ありがとうございます」
そして、ミミロップのモンスターボールを握りしめて、立ち上がる。
ジムリーダーが微笑む。
「準備ができたら、また来るといい」
そうだ。負けてしまったのなら、次は。
「───次は、絶対に負けません!!!」
トーサカジムは今日もしあわせ
「お疲れさま、あなた」挑戦者が元気に出て行くと、ジムリーダーもやっとバトルフィールドを降りた。
そんな彼を迎えるのは、彼の妻だった。くすんだ緑色の長い髪を揺らし、愛する夫に微笑みかける。と、彼女の瞳は、彼の額に浮かぶ汗を見つけた。視線に気づいた彼は苦笑し、長い前髪をかきあげる。
「ああ…やはりバトルは熱くなってしまうね。どうしても家訓を忘れがちになってしまう」
「そんなことないわ。戦うあなたも、とても優雅で素敵よ」
女性はハンカチを取り出すと、ジムリーダーの額に浮かぶ汗を優しく拭きとる。彼は気持ちよさそうに一旦目を閉じたあと、ありがとう、と彼女に向かって微笑んだ。
「さてと…今日の予定は、もう終わりだったかな」
「ええ。予約していた挑戦者は、さっきの子でおしまいのはずよ」
「そうか。では、今日はあと、のんびり過ごすことにしよう」
「時間があるなら、この後一緒に育て屋の方まで来てくださるかしら?見せたいものがあるの」
「ああ、わかった」
応え、ジムリーダーはちらりと腕時計に視線をやる。
「それでは、丁度良い時間だし、その後はお茶にしようか」
ええ、と女性は微笑み、彼女の夫が差し出す手にそっと手を重ねた。
ここは、ポケモンリーグ直下にある町、トーサカシティ。この町にはほのおタイプを司るトーサカジムがあり、そのジムリーダーの名はトキオミといった。彼には妻のアオイと幼い娘のリンがおり、この3人がトーサカジムのすべてだ。ただ、今はもう一人、別のジムからトキオミに弟子入りしている青年が居るのだが、…彼の話はまた改めてしよう。
トーサカジムは単純な構造だ。リンとアオイとそれぞれバトルし、勝利すればジムリーダーのトキオミに挑むことができる。トキオミに勝利すれば、バッチを手にすることができる。変わった仕掛けもなく、たった3回戦えばバッチを手に入れられる仕組みなのだ。ただしその分、トレーナーたちの強さは大層なものであるのだが。なお今は弟子がいるため、アオイの代わりに彼が挑戦者の相手をすることになっている。
ちなみにジムの隣には、アオイが経営するポケモン育て屋もある。彼女は、バトルの腕はそこまででもないのだが、ポケモンブリーダーとしての才能は非常なものなのだ。彼女にポケモンを預ければ、普通に戦闘の中で経験を積ませるのと同じくらい強くなると評判である。それどころか普通では覚えない技を覚えたり、特殊な石を使わなければ進化しない形態になったりするのだ。
だから、トーサカシティにはジム戦を望むトレーナーだけでなく色々なトレーナーが訪れる、賑やかで活気のある街だった。
お茶を淹れて来ますので先にテラスへ行っていてください、というアオイの言に従って、トキオミはジムから繋がるテラスへ出る。広大な庭に面したテラスからは、庭を自由に駆け回るポケモンたちを眺めることもできるのだ。今は遠くに、トキオミの手持ちであるウィンディと、その子のガーディが連れ立って走り回っているのが見えた。
平和な光景を眺めながら、アオイが戻ってくる前に、とトキオミはテラステーブルとチェアの位置を直し、埃を綺麗に払う。そんなことをしているうちに、アオイではない人物がテラスに現れた。
「お父さま!」
きらきらした笑顔で駆け寄ってくるのは、トキオミの娘であるリンだ。父親によく似た茶色の髪は長く、両脇の高い位置で2つにくくっていた。トキオミの寸前で足を止め、彼女は大きく仰向いて尊敬する父の顔を見上げる。
「ジム戦お疲れ様でした、お父さま」
「ああ、ありがとう」
「わたし、お父さまが勝利して安心しました!」
しかし、そんな興奮気味のリンに、トキオミは諫めるような苦笑を向けた。
「勝利を喜んでくれるのは嬉しいが、そういうことを言っては駄目だよ、リン。我々ジムリーダーは、トレーナーたちの強さを測り、彼らが更に上を目指せるようになるのを手助けするための存在だからね」
「…はい、お父さま」
それでも敬愛する父の敗北する姿など出来れば見たくない、少々ファザコンの気のある娘であった。意気消沈する娘を見て、しかしトキオミは愛情を増した笑みを浮かべる。
「だが、リン。今日のジャッジは良かったよ。声も響いていた。何よりも公平だったしな」
そう、先程のバトルで審判を務めていたのはリンだった。彼女は、いずれ父をも凌駕するであろうポケモンバトルの才能を持っているのだ。できるだけバトルの雰囲気に慣れて貰いたいという父からの指示で、まだトレーナーになって間もない少女である彼女が、このジムでは審判を務めている。
「これからもこの調子で励みなさい。きっと君は、私よりも素晴らしいジムリーダーになるだろう」
「はい!わたし、お父さまの期待に応えられるよう、精一杯頑張ります!!」
父に褒められ、リンの表情はわかりやすいほどに輝いた。力強く頷く娘に、父も優しげに一つ頷いた。
───と、そこへ。
「トキオミ師」
もう一人の人物が現れる。
首にロザリオをかけ漆黒の僧衣に身を包んだ男である。優雅な佇まいの父娘、開放的なテラス、どちらにも似合わない出で立ちではあるが、トキオミは微笑んで彼を迎えた。
「ああ、キレイか。君も来たのかい」
「はい。まずは、師に勝利の祝福をと」
「だからキレイ、今リンにも言ったとおり、我々ジムリーダーの仕事とは…」
「しかし師よ、あなたの勝利は事実。我が師の勝利を祝うことの、何が間違っているというのでしょうか」
リンとは異なり言い返してくる彼の言葉に、トキオミは一瞬きょとんとしたあと苦笑を浮かべた。
「…まあ…そうだな。間違ってはいないだろう、ね」
「それならば改めて。勝利、おめでとうございます、トキオミ師」
「…ああ、ありがとう」
そんな二人の様子を交互に見、リンがぷうっと頬をふくらませた。
彼はいつもこんな風に彼女の父親に馴れ馴れしく、リンのできないことをやってのけるのだ。
それが、リンにはとても羨ましく、キレイに反感を覚える理由になっている。
キレイ、というのはトキオミの弟子である。彼はこの街の人間ではなく、隣町コトミネシティのジムリーダーの息子だ。リセイというそのジムリーダーは、年を召したためそろそろ引退を考えており、息子にジムを譲りたいと考えていた。そのため、他のジムで修行をしてきなさいと、キレイをトキオミの元へと送り出したのである。
コトミネジムはノーマルタイプを司るジムであるが、キレイは未だ自分の属性を決め兼ねている。父にもらったリングマとザングースは彼の良きパートナーではあるのだが。それも、この修業のうちに決めろと。それが、リセイからの命であった。
「お待たせしてすみません、トキオミさ…あら?」
家内からテラスに続く扉を開けて、今度こそ現れたのはアオイだった。夫の他に二人増えている事に気づき、ぱちぱちと瞬きをし、目の前に三人いることと、手にした盆にティーカップが2つしか無いことを確認する。
「あらあら、あとで呼びに行こうと思ったのに。もういるとは思わなかったから、ティーカップは2つしか用意して来なかったわ」
「あっ、じゃあ、わたしが取ってきます!」
愛する両親にいいところを見せようと、リンが元気に手を挙げる。
「ええ、じゃあお願いしようかしら」
「私も手伝おう」
「キレイはこないで!わたし一人でできるわ!」
途端にリンは不機嫌な表情を浮かべた。同じようにトキオミに師事し学んでいる者同士として、キレイはリンにとって兄弟子のようなもの。つまり、ライバルだ。ライバルに、みすみすいいところを見せる機会を譲る訳にはいかない!
たたっと駆け出し、大きな扉を開け放ってキッチンへ向かう可愛らしい少女を、三人の大人たちは微笑ましく見つめていた。若干一名、他の二人が浮かべる純粋な愛情とは異なる意味を込めた笑みを浮かべたものもいたが、それも彼なりの愛情なので、まあ仕方のないことだろう。
キッチンにリン専用の踏み台を持ち込んで、食器棚からティーカップを2つ取る。キレイのことは好きではないが、アオイの淹れる紅茶はピカイチなのだ。飲めないのはかわいそう。だからティーカップは2つなのだ。
急いで戻れば、大人三人はなにかの話で盛り上がっているようである。リンが扉を開けると、三対の色の違う瞳が一斉に彼女を写した。父と母が向い合ってテーブルについていて、キレイは父の背後に控えている。
テーブルの上には、既にクッキーやチョコレートが並んでいた。だが誰も手を付けていない。自分を待っていてくれたのだ、とリンは嬉しくなる。
「お母さま、持って来ました!」
「ありがとう、リン。すぐに紅茶を入れるわね」
持ってきたティーカップをテーブルの上に置くと、さりげなくキレイが回りこんできて椅子を引いてくれる。
「…ありがと」
「リンが私の分のカップも取ってきてくれたからね。その礼だ」
まるで、これで貸し借りはなしだとでも言うような口調にむっとしながらも、リンはその椅子に座る。キレイも、リンの向かいの椅子にかけた。その間にアオイが四人分のカップに紅茶を注ぐ。ローズティのようだ。
ふわりと優しい香りがあたりに漂った。
「そういえばお父さま、今なんのお話をしていたんですか?」
「ん?ああ」
カップを手に、その香りを楽しんでいたトキオミが、リンの問いに顔を上げる。
「そうだ、リンにも教えてあげないといけなかったな」
思いついたように、スーツの裾から腰に手を伸ばす。彼が取り出したのは、2つのモンスターボールだった。
「出ておいで」
トキオミがモンスターボールのボタンを押せば、赤い光とともに小さな二匹のポケモンが飛び出してきた。
「わぁ…!!」
リンが笑顔を輝かせて歓声をあげる。
現れたのは、二匹のエネコだった。まだ幼いのだろう、体はとても小さく表情はあどけない。狭いところからやっと出られた、と喜ぶように、二匹は声を揃えてにゃあと鳴いた。二匹とも首にはリボンを巻いている。片方は赤、片方は青だ。
「もしかして、お父さま、この子たちって…」
その二匹の正体に気がついて、リンはトキオミを見上げる。トキオミは笑顔で頷いた。
「この子たちは、私とアオイのエネコロロが何処かから持ってきたタマゴから孵った子たちでね」
今朝孵ったばかりなんだ。愛らしいだろう?とトキオミは自分の足にじゃれついてきた赤リボンの子を抱き上げる。
トキオミはほのおタイプの使い手であるのだが、その手持ちの中に一匹だけ、ほのおタイプを持たないポケモンがいる。それがエネコロロだった。大して強いとも言えないポケモンではあるが、トキオミは彼をとても大事にしている。それは、エネコロロがトキオミの家の家訓に関連するためだ。
『常に余裕を持って優雅たれ』。それが、彼の家訓である。
トキオミも、もちろん彼の妻になったアオイも娘であるリンも。全員の心の中心にある教えがそれだった。エネコロロは、その『優雅』を体現するポケモンだ。だからこそ、トキオミもアオイも、手持ちにエネコロロを加えていた。トキオミはオスの、アオイはメスの。彼らのトレーナーと同じように、彼ら自身もとても仲の良いパートナーだった。
その二匹がタマゴを持ってきたというのである。これはとても喜ばしいことだった。
「お父さま、触ってもいいですか?」
「ああ、いいとも」
トキオミが、抱いていた赤リボンの子をリンに差し出す。リンはその子を慎重に受け取った。
暖かく、小さい。それがその子に抱いた感想だった。リンは既にポケモントレーナーで何匹かのポケモンを持っているが、それらはすべて父から譲ってもらったポケモンや、ゲットした元野生のポケモンである。こんなに生まれたてのポケモンを見るのも、抱くのも、初めてだった。
「かわいい…」
「気に入ったかい」
「ええ、もちろんです、お父さま…!」
思わず言葉が漏れれば、トキオミが温かい笑顔を向けてきた。エネコは首を傾げ、自分を抱き上げてくれた相手を見定めるようにリンの顔に視線を定めていた。膝の上に座らせてその頭を撫でる。大きな耳を毛の流れに沿って撫でれば、嬉しそうにエネコは喉を鳴らした。なで方が上手ね、とアオイがリンを褒めた。事実、エネコは元から細い目を更に細め、気持ちよさそうな顔をしていたのだから。
ふいに、トキオミが口を開いた。
「その子か、この子」
その子、とリンの膝に居るエネコを指し、この子、と足元でおとなしく座っているもう一匹を指しながらトキオミが言う。
「二匹をそれぞれリンとキレイに譲ろうと思って、連れてきたんだ」
「わたしにエネコを譲ってくださるんですか!?」
あまりの驚きに大声を上げてしまい、撫でられてリラックスしていたエネコが飛び起きる。
「あ…ごめんなさい」
大声を出してしまうなんて優雅じゃないわ、とリンは心のなかで自分に言い聞かせた。
だが、彼女が一時でも家訓を忘れてしまったのも仕方のないことだ。
リンにとって、エネコというポケモンは特別な存在である。それは、父と母が持つエネコロロに関連していた。先述の通り、トキオミ一家にとって『優雅』という言葉は何よりも大事なものなのだ。その言葉とイコールで結ばれるポケモン・エネコロロ。その進化前の姿がエネコだ。エネコを与えられるということは即ち、未来のエネコロロを与えられるということと同意。自らも優雅であると認められた気がするのだ。
「…私にも、ですか」
しかし高揚したリンの気持ちは、そんな低い声に空気を抜かれてしまう。もちろん、問を発したのはキレイだ。キレイはトキオミと血がつながっているわけではない。家族ではないから、家訓を守る必要もない。そんな自分に、彼の家が大事にするポケモンを与える、というのが理解できなかった。
「師にとって、エネコ、エネコロロというのは大事なポケモンでは。そんな大事なポケモンを頂くわけには…」
「いいんだ、もらってくれ。アオイも、いいだろう?」
「ええ、もちろんですわ、コトミネさん。あなたはトキオミの弟子なんですから」
「別に、育てて君の手持ちに加えて欲しいというわけではないし、君に我が家の家訓を守ってほしいというわけではないよ」
弟子なのだから師の家のルールに従え、ということなのだろうか。だがそこまで深い意味はないようだった。まだ納得行かないような弟子に、トキオミは苦笑を浮かべ続ける。
「初めて私たちのエネコロロが持ってきたタマゴから生まれた子なんだ。だからこの喜びを、君にもと思ってね」
「はあ…」
難しい顔をしながらも、キレイは立ち上がりテーブルを回ってくる。そして、立ったまま青リボンのエネコを見下ろした。エネコは顔を上げてキレイに視線を向けるが、それは驚いていると言うよりも、誰が自分を見ているのか、という興味の現れのようにも見えた。巨大なキレイの体でできた影に覆われても、エネコは落ち着いた様子で彼を見上げていた。
筋肉質な黒い神父と愛らしい小さなポケモン。そんな二人の対比が面白くて思わず吹き出しそうになってしまったアオイを、誰が責められることだろう。
「二匹とも、ステータスも特性も技も差異はない。ただ、性別が違ってね」
会話が一段落した所で、トキオミからの説明が入った。
「今リンの抱いている赤いリボンの子がメス、にいる青いリボンの子がオスだ。どちらがいいかい?」
「わたし、女の子がいいです!」
膝の上に乗せていた赤いリボンのエネコをぎゅうと抱きしめ、リンが宣言する。何が何でも譲らないぞ、とでもいうようにキレイを睨みつけた。
「では私はこの子を」
特に性別にこだわりのないキレイである。リンの鋭い視線など受け流して、足元の青いリボンのエネコを抱き上げる。キレイの大きな手に両脇を持ち上げられても、エネコは声も上げずにキレイをじっとみていた。
なるほど、これが『余裕を持って優雅たれ』ということなのだろうか、とキレイは思った。何が起きても動じず、落ち着いて周囲を観察し、どんな相手も受け入れる。───ふと、そんなエネコの仕草と首に結ばれた青いリボンに、とある人物の姿が重なる。
「…師よ」
「なんだい、キレイ?」
「このエネコに、名をつけても?」
「ああ。別に構わない」
「それでは、トキオミと」
「…………………は?」
まるで技を忘れたポケモンのように、ぽかん、とした顔をしたのはトキオミだけではない。アオイもリンも、時が止まったかのような顔でキレイを見た。変わらないのは人語を理解しないポケモン達と、言葉を発した本人であるキレイだけだ。
「トキオミ」
「えにゃー」
「トキオミ」
「えにゃー」
キレイがエネコの名を2回呼びエネコが2回返事をしたころ、やっと金縛りが解けたのはリンだった。
「ちょ、ちょっとキレイ!何やってるのよ!!」
「何とは?私は師から頂いたポケモンに名をつけ、その名を呼んでいるだけだが」
「そんなこと聞いてるんじゃないわよ!なんでそんな名前をつけるのよ!!」
「そんな名前などとは…。リン、同じ名を持つ師に悪いとは思わないのかな?」
「違…っ!お、お父さま!お父さまからも何か言ってください!!」
ツインテールを振って振り返ると、父の金縛りはまだ解けていなかったようだった。リンの鋭い視線を受けて、やっとトキオミの視線はキレイとキレイに抱かれたエネコを行き来する。
「あ、ええと。キレイ」
「はい、トキオミ師」
「なぜそのエネコに…その名を?」
「このエネコからあなたの家訓を感じ取りました。それと、このリボンがあなたに似ていると感じましたので」
「リボン」
オウム返しに呟いて時臣は自分の胸元を見下ろす。たしかにそこには、青いリボンタイが揺れているのだ。キレイに抱かれるエネコと同じ色の。
「ああ、確かに」
「お父さま!!」
思わず納得してしまえば、リンが怒った声を上げた。
「そんなの絶対に駄目です!」
「そんなのとは何かね?」
「あんたが、お父さまを呼び捨てにすることよ!」
「導師には師という敬称をつけて呼んでいるだろう。私がトキオミと呼ぶのはこのエネコだ」
「だけど、同じ名前だったらお父さまのことだと思う人だっているかもしれないじゃない!あんた人前でそのエネコを呼ぶつもりでしょ!?」
「バトルなどになれば指示を出す必要があるからな。トキオミ、なきごえをあげろ、と」
「絶対ダメ!!!!」
バン、とテーブルを叩いてリンが立ち上がる。トキオミ自身は余り理解ができていないのか、それとも理解したくないのか、どこかぼんやりした表情で首を傾げていた。
「…と言われてもな。もう名前をつけてしまった。リンも知っているだろう?一度つけた名前を変えるためには、マトーシティの姓名判断士のところに行く必要がある」
「し、知ってるわよ」
「今からマトーシティに行けば3日は帰って来られない。明日も明後日もジム戦を予約している挑戦者がいるだろう?ジムリーダーに挑む資格があるかを見極める役を仰せつかっている者としては、そんなに長く留守をするわけにはいかないな」
「う………、じゃあ、ジム戦がない日に行きなさいよ」
「さて、それはどれだけ先のことになるかな?」
にやにやと楽しそうに言うキレイにからかわれているのだとわかる。だけれど舌戦でリンが勝てるとは思えなかった。
「…コトミネさん」
そんな二人の均衡(というかキレイの圧勝)を破ったのは、これまでずっと黙っていたアオイだった。
「………何でしょうか、奥方様」
静かな声、静かな笑顔。しかしリンとは全く異なる圧倒的な敵意に、キレイは冷静を装いながら言葉を返した。
「私のチルタリスを貸してあげるわ。すぐにマトーシティに行ってきなさい」
「しかし」
「すぐに行ってきなさい」
常と変わらない優しい笑顔。しかし周囲に纏うオーラが全く違う。静かな怒りを押さえることもせず、口調は否定の返事を許さぬかのように固く。
トキオミやリンすらも初めて見る彼女の姿に驚く中、その怒りを真っ直ぐにその一身に受けたキレイは、頷くことしかできないのであった。
数時間後、チルタリスの『そらをとぶ』でマトーシティとの一往復を果たしてきたキレイの手には「トッキー」と再度名付けられたエネコが居り、アオイ・リン母子との第二ラウンドが繰り広げられたとか。
そしてその裏で、キレイに充てられたトキオミが、手持ちのヘルガーに「キレイ」と名付けるかを真剣に悩んでいたとか。
私の最愛ポケ・エネコロロさんは
中国語で「優雅猫」というのでして
そんなもん時臣師に持たせるしかねえ!
と思い立ってしまった悪ふざけの産物です。
エネコロロちゃん弱いけどな!!
中国語で「優雅猫」というのでして
そんなもん時臣師に持たせるしかねえ!
と思い立ってしまった悪ふざけの産物です。
エネコロロちゃん弱いけどな!!