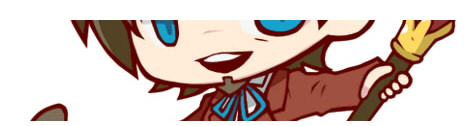
裏/ゴリバレ前~ゴリバレ~試練/付き合っていない二人
裏ゴリバレ前にナイトプライドを放ったり、
シルビアが剣を使うことを躊躇したり、
正体がバレたり、試練に失敗したりする話
裏ゴリバレ前にナイトプライドを放ったり、
シルビアが剣を使うことを躊躇したり、
正体がバレたり、試練に失敗したりする話
乙女よ、汝が騎士道に胸を張れ
■プロローグ
第一印象は「厄介な子」だった。
デルカダール王からの預かり物。バンデルフォン王国の遺児。剣や武道を学んだことのない、図体ばかり大きい子供。どこを取っても厄介と表現するほかないだろう。
ボクの父――彼の師匠になる人――に連れられて相弟子となる仲間たちの前に初めて現れたときも、自己紹介は噛むし、表情はどこかへらへらして緊張感がないし、視線はきょろきょろと落ち着かない。なのにその眼の奥には消すことの出来ない昏い炎が宿っているようで、近づく他人を焼き殺してしまいそうに、ボクには見えた。
更には、修行をしに来たなんて言う癖に、剣を握る姿のなんと様にならないこと。他の年下の子だってもう少し優雅に剣を構えることが出来るのに、全身に無闇やたらと力を込めて、威嚇するように相手を睨みつける姿といったら、まるで体の大きさだけが成長してしまった仔いぬのようだった。
そのうえ型にはまらない「自由形」の剣――もちろん皮肉だ――はその視線の強さと腕の太さ通りに力強く、暴風みたいな闘い方に吹き飛ばされて尻もちを付かされながらボクは父を恨んだものだ。如何にデルカダール王からの直接の頼みだとしても、なぜこんなけものの仔のような弟子を取らねばならなかったのかと。
だが、そんなけものらしさを見せつけながらも、本当の彼は酷く脆かった。
最初のころ、稽古を終えた彼は誰ともつるまずにさっさと部屋に帰ってしまっていた。他の子たちと異なる時期に入ってきた彼には寄宿舎の部屋が用意できず、屋敷の客室に一人で滞在している。だから稽古が終わったあとにさっさと戻ってしまえば、誰も話をする機会などなく、当然彼に友などできないようだった。ボクと同じようにあの暴風みたいな剣に一度でも吹き飛ばされたことのある者などは、陰口を叩いたものだ。礼儀も知らぬ家なし子め、力で僕たちを打ちのめして勝った気になっているんだ、いやらしい、など。そんな事を当人に隠れてこそこそ言っている者こそいやらしいとボクは思ったけれど、それを口に出すことはなかった。何故かと言えば、陰口を叩かれているあの子に対し、そこまでしてやる義理など持っていなかったからだ。
だが、彼がそんな立場に置かれていることを知った父はボクに命じた。あの子に、出来るだけ付き添ってやれと。
気が重くなかったと言えば嘘になろう。その頃のボクは、剣の腕を磨き父のようになることしか考えていなかった。そうでなければどうしても、それだけではいけないのではないかと思ってしまうのだ。ボクはソルティコ領主・剣神ジエーゴの息子。それ以外の何者でもない。それ以外の道などないはずなのに。
『――入るよ、グレイグ』
なおざりにノックをし、返事も待たずにボクはその扉を開けた。
ぐるりと見渡しても、部屋の主の姿がないことに困惑する。テーブルにも、書物机にも、ベッドにも、あのでっかい図体はない。
彼が部屋に戻ったのは確かなはずだ。屋敷に入るのは見たし、廊下を彼にあてがわれた部屋の方へ移動するのも窓から見た。どこへ行ってしまったのだろう、と首を傾げたときのことだ、小さな声が聞こえたのは。
『……ゴリアテ?』
声の元は、ベッドと壁との狭い隙間にいた。床に座っているらしく、低い位置からおずおずと覗いた顔。真っ赤になった目元と、明らかに今拭ったばかりのように濡れた頬。
厄介な子に関わってしまった、とボクは思った。
――そんな子が、数十年の時を経てまたアタシの前に現れた。
「イレブンが世界を救う勇者なら、……俺は、勇者を守る盾となろう」
そう言って微かに笑む男は、見たことがあるような見たことがないような顔をしている。大きな体には何もかもを阻むような黒い鎧をまとい、顎には威厳を表すような髭。グロッタには彼の大きな像が飾られているけれど、あれよりはまだ記憶の中にある少年の姿のほうがイメージは近い気がした。
旅立つ前に客室を借りて、まずは仲間を紹介するよ、とイレブンちゃんが言った。カミュちゃん、ベロニカちゃん、セーニャちゃん、そしてアタシの番。
「旅芸人のシルビアよ。よろしくねん、グレイグちゃん!」
とびきりの笑顔とともにウィンクを飛ばしてみたら、彼の眉間にはとびきり深いシワが寄った。
本当に真面目なんだから。そんな反応をけらけらと笑い飛ばしながら、アタシはそのシワの深さこそが彼とアタシとの溝の深さなのだと今更のように思い知る。
彼はデルカダールの将軍、アタシは旅芸人。
彼もアタシも大人になった。
もう二度と、昔の二人には戻れないのだと。
■1.勇者の仲間たち
デルカダールの将軍・グレイグが仲間になって、数週間が経つ。勇者を悪魔の子と呼び執拗に追いかけその命を奪わんとしていた彼が、今やその勇者の背を守る盾だ。世の中、何が起きるかわからないものである。
前からあまり『グレイグ将軍』にいい印象を抱いていなかったカミュちゃんやベロニカちゃん――当たり前だ、あんなに追いかけ回されたんだから――のことは少し心配していたけど、意外とすんなりと仲間として受け止められているみたいだった。彼とカミュちゃんがクレイモランの地酒の話で盛り上がっているのを見かけたのはつい先日だし、さっきもベロニカちゃんとセーニャちゃんに纏わり付かれていたし。仲間たちに絡まれては不器用そうに笑う彼を見て、アタシはホッとしていた。
なにせ、彼は新しい交友関係を作るのが余り得意ではなかったはずだから。
それをアタシは知っている。まだ誰にも言っていないけれど、彼とは昔なじみなんだから。
デルカダールには親友が一人いると言っていたけど、ソルティコではさっぱり人付き合いができていなかった男の子のことを、アタシは知っているのだ。でも、あれから長い長い時間が経っている。様々な経験をして、必要なスキルを身に着けて、彼は大人になったんだ。見た目だけじゃなくて、中身の方も。偉そうな考え方かもしれないけれど、彼の成長がアタシにはとても嬉しい。
だけど未だ彼は、アタシの正体に気付いていなかった。
当たり前だろうと思う。アタシの外見は昔とだいぶ違うし、今さら自分から名乗るつもりもない。彼が、アタシが何者なのか知ったら面白いことになるんじゃないかなという期待もあるけれど、同じパーティーの仲間として平和にやれているんだからわざわざ気付かせることもないだろう。正直、機会を逃してしまったというところもある。
だから、今の彼とアタシはただの『勇者の仲間同士』だ。
「シルビア」
「あら、イレブンちゃん」
呼びかけられ、物思いに沈みかけていた気持ちを引き戻す。こちらを見上げてにこにこしていたのは、その勇者イレブンちゃんだ。今日ももちもちしたほっぺたを血色良く染めて、綺麗な髪の毛がさらさら揺れているのがとても素敵だ。
ここはユグノア城跡の近くにあるキャンプ。川も近いし景色もいいし、それからイレブンちゃんのご両親――であり、ロウちゃんの家族ちゃんたち――のお墓参りもできるから、結構よく訪れる場所だ。
まだ太陽は高い時間。夕飯の用意にも早いから、みんな好き勝手に過ごしていた。イレブンちゃんはさっきまでロウちゃんとカミュちゃんと一緒に、実益と娯楽を兼ねた川釣りに出かけていたはずだ。
「今日の釣果はどう?」
「まあまあかな。カミュとおじいちゃんだけでもみんなの分を釣れそうだし、思い出したことがあったからボクだけ戻ってきたんだ」
思い出したことってなに?とアタシが聞く前に、イレブンちゃんが首を傾げた。
「シルビアは、グレイグを見ていたの?」
視線の先を読まれ、思わずくすりと笑みが漏れる。
「さっきね、面白かったのよ。風に飛ばされたハンカチが木に引っかかっちゃって、ベロニカちゃんがグレイグちゃんに肩車をお願いしたの。それをセーニャちゃんが羨ましがっちゃってね」
「えー、ボクも羨ましい。グレイグ、大きいもの。眺めが良いんだろうなあ」
「ウフフ、お願いしてみたら?」
「今度お願いしてみようかな。それで? セーニャも肩車してもらったの?」
「ううん。グレイグちゃんはあたふたしながら、ロングスカートだと足が広がらないから難しいだろうって言って、セーニャちゃんはそれならおどりこの服に着替えてきますって答えて、グレイグちゃんったら更にあたふたしちゃって」
「ベロニカはスカートじゃなかったっけ?」
「さっきはねこの着ぐるみを着ていたわ。だからグレイグちゃんも肩車出来たんだろうし、肩車している姿がなおさら面白かったのよ」
アレルギーのでないおっきな猫ちゃんを肩の上に乗せ、猫ちゃんの指示通りにふらふら歩く、立派な体格の将軍サマ。今でもまだ思い出し笑いをしてしまいそうだ。
最初の頃はベロニカちゃんを見た目通りだと思っていたグレイグは、未だに彼女の扱い方に困っているみたいだ。ベロニカちゃん自身はその見た目の年齢が役立つときと、実際の年齢の方が役立つときとで器用に振る舞い方を変えているけれど、不器用なグレイグはそれでなおさら迷ってしまうようだった。年頃の女の子らしいお洋服を欲しがるベロニカちゃんも、背が高いからってグレイグに肩車をねだるベロニカちゃんも、同じベロニカちゃんなのに。
「セーニャに、ベロニカとお揃いの着ぐるみを作ってあげたほうがいいかな?」
イレブンちゃんのいたずらっ子みたいな表情。黒い鎧の大男がねこの着ぐるみ姿のセーニャちゃんを肩車する光景を想像して、アタシは笑ってしまった。
「断る理由がなくなって、グレイグちゃんは困っちゃうだろうな」
「セーニャも、そういうとこ鈍いからね」
視線を向けても、もう彼女たちはいない。グレイグは自主鍛錬に戻り、敵に見立てて立てた杭に向かって剣を振っている。大剣を振り下ろしきる直前でぴたりと止める姿が美しく見えた。腕の筋肉が、服の上からでもわかるくらいに盛り上がっている。
「――シルビア、あのさ」
イレブンちゃんがまた話しかけてくる。というより、世間話は本題に入る前置きみたいなものだったんだろう。釣りを切り上げてまで戻ってくるくらい重要な『思い出したこと』とやらは、まだやっていないみたいだし。
「なあに?」
こちらを見上げるイレブンちゃんは、そこで言いよどむような素振りを見せた。いつも真っ直ぐな彼にしては珍しい。アタシは少し首を傾げて、イレブンちゃんが続きを言いたくなるのを待つ。
「えっと……、あ、そうだ。この間受けたクエストが、まだ残ってたことを思い出したんだ。悪いけど、付き合ってくれないかな」
「ええ、もちろんよ」
それが本当に言いたかったことかしら? だけどごまかしたいのなら、アタシはそれに乗ってあげよう。イレブンちゃんなら、きっと後で話してくれるはず。
「詳しいこと、聞く前に頷いてくれるんだね」
「他ならぬイレブンちゃんの頼みだもの! アタシにできることなら、何だってしてあげちゃうわよん」
力こぶを作るようなポーズをして強く頷いてみせると、イレブンちゃんは嬉しそうに笑ってくれた。
「ありがとう! じゃあ、グレイグにも声をかけてくるね」
「え? グレイグちゃん?」
とつぜん出てきた名前に首を傾げる。彼をパーティーに入れるとなると、今日は物理攻撃寄りの戦い方がメインになるかしら。もう一人のメンバーはセーニャちゃんかロウちゃんにしてもらえると、バランスがいいのだけれど。そこまで考えたアタシに向かって、イレブンちゃんは首を振る。
「ううん、他のみんなにはキャンプで休んでてもらうよ。今日のクエストは三人で行くのが一番いいと思うんだ」
「三人……、イレブンちゃんと、グレイグちゃんと、アタシの三人ってこと?」
「うん。連携技で魔物を倒す依頼だからね」
そう言って、きょとんとするアタシを置いてイレブンちゃんはすたすたとグレイグの元へ向かってしまった。四人でパーティーを組んでも、三人連携は使えるはずなんだけど、どういう意図があるんだろう。イレブンちゃんに話しかけられ、グレイグが振っていた剣を下ろす。額を流れる汗が、離れていても見えた。
(そもそも、アタシたち三人の連携技なんてあったかしら……?)
イレブンちゃんとアタシ、イレブンちゃんとグレイグの連携なら思い当たるものがいくつかある。メラハリケーンとか竜王斬りとか、武器も魔法も選び放題だ。
近くの樽に寄りかかってぼんやり眺めていると、イレブンちゃんが何か言って、グレイグが何か返しているのが見えた。ふとグレイグが視線を上げて、目が合う。たぶん、今日はイレブンちゃんとアタシとの三人パーティーだって聞いたところなんだろう。笑って手をひらひらふってみたら、目を細める仕草が返ってきた。一体どういう意味の仕草なのかはわからないけれど、それで視線は外される。
(ちょっと、やり辛いわねぇ……)
嫌われてはいないと思うのだけど、何だか彼はアタシが苦手みたいだ。その鎧みたいにカチカチの堅物な彼だから、旅芸人なんて埒外の生き方をしている相手にどう接すればいいのかわからないのかもしれない。
だからアタシは彼が慣れてくれるまで、彼が嫌がらないような距離を保っていればいい。そうやって時間をかけてゆっくり仲良くなることはこれまでにもあったし、得意だと思っている。だけど今だけは、どうにもうまくいかなそうな気がしていた。
2.怪鳥の幽谷のクエスト
「目的地、ここだったのね……」
「ごめんね、早めに終わらせるように頑張るから」
アタシたちが立っているのはメダチャット地方の北側、『怪鳥の幽谷』と呼ばれる場所だった。
鋭利な刃物で削いだみたいに切り立った崖、その上から激しく落ちる滝、そしてその流れを組む太い川。見惚れてしまうほど雄大な景色だけど、毒々しい色のカエルや亡霊じみた魔物たち、それにこの地の呼び名にもなっている怪鳥たちがあちこちを闊歩しているから、観光に訪れる人はそうそういないだろう。
「この場所が嫌いなのか、シルビア」
アタシのげんなりした様子に気付いたのか、デルカダールの鎧を着込んだグレイグが声をかけてくる。アタシは肩をすくめて答えた。
「ここ、鳥の魔物が多いでしょ。アタシ、鳥ってあんまり好きじゃないの」
「意外だな。貴様は鳥の羽のついた服を持っていただろう」
「パレードの服のこと? あれはイレブンちゃんがくれたのよ。確かに一番のお気に入りだけど」
それは、イレブンちゃんがカジノで手に入れてきてくれたらしい、帽子と腰にたくさんの羽を飾った衣装だ。色が派手で目立つし、動くたびにふわふわ揺れてとても楽しい気分になる。アタシの好みそのもので、お気に入りの一着だ。今日は着ていないけれど。ジェネラルマントを身に纏ったグレイグの隣に並んでも見劣りしないよう、動きやすくて鮮やかな色のハンサムスーツを着てきたのだ。
「ああいう綺麗な羽とか、手のひらに乗っちゃうくらいの小鳥ちゃんなら大丈夫なんだけどね……」
目を狙われたことがあるのだ、と語ろうとしてふと口をつぐむ。その事件は自分が幼い頃に起きた。グレイグがソルティコにいた時に、話のネタにしたことがあったかもしれない。いま語って、その相似に気付かれてしまうのではないだろうか。
話そうかどうしようかと迷っているほんの少しの間に、しかしどうやら彼は話題への興味をなくしてしまったみたいだった。前を行く彼の黒い背を眺めながら、悩む必要のなくなったアタシは小さく息を吐く。
怪鳥の幽谷は、足を踏み入れてすぐのところにキャンプ地がある。ここで一旦休憩して、目的地にはその後で向かおうとイレブンちゃんが言った。
「まだ、クエストの詳しい話をしていなかったよね」
お昼ご飯にとマルティナちゃんが持たせてくれたサンドイッチ――ロウちゃん直伝のユグノアサンドイッチというメニューらしい――を頬張りながら、イレブンちゃんは口を開く。
「ここには『あくまのきし』って魔物が出るんだけど、その魔物は元々名のある騎士だったらしいんだ。彼らは魔物になったことで、人を襲ったり色々悪事を働くようになってしまったんだって。だから彼らに騎士の誇りを思い出させるように、ボクたちの連携技で倒してやってほしいっていう依頼だよ」
「名のある騎士が魔物に……、か」
黒く高い襟に埋もれるように、グレイグがうつむいた。彼の考えていることはなんとなくわかる。きっと、彼の親友だった人のことだ。それからもしかしたら、かつての勇者の仲間だったという魔法使いのことも。イレブンちゃんと目が合う。小さく首を降るイレブンちゃんにアタシは頷き返した。今は、彼に言葉をかけるべきではないだろう。
果たして、すぐにグレイグは顔を上げた。何事もないように分厚いサンドイッチを大きな口でかじってみせたのは、どうということもないとアタシたちへ示す意図だろう。
「――それで、連携技とはなんだ? 俺たち三人で使える技などあっただろうか」
「そうそう、アタシもそれが気になってたの。グレイグちゃんが仲間になってから、まだそんなに時間も経ってないし……」
何かできることはあっただろうか。グレイグからは「貴様も剣を使うのなら、そのうち連携技を考えてみるか」
と言われたことはあるけれど、未だ実現してはいない。
その理由は、「剣を使うなら」という条件を課したにも関わらず、最近グレイグもアタシも二人とも剣を使っていないからだろう。彼はイレブンちゃんが作ってくれた斧を、アタシはイレブンちゃんがカジノで手に入れてきた鞭を、今も使っている。そう考えると、アタシの衣装も武器もイレブンちゃんがカジノで手に入れてきたものということで、……少し、イレブンちゃんの教育方針をロウちゃんと考え直なければいけないかも知れない。カジノが楽しいのはわかるんだけど、ハマりすぎちゃうのは困りものだ。
とりあえず連携技のことを考えるなら、グレイグの大盾を使った技も面白そうだ。アタシの火吹き芸なんかと組み合わせれば、派手なことができるかもしれない……とまで考えて、思考が旅芸人としてのそれに傾いていることに気が付いた。いけない、もっと勇者の仲間っぽい技を考えなくっちゃ。
「実は、考えていることがあるんだ。後で話すよ」
イレブンちゃんはそう言って微笑んだ。今ちょうど落ち着いているところなんだから話してくれたって良いのに、もったいぶることだ。でもまあ、彼に任せておけば問題はないのだろう。グレイグとカミュちゃんなんて取り合わせの連携も、キレイに決めてくれるイレブンちゃんなら。
「そういえば、『はやぶさ三連』って技、格好いいわよねー! アタシははやぶさ斬りを使えないから、羨ましいわ」
「そうなのか。器用そうなのに、意外だな」
「ドラゴン斬りとかメタル斬りなら使えるんだけどねん」
「ドラゴン斬りはイレブンとの連携で使うが、メタル斬りは連携に組み込んだことがないな。何か考えてみようか」
「うーん、そうね。グレイグちゃんが合わせられそうな技があるなら」
ふと見ると、イレブンちゃんがこっちを向いて穏やかに笑っていた。
最近の彼は、たまにこういう表情をしていることがある。まるで、仲間たちが楽しげにしているのが嬉しくてしかたないような。
そんな表情はベロニカちゃんとセーニャちゃんに向けていることが多いけれど、たまにアタシにも向けられていることがある。不快ではないし、イレブンちゃんが安心したように笑っていてくれることは嬉しいのだけど、そんなときはなんだかあの子の方が年上のように見えて不思議な気分になる。
「それじゃ、そろそろ行こうか」
イレブンちゃんが指をぺろりと舐めながら、アタシたちを見渡す。不格好だけど具がたくさん入っていて分厚いサンドイッチは、十分彼を満足させたようだ。
そうね、そうだな、とそれぞれ頷いたアタシたちは、手早く片付けを始める。片付けと言っても、サンドイッチを包んでいた風呂敷を畳み、水筒などを荷物にしまい、マントや裾に付いた砂を払うくらいだけれど。最後に荷物を元通りに――ここへ戦いに来ただけなのに、イレブンちゃんの荷物はずいぶん大きい――背負えばおしまい。火も付けなかった焚き火あとを振り返れば、落ちていたらしいパンのかけらを咥えて小さなネズミちゃんが逃げていくのが見えた。
「行こう」
イレブンちゃんの言葉にもう一度頷き、アタシたちは歩き出した。
「連携技の件なんだけど」
とイレブンちゃんが口を開いたのは、さっきの休憩から十五分くらい経った頃のことだった。モンスターたちが切り開いたのだろう獣道を、グレイグ、イレブンちゃん、アタシの順に列になって進んでいる。小川を渡り、洞窟を抜ければそのあたりが『あくまのきし』たちの生息域だ。後でというのがこのタイミングなら、さっき話してくれても良かったのにと心のなかで思う。
「ボクが合図をしたらシルビアはバイキルトとピオリムを、グレイグはスクルトを、ゾーンの力と共にボクに送ってくれないかな」
「お前に?」
「全員の力を一人に集めて、集められた一人が全力で敵を蹴散らすっていうのがやってみたいんだ」
振り返ったイレブンちゃんの目はキラキラ輝いていた。なるほど、バイキルトにスクルト。三人パーティーっていうのはほんの少し心細いけれど、アタシたちは意外とバランスがとれた組み合わせみたいだ。
「いくらゾーン状態だとしてもアタシ、二つも同時に呪文を唱えられるかしら」
「ピオリムは全員にかける魔法でしょう。一人分だけなら少しは早く唱えられないかな?」
アタシはゾーン状態でも素早さは上がらないけど、ゾーンの力に乗せれば詠唱がなくても発動できるかもしれない。そういえばアクロバットスターとかもそうだ。あれもゾーンの力にピオリムを乗せて、イレブンちゃんとカミュちゃんの組み手でその威力を増大させているのだし。
「そうね、できるかも。やってみるわ」
「うん。お願いね、シルビア」
「それにしても、アタシだけ二つなのね。グレイグちゃんからもらうのはスクルトだけでいいの?」
「マジックバリアはちょっとイメージが違うんだよね……。せっかく騎士から力をもらうんだし、魔法じゃなくて物理の防御とか攻撃とかを目一杯高めたいんだ」
「だったら、ソードガードが上手にできるようにって祈りを込めてもらうのはどうかしら?」
「あっ、それいいね! グレイグ、どうかな」
「う? うむ、わかった」
うろたえたように答えたグレイグは、短く唸って腕を組んだ。祈りを込めてって言われても、どうすればいいのかわからないのだろう。一番うしろを歩くアタシにはその表情は見えないけれど、少し横へ傾けた頭と不規則に揺れる黒いマントが彼の心中を表しているようでなんだかかわいらしい。アタシは、声を立てないように笑った。
魔物の巣の真っ只中だというのに、しかも空にはくちばしも鋭い鳥ちゃんたちが飛んでいるというのに、なんだか楽しくて仕方がない。多分、イレブンちゃんがのんきだからだ。確かにこの辺りの魔物たちはあまり強くはないけれど、ピクニックみたいにご飯を食べて、雑談みたいに新技なんか考えながらのんびり歩いて、傍らを流れる川の音も木々の緑も空の青も爽やかだし、緊張感を抱けっていう方が難しいだろう。
そんな爽やかな空気の中、ううん、と低い唸り声が響いた。グレイグだ。
「イレブンよ、やはりどうすればよいか検討もつかん。どこかで一回試したほうが良いのではないだろうか」
「うーん、多分大丈夫じゃないかなあ」
「むう……、だが初めてだからな……。シルビアも不安だろう?」
「え? ええ、そうね、初めてのコトは、ちょっと不安かもねん」
突然呼ばれ、はっとして顔を上げる。首だけで振り向いたグレイグと目があったので、アタシは笑顔を浮かべてみせた。グレイグは一瞬だけ不思議そうな顔を浮かべて――とっさだったからちょっと引きつっていたのかもしれない――、それからアタシの答えに頷いた。
「だ、そうだ。イレブン」
「うーん……、でも、多分大丈夫だと思うよ」
「どうして?」
「なんとなく、かな」
そしてイレブンちゃんは、前を歩くグレイグと後ろを歩くアタシに交互に視線を向けた。
「ボクは、ボクの仲間を信じてるから」
その笑顔の、なんて純粋なこと。振り向いたグレイグの頬が赤くなっている。そして多分、アタシも。「んもう、イレブンちゃんったら人たらしなんだからー!」
、なんておどければよかったと思ったのは数秒後で、そのときにはもうイレブンちゃんもグレイグも前に向き直ってしまっていた。
行き場のなくなった息を、そっと吐き出す。葉っぱ一枚も揺らせない微かな息は、きっとイレブンちゃんにも届かなかっただろう。
(イレブンちゃんは……)
最近、何だか大人になったな、とやっぱり思う。前はもっと無邪気でパーティーの末っ子みたいな雰囲気だったけれど、今は落ち着きがあるというか、妙に達観してるというか。
いつ頃からだっただろうと思い返すと、神の民の浮島を初めて訪れたにはすでにその兆候があったように思う。あんな不思議でワクワクする場所にたどり着いたというのに、イレブンちゃんの反応はちょっと薄かった。そういえば、ケトスちゃんが現れたときも。
(もしかして、未来を知っていたのかしら? ラムダの長老ちゃんみたいに、夢でみたとか……なんてね)
ただでさえ勇者のチカラを背負っているイレブンちゃんに、夢見のチカラまで負わせるわけにはいかない。そんな重荷ばっかりじゃ潰れてしまうだろう。
そういえばイレブンちゃんは、大樹の根に触れることで、過去を見ることができるらしい。一度は、彼のおじいちゃん――ロウちゃんではなくて育てのおじいちゃんだ――とお話をしたこともあるんだそうだ。その勇者のチカラで過去の勇者・ローシュちゃんたちの足跡を見たとか、そんなところだろうか。そういう経験をしているのなら、事実イレブンちゃんはアタシたちよりも多くの時間を過ごしているのかも知れない……なんて。
「わっ」
「あらっ、ごめんなさい」
物思いに沈みかけていたら、突然立ち止まったイレブンちゃんの背中にぶつかりそうになってしまった。先頭を行くグレイグが足を止めたからだ。彼は左手を水平に横に伸ばし、静かにアタシたちへ立ち止まるよう指示を出していた。
木々の隙間から伺えば、少し先をうろついている大きな影がある。意思のないような虚ろな歩行。そのたびにガシャリガシャリと重たく響く甲冑の音。『あくまのきし』だ。
あれが、騎士の誇りを失って悪事を働いているという魔物か。一体どこの国の騎士だったのだろう。どんな功績を積んできたのだろう。――どんな誇りを持っていたのだろう。面貌で隠した表情は全く伺えず、武器すら持たない姿は想像の余地すら与えてくれない。
グレイグが振り返り、イレブンちゃんが頷いた。下ろした荷物を足元の茂みに軽く隠して、アタシたちはそっと隊列を入れ替える。先頭にイレブンちゃん、その次にグレイグ、最後にアタシ。イレブンちゃんが二刀流の剣の柄に手をかけ、ぐっ、と足に力を込めた。グレイグは斧に、アタシは鞭に手をかける。
一瞬少しだけ体を沈め、イレブンちゃんが飛び出した。
『あくまのきし』が振り返る前に、二本の剣で大きく斬りかかる。イレブンちゃんの鋭い掛け声に、剣と魔物の鎧がぶつかり合う嫌な金属音が重なる。それを聞きながら、アタシたちも飛び出した。
魔物は三体。イレブンちゃんの斬りかかった『あくまのきし』ちゃんと、近くにいて参戦してきたパールモービルちゃん二体だ。予定外の二体を含めてどれもそう強い魔物ではないけれど、鉄みたいに硬い体をもった魔物ばかりだから、魔法つかいのいないパーティーで戦うにはちょっぴり不利だ。
(でもっ!)
『あくまのきし』ちゃんと相対するイレブンちゃんの後ろから襲いかかろうとするパールモービルちゃんへ、グレイグが突進する。アタシはその速度に合わせて、素早く魔法を唱えた。
「――バイキルトッ!」
「せェッ!」
腕力増強の魔法を受けた体を輝かせながら、グレイグはオノむそうを放った。力強い一撃を受けたパールモービルちゃんたちは耳障りな金属音を立てながら一歩退く。
魔物たちの分断は成功だ。これで一対一、二体二の構図を作ることができた。しかもアタシは前線から少し離れて、イレブンちゃんの方になにかあっても駆けつけられる位置。計算通りだ。
とはいえ、これは普通の戦闘ではない。ただ魔物たちを倒しておしまいというわけにはいかないのだ。ここに来た目的――クエストを果たさなければ。
(まずはゾーンの力が体に満ちるのを待って、それからイレブンちゃんが合図をしたら)
アタシは、バイキルトとピオリムをゾーンのチカラと共にイレブンちゃんへ送る。具体的にどうすれば良いのかはわからないし、グレイグの言うとおりに不安しかないけれど、イレブンちゃんが信頼してくれるならなんだってできる気がしてくるから不思議だ。
一度は退けられたパールモービルちゃんが、果敢にもまた向かってくる。グレイグは黒いマントを翻しながらその突撃をかわし、行き過ぎた魔物の背中へ斧の刃を叩きつけようとした。だが更にそのグレイグの頭上には、高く飛び上がったもう一体の丸い魔物ちゃんが。
「――スキだと思った?」
だけど、アタシがいる。素早く鞭を伸ばし、急降下してくる魔物の足に絡みつけて引きずり落とした。がくんとバランスを崩して地面に叩きつけられた魔物の体から、ガシャンと金属のパーツのようなものが弾け飛ぶ。同時に、離れたところでも鈍く激しい音が響いた。ちらりと視線をやれば、斧を大きく振り切ったグレイグの姿。そしてさらに離れた木の根元で、頭を大きく凹ませた魔物が黒い煙に包まれて消えるのが見えた。
「一撃だなんて、やるじゃなーい!」
「貴様のフォローのお陰だ、シルビア」
止めをさしたのは会心の一撃だったのか、珍しくグレイグは上機嫌なようだった。アタシの方を振り向いて、得意げな子供みたいにニヤリと笑ってみせてくれた。思わずアタシも嬉しくなって笑い返す。
「その調子で、もう一体もお願い!」
「ああ、任せろ」
頷くグレイグと位置を交代して、アタシはイレブンちゃんの方を伺った。
三人がゾーンに入るまで、『あくまのきし』ちゃんを倒し切るわけにはいかない。イレブンちゃんは二本の剣をつかって、魔物の重たいパンチやタックルをうまく受け止めたり受け流したりしていた。怪我はしていないみたいだけれど、ピオリムくらいかけておいたほうがいいかしら。手にした鞭を腰に戻して呪文を紡ごうとした瞬間、イレブンちゃんが大きく飛び退って魔物との距離を開けこちらを向いた。
「シルビア、グレイグ! これを使って!」
そして何かを放る。放物線を描いて飛んできた小さな二つをグレイグの分も受け取ると、それは青いサクランボのような木の実だった。受け止めた衝撃で握りつぶしそうになった指の力を慌てて緩める。
「あら、これって『きせきのきのみ』じゃない!」
食べると体にゾーンの力がみなぎるという珍しい木の実だ。海のように青い実は、十分に熟しているようで鮮やかだ。
「ありがと、イイモノ持ってたのね!」
「カジノで……あっ、あー、危なっ!」
イレブンちゃんは何か言いかけて、だけど途中でわざとらしく魔物の攻撃を避けるふりをして言葉を切った。まったく、大事なところは聞こえているというのに。やっぱり、ロウちゃんへの相談が必要そうだ。
でも、今はそんなことを追求する時じゃないだろう。
「グレイグちゃん、イレブンちゃんからの差し入れよん」
「む」
アタシは、パールモービルちゃんと睨み合っているグレイグに近付いて、口元に『きせきのきのみ』を差し出した。仲間がやられて気が立っているらしい魔物ちゃんは今にも突撃してきそうで、視線を逸らすわけには行かないだろう。少し開いた唇に、鮮やかな青い木の実をぎゅっと――唇に少しだけ触ってしまったけれど許してほしい――押し込む。同時に、アタシ自身の口へも。
噛んだ瞬間瑞々しい果汁が口内で弾けて、激しい力が体内を勢い良く駆け巡った。喉から脳へと、燃えるような熱さが神経や血管を駆けのぼり全身を満たす。肉体なんて小さな器では閉じ込めきれない力が溢れ出して、青い閃光のように全身を取り巻くのが目にも見えた。同じ現象が、かたわらのグレイグにも起きている。
(――きれい)
たくましい腕が、険しい顔が、揺れる青いオーラを纏って凄絶に見えた。巨大な体躯が更に大きく見える。なびく黒い服と襟元から飛び出した長い髪。オーラを映してまるで燃えるような翠の瞳。斧を握る大きな手。その戦士の姿をアタシは、きれい、だと思った。
驚いたらしいパールモービルちゃんが片足を引き身構えるが、既にグレイグが地面を蹴っていた。一跳びで肉薄した魔物へ斧を振り下ろす。頭を大きく凹まされても頑丈な魔物はまだ力尽きず、反撃とばかりにグレイグへと体当たりを仕掛けた――が、弱っている。グレイグは小さく二三歩下がっただけで、ダメージもないようだ。その隙をついてアタシはアモーレショットを放った。シゲキ的な愛をたっぷり込めた魔力の衝撃で魔物が大きく吹っ飛び、空中でとうとう黒い煙に包まれて消える。
「イレブン、こっちは片付いたぞ!」
「うんっ!」
嬉しそうな返事を返しイレブンちゃんが大きく頷く。そして勇者の印の浮かぶ拳を強く握り、深く集中した。直後、彼の体をアタシたちと同じ青いオーラが包み込む。
「シルビア! グレイグ!」
力の奔流にサラサラと滑らかな髪をなびかせながら、バッと勢いよく手を掲げるイレブンちゃん。意図を理解して、アタシとグレイグは同時に頷いていた。
「おう!」
「ええ!」
――そのときの感情を、どう表現すればいいのだろう? とても不思議だけど、その瞬間アタシは――いやアタシたちは、やるべきことを完全に理解していた。
グレイグが握った手の中に、光の剣が生まれる。それはゾーンの力を集約した、実態のない剣だ。力を、彼は剣の形にイメージする。アタシも同じだ。全身になみなみと満ちた力を集中させたアタシの手の中にも、グレイグのそれと寸分変わらぬ光の剣がうまれている。バイキルトとピオリムの力を同時に……、だなんて理屈は全く考えていなかった。だけど、不思議と考えなくても出来ていた。まるで、そのやり方を元から知っていたかのように。
言葉もなく、アタシたちはそっと背を寄せ、同じかたちの剣を重ね合わせた。二人の力が一つに溶けていく。全身から力が溢れ出す。触れる背中の、腕の、そして溶け合う力の、温かさを感じる。一つになった力が道のようにまっすぐに伸び、そしてその直線上に立っていたイレブンちゃんの体へと突き立った。
「うぁああああ!」
イレブンちゃんの雄叫びのような声。二人分のゾーンの力を真正面から受け止めたイレブンちゃんの体に、爆発するかのような激しい力が満ちるのがわかった。青を越え、白く発光するオーラ。強く剣を振り上げたイレブンちゃんと対象的に、下ろしたアタシたちの手の中で役目を終えた光の剣が消えていくのを感じた。
アタシはイレブンちゃんを見つめている。グレイグと並んで。
激しいゾーンの力をその身に宿したイレブンちゃんが瞳をきらめかせて笑い、体を低く構えた。そして目にも止まらぬ速さで魔物へと飛びかかる。アタシたちのゾーンも加え限界まで強化された筋力で剣を振った――肉眼でギリギリ確認できた二本の軌道。はやぶさ切りだ。
大砲みたいな勢いで突進されて光みたいな速さで切りかかられ、ただの魔物に耐えられるはずがない。『あくまのきし』ちゃんは足を踏ん張り耐える素振りを見せたが、よろりとよろけると、その場にどうと倒れた。
「ズ……、ア゛……」
耳障りなざりざりした声で何かを呟き、手甲に覆われた指が尚も地面をかくが、そこまで。魔物はがくりと頭を落とした。
その、倒れ伏した鎧の隙間から何かがスウッと溢れ出した。ほとんど透明な、白い光のような何か。
(……「スマナカッタ、アリガトウ」
?)
そんな声が頭に響いた気がしたけれど、現実だったか気のせいだったのかわからないうちに、白い煙はそのままふわりと空に溶けていく。残った鎧も、パールモービルたちと同じように黒い煙になって消えていった。
「――ふぅっ!」
イレブンちゃんが大きく息を吐く。そして、振り向いた。
「大成功!」
両手を掲げ、満面の笑顔でこちらへ走ってくる。アタシとグレイグも片手ずつを掲げた。そして、ハイタッチ! 手のひら同士が打ち鳴らされる高い音が、広い谷に元気よく響いた。
さて、あとは帰るだけである。
キメラの翼を使うとか、イレブンちゃんにルーラを唱えてもらうとか、方法は色々あった。だが、それはあとから考えれば、という話。このときのアタシたちは戦闘の大勝利と初めての連携成功に興奮していて、帰り方にまで考えは及んでいなかった。
来た道を逆方向へ。洞窟を抜け、小川を渡り、もうすぐ行きに立ち寄ったキャンプ地であるというそのタイミングで、それは起きた。
完全に油断していた。この辺りの敵は強くないし、先程も通った道だし、視界は開けているからカエルやカニの魔物なんかがいないのはすぐにわかるし。
ここがどこなのか、アタシたちは完全に忘れていた。
「連携技、か」
その道中、グレイグがポツリとこぼす。
「うまくいってよかったね」
その言葉に、イレブンちゃんが振り返って応えた。浮かべた笑顔は、行きに見た達観したような大人びたものではなく、年相応に無邪気なものだった。
「ああ。しかし不思議だ、こんなにうまくいくとはな」
「ボクたちの息がぴったりってことじゃないかな」
「そうだろうか。……だがやはり不思議な気分だよ。俺は未だに、さっき自分が何をやったのかよくわからんのだ」
グレイグが、何かを考えるように自身の顎に指を当てる。無意識にか整えた顎髭をしごきながら、ほんの少し首を傾げた。
「もう一度やろうと言われても、できんだろうな」
「アタシも」
「残念。すっごい力が流れ込んできて、最高に気持ちよかったんだけどな」
「すごかったわね、はやぶさ斬り。格好良かったわよ、まるでイレブンちゃん自身が雷になったみたいで!」
ヒュンヒュンとはやぶさ斬りのポーズをとってみれば、イレブンちゃんは得意げに胸を張った。
「やっぱり連携ってすごいね。シルビアとグレイグの連携も、早く見たいな」
「ふむ……」
そういえば、行きにはそんな話をしていたんだっけ。グレイグがふむ、と呟きこちらを見た。
「なにか、案ある?」
「そうだな……。やはり貴様の戦い方を見てみないことにはなんとも言えん。いい機会だ。シルビアよ、武器を剣に持ち替えてくれないから」
「今から?」
「ああ。斧と鞭でも良いのだが、片手剣の使い手同士、やはりここは一つ剣の連携技でも編み出してみないか? そのために、俺も今日からしばらく剣に持ち替えよう」
剣持ってるよ、とイレブンちゃんが足を止めて背負っている荷物袋を下ろした。中から取り出したのはデルカダールの紋章が刻まれた黒い剣と、それから見慣れたアタシの剣。こんなものまで入れていたのか。道理でイレブンちゃんの荷物はずいぶん大きかったわけである。カミュちゃんなんかがよく武器を持ち替えるからなんだろうけど、用意の良いことだ。
「……」
グレイグが自身の剣を手に取り、なし崩し的にアタシもアタシの剣を手にする。
白く華奢で綺麗な剣だ。飾りを兼ねたガードのついた柄と、すらりと眩しく銀色に光る刃。細い刀身は、斬るより突く方が向いたつくりをしている。アタシの戦い方ではなく――アタシの技に合わせた剣。
「ほう、それが貴様の剣か。そういえば初めて見るな」
「デルカダールのグレイグ将軍の前で剣を使うなんて、緊張するわね」
「何、旅芸人の剣を見せてくれればいい」
「……」
腰の鞭を外し、代わりに使い慣れた鞘を下げる。柄を軽く握って、位置と慣れた重みを確かめた。隣で同じようなことをしているグレイグ――流石に斧は荷物に入らないので背負ったままのようだ――を横目で見、気付かれないように小さくため息をつく。
(旅芸人の剣……、か)
それはアタシの得意なものだ。例えば投げ上げたりんごをその切っ先で受け止めたり、大きな布で覆った箱を派手に両断して中からハトを出してみせたり――。そういう技を、彼に望まれているということだろうか。アタシの使える剣技は他にもあるのに。
(……だけど、それを振るったら)
きっと、彼はそれが彼の知っている太刀筋と同じであることに気付くだろう。彼は人の心には疎いけれど、剣に関してはきっと目ざとい。アタシが何者なのかを、知られてしまうかもしれない。
……でも、だからなんだというのだろう? アタシはアタシだ。アタシの胸の中には幼い頃から変わらない一本の道がある。それに従うままに歩き、一歩一歩しっかりと進んでいるアタシに、何も恥じることなんてない。だから彼に、アタシが誰なのかを知られたって――
「シルビア!」
イレブンちゃんの硬い声に、いつの間にか一人離れてしまっていたアタシはハッとして顔を上げる。だけど、その瞬間体が固まってしまった。だって目の前に迫っていたのは、鋭く尖った――
「キャアア!」
――鳥のくちばし。
情けないほどの悲鳴が出た。咄嗟に剣を振り上げるも手応えはない。目をつぶってしまったせいで、多分外れたのだ。赤色の巨大な翼に肩を打たれて無様にも剣を取り落とす。そのアタシに、空中で素早く旋回した怪鳥が再度襲いかかってくる。
「!」
その瞬間に起きたことは、本当に一瞬のことだったはずだ。
まだ体勢の立て直せないアタシ目掛けてあの鋭いくちばしが突撃してきて、避けようとしたけれど足がもつれて仰向けに倒れ込んで、――だけどアタシの体を鋭いくちばしが貫くことも、アタシが地面に尻もちをつくこともなかった。
すべてがスローモーションのように見えた。ぱっと散った赤黒い羽毛。銀色の閃光のように閃いたつるぎ。苦痛に限界まで開かれた怪鳥のくちばし。怒ったような険しい横顔と、翻る黒いマント。足を大きく踏み出した動作の軌道を描くようになびく、緩く結った紫の髪。それと、魔物の断末魔の悲鳴。
アタシは、幼い頃に受けた修行でどんなときも目を閉じないクセがついている。どんなときも物事を観察し、瞬時に対応できるように。だから、アタシはアタシの背を支えてくれる誰かの腕に倒れ込みながら、目を見開いたままそのすべての光景を見ていた。瞬時に反応してアタシに駆け寄ってくれる騎士の姿を。魔物が一刀両断にされる光景を。
「――大丈夫か、シルビア」
低い声を載せた吐息が、アタシの鼻の頭を掠める。長い髪がカーテンのように太陽を隠す。うつむいたせいで暗い翠の眼が近い。まっすぐにアタシを見つめているグレイグと、視線があった。彼の腕が、アタシの体を支えていた。
アタシは今、グレイグの腕に抱かれている。
服越しに伝わってくる暖かさと、筋肉の盛り上がり。当然だ、アタシの体は軽くなんてない。ぱんぱんに張った二の腕と、アタシの腕に食い込む彼の指に込められた力強さがその事実を物語っている。だけど、グレイグは腕一本で、易々とアタシを支えていた。翻ったマントから、なにか懐かしいような香りと汗の香りがする。
鋭いくちばしが地面に落ちる前に、黒い煙のようになって消える。アタシはまばたきも忘れて、アタシを見つめる瞳を見返す。全部一瞬だったはずなのに、一秒の何分の一くらいの時間が永遠みたいに長い。翻ったマントのしぼんでいくさまを、アタシは見た。
「シルビア?」
「……ッ」
「あ、おいっ!」
不意に足の力が抜けて、体ががくんと崩れ落ちる。それでもグレイグは支えようとしてくれたけれど、駄目だった。アタシがへたり込むのに巻き込まれて、一緒に地面に膝をつく。ずっと触れていてくれる手のひらが暖かくて、思わずその手の甲に手を重ねた。
「おい、平気か? どこかやられたのか?」
驚いたように見開いた目にアタシが映っているのが不思議だ。ゆっくり瞬きしたけれど、目の前の光景が消えることはない。体を軽く揺さぶられて、はっとする。
「だ、大丈夫……」
こわばった口角をなんとか持ち上げて、アタシは笑顔を作る。
「――ごめんなさい、少し、びっくりしちゃって」
「怪我は?」
「ないわ。平気。大丈夫よ」
笑顔のままさり気なくグレイグの手から離れようとしたが、グレイグはアタシが立ち上がるのを最後まで支えてくれた。温かい手のひらが、服越しに腰のあたりに触れているのを感じる。
今、アタシの心臓はとても早く脈打っている。それを気付かれたくないと思った。息苦しささえ覚えて、胸を抑えながら浅い呼吸を何度も繰り返す。
「本当に、鳥が苦手なのだな」
「ええ、どうしてもダメなの、鳥だけは」
大げさに肩をすくめ苦笑しながら、酷く近いグレイグの顔を見上げる。思ったよりも近くて、首を仰向けないとその顔は見えなかった。お髭の生えた顎辺りから、しっかりした鼻を通って、翠色の目と視線を合わせる。
「――ありがと、グレイグちゃん。助かったわ」
そういえば、とふと思う。
そういえば、昔から彼とアタシの視線の高さはずっとこのくらいの差だった気がする。アタシはいつも、彼を見上げている。その瞳の奥にもっと、昏い炎を宿していたときから。
(グレイグの、眼)
あの昏さはもうどこにもない。今は少し険しくしかめられているけれど、その奥にあるのは勇者を護るという使命の炎や仲間への優しさだ。安心して背中を、命を、体を預けたくなるような。
(……)
アタシが立ち尽くしていると、グレイグはようやく腕を下ろしてアタシを解放してくれた。アタシはさり気なく半歩ほど身を引く。心臓が、跳ねすぎて飛び出してしまいそうだ。
「シルビア、大丈夫?」
「イレブンちゃん。ごめんなさい、びっくりさせちゃったわね」
彼はアタシが取り落してしまった剣を拾っててくれてたみたいで、はい、と差し出してくれる。アタシは礼を言って受け取り、腰の鞘に戻した。ずしりとした重さが、左側にかかる。
「あーあ、格好悪いところ見せちゃったわね」
「平気だよ、完璧な人間なんていないもの」
「イレブンちゃんってば優しいのね……、ありがとう!」
胸の前で手を組み、それからイレブンちゃんの肩にしなだれかかってみせる。アタシのオーバーアクションに慣れたイレブンちゃんは、楽しそうにアタシを受け止めてくれた。全力で寄りかかっているわけではないから、イレブンちゃんの動作も多少はオーバーだ。
そんなアタシ達を見て、グレイグが若干顔をしかめている。カッチカチの真面目な将軍ちゃんには、あんまり理解できないコミュニケーションなんだろう。だからアタシは悪ノリのまま、グレイグの腕にもしがみついてみた。
「グレイグちゃんも、ありがとねん!」
「あ、ああ……」
即座に振り払われるかと思ったけれど、グレイグは体を固くしたままアタシのしたいようにさせてくれた。
巫山戯たように笑いながら、しがみついた腕をわざとらしくぎゅうぎゅう抱きしめる。緊張したように力がこもっている、太くて温かい腕。アタシの体を、一本で支えられる逞しい騎士の腕。頼れる仲間の腕、だと思っていた。ほんの数分前までは。
(……グレイグ)
でもどうやら、その気持ちはいつの間にか変化してしまっていたらしい。
騎士の家の子として生まれたアタシが、人を守ることではなく、守られることに喜びを感じてしまっただなんて。
(グレイグ)
触れても触れ返してはもらえないことに、心の中で呼んでも返事をしてもらえないことに、溢れそうなくらい切ない気持ちが押し寄せてくる。こんな感情を持つのは初めてだったけれど、アタシはその名を知っていた。
数多の詩人が弾き語り、数多の役者が舞台上で演じたその感情。
いまアタシの胸にぽっと咲いたこれがきっと、その「恋」という感情だ。
:
:
裏ゴリバレ前に『ナイトプライド』、
『あくまのきし』のクエスト、
辺りが書きたかった話です。
ずっと書きたかったので書けてよかった!
在庫等の最新情報はpixivを御覧ください。
[pixivのサンプルページヘ]
『あくまのきし』のクエスト、
辺りが書きたかった話です。
ずっと書きたかったので書けてよかった!
在庫等の最新情報はpixivを御覧ください。
[pixivのサンプルページヘ]