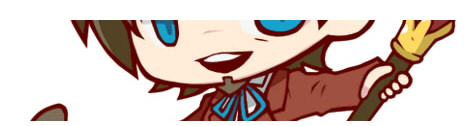
!!! R-18 !!!
現代パラレル+うさみみ(グレイグ)ご注意
グレイグの「発情期」に付き合うシルビアの話
WEBに掲載していた短編2本を含みますので、
以下が大丈夫そうな方のみ手にとって頂ければと思います
※リンク先R-18注意(pass:guresiru)
①https://privatter.net/p/3924101
②https://privatter.net/p/4132813
現代パラレル+うさみみ(グレイグ)ご注意
グレイグの「発情期」に付き合うシルビアの話
WEBに掲載していた短編2本を含みますので、
以下が大丈夫そうな方のみ手にとって頂ければと思います
※リンク先R-18注意(pass:guresiru)
①https://privatter.net/p/3924101
②https://privatter.net/p/4132813
肉食系草食男子との生活
「ただいま、グレイグ」
「おかえり、ゴリアテ」
一人と一匹暮らしの家に、アタシは今日もうきうきしながら帰る。おかえりと言って扉を開けてくれる相手がいるのは、やっぱり暖かくて幸せだ。
「今日もいい匂い。メニューはなあに?」
「鶏肉が安かったから、この間テレビで見たオレンジソースで焼くやつを作ってみた」
「セニカちゃんの番組の? あれ食べてみたかったの。嬉しいわ」
「貴様がそう言っていたのを、俺は覚えていたんだ」
グレイグは得意げににやりと笑う。褒めろと言わんばかりの顔を向けられたので、アタシは腕を伸ばしてその頭を撫でてあげた。ふわふわの耳をぺたりと寝かせる仕草がアタシにはとても可愛く見えるのだけど、客観的に見たグレイグは身長2メートルで筋骨隆々の大男だ。とても、お友だちに「かわいいペットと暮らしてるの」とは紹介しづらいな、なんてことをたまに思う。
「どうした? ゴリアテ」
「ううん、何でもないわ」
耳の根本をちょっと強めに掻いてあげると、グレイグは気持ちよさそうに笑った。
この長い耳が示すとおり、グレイグはうさぎだ。鶏肉も、市販の玉ねぎの入ったオレンジソースも食べることができない。彼自身はチモシーとかにんじんさえあれば十分なのに、アタシのために料理なんてしてくれる。一緒にテレビを見て、アタシが食べたいと言ったものを覚えていてくれる。まるで、優しい同居人みたいに。
「――はい、おしまい」
最後に軽くぽんと叩いて、アタシはグレイグの頭から手を下ろす。
「もうおしまいか」
「せっかくアナタがご飯作ってくれたのに、冷めちゃうでしょ?」
「ああ、そうだな。早く食べてくれ。俺も腹が減った」
「手を洗ってくるわ。先に食べててくれていいわよ」
洗面所に向かうついでにちらりと覗いたリビングのテーブルの上には、白いお皿が二人分並んでいた。アタシのための鶏ステーキと、それからグレイグの干し草サラダだろう。一緒に暮らす相手が作ってくれた、二人分のご飯。グレイグが少しムッとした顔をする。
「それでは、つまらんだろう」
暖かいひと。――ううん、うさぎ。
「せっかく一緒に暮らしているのだ。一緒に飯を食おう、ゴリアテ」
とても幸せで、でも、その事実がとても苦しかった。
グレイグと暮らすようになって、うさぎの飼育本を読んだ。といってもグレイグのような人型動物に関する本なんてないから、普通の、小さなうさぎと暮らすための本だ。それによると、うさぎという生き物には発情期というものがないらしい。逆に言えば、一年中発情が可能なんだそうだ。
なのに、グレイグには発情期という習性がある。聞けば、彼が昔一緒に暮らしていたホメロスちゃんという子にも同じようにあったらしいけれど、症状とか期間とかは違ったんだとか。人型の動物はみんな違った習性を持つのかもしれない。グレイグの場合は一、二ヶ月に一回、三日から一週間ほど続く。そしてその間のグレイグは、いつもと違う行動をする。
例えば、一所に落ち着かずにうろうろする。いらいらして足踏みする。ものを散らかす。常に股間が張るようで、日に一度以上自慰をする。アタシがいるときは、それを手伝ってあげることもある。体臭や精液の匂いがいつもより強くなる。そんな具合だ。
もちろん、他人に構う余裕なんてない。先みたいな会話ができるのは、そうでないときだけだ。
発情期でないときのグレイグは、いつも優しい。仕事で疲れているだろうなんて言って、お皿洗いをしようとしたアタシを風呂に追いやり代わりにやってくれたりもする。食器洗い機ちゃんがやってくれるから面倒ではないんだけど、その優しさが嬉しいのでお言葉に甘えがちだ。
「ね、グレイグ。おフロ、一緒に入らない?」
甘えついでにその太い腕にしがみついて誘ってみたが、今はやめておく、なんて断られてしまった。その言い方は、今じゃなければ一緒に入ってくれそうに聞こえるけど、実際、発情期のときはお風呂だろうがおトイレだろうがアタシを襲おうとするのがグレイグである。
そして『そう』でないときには、こうやって距離を取りたがるのも。
「ざーんねん」
軽い口調で言ってアタシは笑う。後ろで手を組んでくすくす笑えば、からかわれたと勘違いしたのかグレイグも苦笑いを浮かべた。
「それじゃ、一人でおフロ入ってくるわね。寂しいけど」
「ああ、ゆっくり入っていてくれ」
そう言いながらお皿洗いのために水道をひねったグレイグに背を向け、アタシは洗面所に向かうことにした。
白とブラウンで統一した、広い洗面所。この洗面所とお風呂はアタシのお気に入りだ。一人暮らしのマンションを探すときも、一番こだわったポイントである。大きな鏡や人工大理石の洗面ボウルがぴかぴかしているのを見るだけで、気分が盛り上がるのだ。
だけど、その広い鏡にぽつんと映っている自分を見ると、今はちょっと落ち込んでしまう。その鏡は、二人で映るには狭いことを知っているので。
「……はー」
ため息をつきながら、シャツのボタンをぽつぽつ外す。そう言えばグレイグはこれが嫌いだっけ。器用な手指――前足を持った人型の動物でも、太い彼の指では外しにくいらしい。それに気付かなかった最初の頃、一度だけ服を引き裂かれたことがあった。華奢な貝ボタンが外せないけれど、早く欲を発散させたくて焦ったんだと思う。その服はお気に入りだったし値段も結構したから、アタシは悲鳴を上げてしまった。
(そういえば、あの時グレイグはそこでやめてくれたのよね。発情期のあの子が途中でやめてくれるのなんて、あれが最初で最後だったんじゃないかしら)
シャツちゃんはかわいそうだったけれどグレイグもかわいそうだったので、その後ベッドへ移動して裸になってから、ちゃんと相手はしてあげた。本能に流されそうになりながらも罪悪感はあったのか、ちょっぴり優しくしてくれたことを覚えている。
「……」
鏡に映った体を見る。その時に花びらみたいに散らされたキスの痕は、もうアタシの体のどこにも残っていない。
「――はぁっ」
そういえば、ここのところ発情期が来てもグレイグはあまりアタシを抱いてくれない。というより、体調不良が先に来ているみたいだった。頭痛とか、目眩とか。一日寝ていることもある。最後にひどく抱かれたのは、確か年末から年始にかけてだ。アタシを抱いて治るものならいいのだけれど、そうでないと何もできないのが心苦しくて、なのに疼いてしまう体に罪悪感を覚える。
……やめよう、考えるのは。アタシは首を振る。おなかの辺りがなんだか切ないことをできるだけ気にしないようにしながら、タオルを掴んでバスルームへの扉を開けた。
:
: