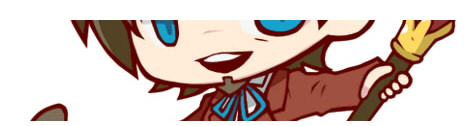
裏/ゴリバレ後/仲のいい二人
ほんの少し意識し合う二人の距離がほんの少し縮まる話
シルビアの出番が少なめです
ほんの少し意識し合う二人の距離がほんの少し縮まる話
シルビアの出番が少なめです
Andante.
人の良さそうな教会の神父は、気安く空き部屋を貸してくれた。
「ええ、この村には宿がありませんからね。旅人さんにはこちらをお貸しすることにしているんですよ。もちろんどなたにもというわけでは有りませんが、あなた方はイレブンの友人ですからね」
ありがとうと礼だけ言い、俺とゴリアテは教会の空き部屋に足を踏み入れる。日々丁寧に掃除をされているのか、普段使用されていない部屋だというのに床はピカピカだった。
「お部屋、貸してくれてよかったわね」
ゴリアテが嬉しそうにいい、荷物を部屋の端に下ろす。
「イレブンちゃんは、イレブンちゃんのうちに来るといいって言ってくれるけど……」
「寝る場所に困ってしまうからな」
そう、単純に場所がない。ベッドはロウ様に譲りイレブンとカミュは二階で雑魚寝するとのことだが、あと二人はさすがに入れまい。
「まあ……、困るのはここも同じなんだけどね」
そう言って、ゴリアテは一つしかない寝台にちらりと目を向ける。
「――グレイグが使っていいわよ」
「いや、貴様が使え」
「じゃあ、この前と同じように、いっしょに使いましょ」
「……そうだな」
教会を旅の宿として提供してくれるのはありがたいのだが、部屋は狭く寝台は一つしかない。初めてここを使わせてもらったときから、それは俺たちにとって重要な問題だった。寝台の使用権を互いに譲り合い、最終的には決闘寸前まで行ったのは、今考えても頑固すぎたと反省している。同じことはゴリアテにも言えるだろうが。
そんなこんなの結果、折衷案として二人で使うことにしたのだ。木で作られた大きめのベッドは思いの外頑丈で、二人分の体重をなんともなく支えてくれた。
「グレイグ、今日こそ潰さないでね」
「……善処する」
背中合わせで寝た日は、ゴリアテを壁際に追い詰めて押しつぶしていた。仰向けで寝た日は、ゴリアテにのしかかって押しつぶしていた。もちろん毎回謝るが、温かかったし平気だと許してくれる優しさに甘え続けるわけにもいかないだろう。今日こそ、ゴリアテに安息の眠りを与えてやれるとよいのだが。
「さーてと」
呟いたゴリアテは、書き物机の椅子に、横向きに腰掛けた。長い足をすらりと組み腕を組んで顎に手を添えるという流れるような動きを、俺は見るともなしに眺めた。
「……それにしても、イレブンちゃんも罪づくりよねえ」
空いた時間をどうしようか、などと相談されるのかと思った。だが、ゴリアテが口にしたのは全く別の話である。
「罪?」
「そう思わない? エマちゃんの思いに気付かないのかしら」
ゴリアテは憂いを帯びた表情ではぁと悩ましげなため息をつき、ちらりと顔を上げて俺を見た。その視線の意味は、あなたも座ったら、という辺りだろうか。俺はのそのそと彼の前を横切り、寝台の端に腰掛けた。部屋に唯一ある椅子はゴリアテに取られてしまったので、腰掛けられるのはここしかなかったのだ。
「あの少女とイレブンは、幼なじみだと言っていたな。幼い頃はただの友情だったものがいつしか意味を変えたとして、その変化が緩やかだったなら、隣にいてもなかなか気付かぬのではないか」
例えば俺のように、と言おうとして、やめる。今は『彼』のことを考えるべき時ではないだろう。
(……いや、『彼』でなくとも)
物憂げな表情で床を見つめている、ある意味では幼なじみと呼べるかもしれない相手を俺は見た。変化が隣で緩やかに起こったのであれば気付かぬこともあろう。だが離れた所で起きた変化なら気付ける、と言うわけでもあるまい。
(なのに俺は、よく気付けたものだ)
勇者に同行することを決め、改めて勇者から仲間の紹介を受けた時、その男はシルビアだと名乗った。旅芸人としての名こそ聞いたことはあるが、知らない人間だ。だと言うのに俺の胸の内に湧いた懐かしいような愛おしいような感情は、今でもうまく説明できない。
(彼がゴリアテだと、気付いてしまえば変わらぬ部分も見えてくるのだがな。人に優しく明るいところも、髪の色や瞳の色も)
かつて、ひとときの道を共にした相弟子の姿を俺は脳内に描く。よく笑う、明るい男だった。身長の差は今よりも小さかったと思う。体格も、多分。当然だろう、俺が更に騎士の道を目指しているとき、彼は異なる騎士道を歩んでいたのだから。例えば二の腕、例えば太腿。筋肉の付き方に差も出ようというものだ。尻も、昔と比べて今のゴリアテはあんなに張りがあって柔らかそうな……。
「ん? どうかした、グレイグ」
「い、いや」
俺はいつの間にか凝視していた視線を慌ててそらす。ゴリアテは不思議そうな表情で首を傾げていた。――危ない。一体俺は何を考えていたのだ……。
不意にくすりと吐息を漏らす音が聞こえ、俺はゴリアテへ視線を戻す。
「うふふ、アタシもなんでもないわ。ただ、アナタはアタシに気付いてくれたんだなって思って」
「……俺も、今そのことを考えていたところだ」
「あの時は本当に驚いたわ。それまで、気付いてるなんて雰囲気、アナタ全然出さなかったじゃない」
「確信がなかったからな」
俺は肩をすくめる。正直に言えば、逃げるように去ろうとする背中を呼び止めたときもまだ確証は得ていなかった。ただ咄嗟に口が動いてしまっただけ。それが正解だったと理解できたのは、彼とともに試練を乗り越えたあとのこと。
「……アタシもね、イレブンちゃんがソルティコに行こうって言い出したときから……」
ぽつりと呟き、ゴリアテは机に腕をついた。そのまま上半身を倒し、腕の上に頭を乗せる。奴の細めた瞳から目をそらそうと下を向くと、斜めに揃えられた足を見つめる羽目になった。
「……なんとなく、もうすぐ、アナタに気付かれてしまうんじゃないかな、って思ったの。不思議よね。二人でゆっくりお話したことさえなかったのに、もうすぐ気付かれるかも、なんて」
:
: