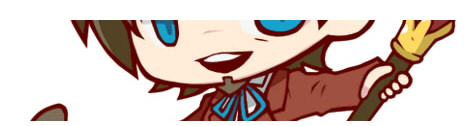
裏/未ゴリバレ/付き合っていない二人
悪夢に囚われたグレイグを助けに行くシルビアの話
登場シーンの大半でグレイグがショタ化しており、
様々オリジナル設定が含まれます。
悪夢に囚われたグレイグを助けに行くシルビアの話
登場シーンの大半でグレイグがショタ化しており、
様々オリジナル設定が含まれます。
やさしい夜明け
:
:
「……おじいちゃん。どう?」
沈黙に耐えかねた、という様子でイレブンが口を開く。すぐには反応しなかったロウだが、ベッドの上にかざしていた手を下ろすとゆっくりと振り向いた。
「反応は弱いが、恐らくは思ったとおりじゃ」
「ロウさま、それは」
「うむ……」
全員の視線の集まる先にはベッドがある。そこにはグレイグが横たわっていた。サーコートを脱ぎベルトを抜いた楽な格好で、目を閉じた顔には何の表情も浮かんでいない。ただ、その胸は規則正しく上下し、生きているのだということだけはわかる。眠っているのだ。
だが、ただ眠っているだけならばセーニャやシルビアが不安そうな顔で、カミュやベロニカがどこか怒っているような顔で、グレイグの寝顔を見つめるわけがない。――彼の眠りは、もう二日も続いていた。
ザメハ、めざめの花、しまいにツッコミを入れても彼の眠りは覚めない。ただの眠りであるはずがない。
しかし心当たりはあるのだ。ロウは、その心当たりを確信に変えるために最後の確認を行っていたのである。皆を眺め、ロウは口を開いた。
「……みな、先日の戦いのことは覚えておるな?」
「イレブンのお父さんの、絶望を食べていたって言う魔物のことよね」
心当たりとは、それだ。ベロニカの言葉に仲間たちが頷くのを見てロウも頷く。
数日前、ユグノア地方に立ち寄ったときのこと。イレブンの提案でネルセンの宿屋に一泊した一行は、揃って奇妙な夢を見た。その夢に出てきた鎧の騎士こそが、イレブンの父でありロウの義息子のアーウィンだったのである。
夢に導かれるようにユグノア城跡を訪れた一行は、そこで虚ろになったアーウィンと、彼の内側に住み着いて絶望を食らっていた魔物に出会った。イレブンの勇者の力で悪夢の中から魔物を引きずり出し、一行と魔物とは死闘を繰り広げた。眠りの魔法を巧みに使うそいつに苦戦しながらも、最後はイレブンがとどめを刺し戦いは終わった、……はずだったのだが。
視線をベッドに移し、ロウは言葉を続ける。
「アーウィンを蝕んでいたバクーモスという魔物。わしらの手で倒したはずだが、やつは元々夢の中を自由に行き来することができる魔物じゃ。肉体が滅んでも、その魂の一欠片は逃れおおせたのじゃろう。……肉体にとどめを刺された瞬間、眠りの中にいた者の中にな」
「……そのせいで、グレイグさまは目覚めないのですね」
セーニャの呟きに、恐らくは、とロウは頷いた。
大きな牙と爪を振り回し邪悪なブレスを吐きかけ、破壊的な攻撃を繰り出す合間に、魔物は聴いたものを眠りへと誘う呪文を唱えた。その度に誰かしらが望みもしない眠りに落ちる。カミュがザメハを唱え、シルビアがツッコミを入れ、手の空いたものはめざめの花を掲げた。目覚めては眠らされ、また目覚め、精神ばかりが疲れゆく中、イレブンがとうとう会心の一撃を魔物へと与えた。その瞬間に、しかしちょうど眠りの中にいたグレイグの目を覚ます呪文や特技は、間に合わなかったのである。
「……」
戦いの間は何とか立ったままだった体は、戦闘が終わったその瞬間にぐらりと傾いで倒れた。近くにいたシルビアが慌てて抱きとめなければ、冷たい石畳に頭を打ち付けてしまうところだったろう。
魔物――バクーモスを倒したことで、囚われていたアーウィンの魂は救われ、彼の救いを求めていたエレノアと共に大樹へと帰っていった。これで、ネルセンの宿屋で見た奇妙な夢から始まった一悶着は解決、と言って良いだろう。
だが、グレイグは目覚めなかった。
「……アタシ、紫色のモヤモヤしたものがグレイグちゃんの胸の上で消えるのを見たわ。あれが、あの魔物ちゃんの最後の悪あがきだったのね」
シルビアが呟く。それは、バクーモスを覆っていた邪悪なオーラと同じものだったのだろう。
眠り続けるグレイグを連れてなんとかネルセンの宿屋まで戻ってきた一行だが、グレイグの様子に変化はなかった。それは、原因ごと連れてきてしまったからだったのだ。
「じいさん、原因はわかった。ならどうすりゃおっさんは目覚める? もう一回こいつの力を使うのか?」
カミュが親指を立ててイレブンを示す。イレブンは自身の手の甲を見た。確かに、父アーウィンを悪夢から救い出せたのはこの力のお陰だ。だがロウは首を振る。
「いや、止めておいたほうが良いじゃろうな」
「何でだよ」
「残された魔物の力は弱い。だがどうやらグレイグの魂に絡みついておるようなのじゃ。全く、往生際の悪い。人質のようなものじゃよ。この状態で勇者の力を使ったりしたら……」
「……失敗したら、グレイグに影響があるってこと?」
「最悪、グレイグの魂も道連れにされてしまうじゃろう」
「……」
ロウの言葉は重く響いた。
イレブンが拳を握りしめる。マルティナが胸を押さえる。カミュは視線をそらしたが、その眉間にはやりきれない苦悩のために深い皺が刻まれていた。
「じゃあ、どうしろって言うの。このまま見捨てるしかないってわけ?」
怒りを込めた口調でベロニカが言う。ロウに当たった所で何が変わるものでもないと分かっているのに、苛立ちが抑えきれない。そんな仲間たちを眺め、ロウは自身の髭をなでた。
「――先にも言った通り、今魔物の魂とグレイグの魂は複雑な状態にある。まずは、これをどうにかせんとなるまい」
「どうにかって」
「夢の中に入り、絡んだ魂を解くのじゃ」
夢の中に? と聞き返したイレブンに、ロウは頷く。
「バクーモスは絶望を喰らう魔物じゃ。人の魂を捕らえ、繰り返し悪夢を見させる。逆に言えば、悪夢を見るからこそバクーモスは彼の魂に執着するのじゃろうな」
「――なら、その悪夢からグレイグを解放すれば」
「うむ。体から追い出すことは出来ずとも、絡み合った魂を分断することが出来るかもしれん」
「おじいちゃんはカンタンに言うけど、『夢の中に入る』となんてことできるの? あたし色んな魔法を学んできたけど、そんな魔法は聞いたことないわ」
「その方法なら、当てがある」
一度言葉を止めると、ロウはイレブンを見た。
「ユグノアの王族に伝わる子守唄があるのじゃ。どんなに寝付きの悪い子供でも眠らせるという不思議な歌なのじゃがな」
「おじいちゃんが、前にボクに教えてくれた歌のこと?」
ああ、そうじゃ、とロウが頷く。歌詞や旋律には特に変哲のない優しい子守唄だが、ラリホーの魔力を込めて歌えば魔物さえ眠らせることができる。もちろん子守にも使えるし戦闘にも応用できる、用途の幅広い歌なのだ。
「その他にも、歌詞にある一節を加えることで特殊な効果を発動することができるのじゃ。いくつか伝わっているその中に、『触れ合う相手と同じ夢を見せる』というものがある。恐らく、これが使えるじゃろう」
「まあ……! すごいです!」
セーニャが胸の前で手を組み、声を上げた。他の仲間達も互いに顔を見合わせ、頷きあう。一気に空気は明るくなった。
「いくつか伝わるって、他にも何かあるの?」
ロウに問いかけたのはベロニカだ。もちろんじゃとも、とロウは頷く。
「自分では忘れてしまった古い記憶を見せたり、行きたい場所に行ったり、あとはそうじゃな、好きなおなごに格好いいわしの夢を見せたりもできるのじゃ!」
「……ロウさま」
「ゴホン! じょ、冗談じゃよ!」
マルティナの睨みを受け、慌てふためくロウ。緩んだ空気を引き締めるためか「とにかくじゃ、」
と言って真面目な顔をするが、カミュとベロニカは顔を見合わせ肩をすくめた。
「――ともかくじゃ。あとは、誰がグレイグの夢の中にゆくかじゃな。望ましいのは、相手――今回の場合はグレイグじゃが、彼と縁のある者じゃ。絆の強い者ならば、夢の深いところまで潜れるじゃろう」
「ボクじゃ駄目かな?」
イレブンが控えめに手を挙げるが、ロウは首を振った。
「イレブンよ、お前とグレイグの間に絆があることは知っておる。じゃが、この歌を歌うにはお前の声が不可欠じゃ。これだけは、ユグノアの血を引く者以外には頼めんからな」
「そうだよね……」
「なら、迷う必要ないじゃない。わたしが行きます、ロウさま」
進み出たのはマルティナだった。生まれたときからグレイグは傍にいた。自慢の騎士だ。彼女は、自分以上にグレイグと強い絆を持つものは父と、もう一人の騎士ぐらいだろうと思っている。イレブンもホッとしたように頷いた。だが、ロウはやはり困った顔を浮かべる。
「絆の強さというのなら、確かに姫ほどの適任はおらんじゃろう。だが、姫には別の問題がある」
「問題? 何でしょうか」
「夢の中というのは、いわゆる精神の世界じゃ。物理的な力より精神的な力――言うなれば、魔力が物を言う。言い辛いが姫よ、そなたはそういった方面には……」
「……弱い、ですね」
マルティナが肩を落とす。彼女には、自身で言う通り魔力がない。もし人間の持つ能力を数値化するならば、彼女の魔力はゼロと表されることだろう。それは、精神の世界で自己の存在を保つことすら難しいということを表している。
勇者と勇者の盾として絆を結んだイレブンは歌を歌うために、そして姫と騎士として絆を結んだマルティナは魔力という問題のために。残りの仲間たちは顔を見合わせた。
魔力の高さ、という純粋な観点だけで見れば、適任はベロニカかセーニャだ。だが彼女たちはどちらもグレイグとの関わりがほとんどない。カミュも同様だ。そしてシルビアは。
「……シルビア?」
彼は、ずっと黙っていた。解決策が提示された時も、ロウが『冗談』を言った時も。いつもならば一番に喜んだり、助平な話題に怒りを表したりするはずのシルビアが。苦しげな表情でグレイグを見つめていたシルビアは、その視線をロウへと移す。
「――アタシに、行かせてくれないかしら」
「シルビアが?」
彼ならば、確かに魔力は高い。ただグレイグとの絆は強いとは言えないと、誰もが思った。年齢が近いようだし、共に剣を使うから戦闘ではタッグを組むことも多い。だが、イレブンやマルティナと比べれば、そんな絆は余りに弱い。
「シルビア、もしかして自分を責めているの? 確かに戦闘が終わった時、グレイグの一番傍にいたのはあなただわ。だけど、わたしだってめざめの花を掲げるのが間に合わなかったんだから同じよ」
マルティナが問いかけるが、シルビアは首を振る。何か言いかけてやはり口をつぐみ、それから、自嘲気味に微笑んで再度口を開いた。
「……アタシ、グレイグちゃんとは小さい頃に会ったことがあるのよ。彼が覚えているかどうかはわからないけれどね。マルティナちゃんもイレブンちゃんも行けないなら、その次の候補はアタシかなって思ったの。……それだけよ」
初めて聞いたわ、とマルティナが呟く。これまで、長い期間とは言えずとも共に旅をしてきた仲間だ。だというのに、グレイグもシルビアも知り合いであるような態度などとってはいなかった。
もちろん、シルビアが嘘をついているとは誰も思わない。シルビアが言うのならそうなのだろうし、だが同じ口で言う通り、もしかしたらグレイグが忘れてしまう程度の弱い繋がりだったのかもしれない。
「そんな薄い縁が役に立つのか?」
カミュが腕を組み首を傾げる。そのカミュの腰を、ベロニカが横から肘打ちした。
「でも、追われた記憶くらいしかないあたしたちよりマシなんじゃない? イレブンもマルティナさんも無理なんだから」
「何だよ、別に悪いとは言ってねえだろ」
ベロニカとカミュの会話が口喧嘩に変わりそうになるのを見てとり、慌ててシルビアが手を振る。
「あら、ただの一意見よ。こんな薄い縁じゃ意味がないかもしれないわよね。他に方法があるなら、そのほうが良いと思う。例えば、マルティナちゃんに魔力のこもったアクセサリーをたくさん身に着けてもらうとか……」
「ボクは、」
遮るように口を開いたのはイレブンだった。静かな、しかし通る声にシルビアは言いかけた言葉を飲む。カミュもベロニカも、口をつぐんでイレブンを見た。澄んだ翠の目がまっすぐに、シルビアを見つめていた。
「――シルビアが良いと思う」
「イレブンちゃん」
「二人の絆はそんな薄いものじゃないと思うよ。シルビアなら、きっとグレイグの夢の奥までたどり着けるはずだ。そうでしょう、シルビア?」
イレブンは微笑んだ。あまりに素直なその表情に、シルビアはたまらず視線を外したが、その顔には少し困ったような笑みがあった。
「……まったく、イレブンちゃんったら。何だか、なんでも見透かされてるみたい」
「そうだったらいいなって思っただけだよ」
そう言ってイレブンはまた微笑み、そして皆の顔を見渡した。
「ボクはシルビアが良いと思うけれど、みんなはどう?」
「イレブンがいいなら、あたしはいいわ」
「私もいいと思います」
「他にいないんだから、賭けてみるしかないだろ」
「マルティナは?」
「私が魔力のこもったアクセサリーを着けたところで、夢の世界に全部を持っていけるとは思わないわ。どうやら、今回私は無力みたい。……グレイグをお願いね、シルビア」
「ええ、任せて」
シルビアは軽く握った手を胸に当ててみせた。まるで騎士のような仕草に、ほっとしたようにマルティナが息を吐く。
「――それじゃ、ロウちゃん。アタシがどうすればいか、教えてくれる?」
うむ、とロウが頷く。
「では、始めようか」
それに皆が頷き返し、グレイグを取り戻すための作戦は開始されたのであった。
:
<中略>
:
「……あなたは、まほうつかいですか?」
「違うわ、アタシは旅芸人。シルビアっていうの。――最も、今のは手品じゃないしタネも仕掛けもないから、魔法みたいなものかもしれないけれどねん」
「たびげいにん」
「あなたはグレイグ――ちゃんよね?」
「なんで知っているんですか?」
「ウフフ、ひ・み・つ!」
立てた人差し指を唇に当て、シルビアと名乗った旅芸人は茶目っ気たっぷりにウィンクしてみせた。何故だか胸がどきりとして、少年は慌てて目をそらす。
「でも、――やっぱり、ここはあなたの夢の中なのね。あなたの心一つで、世界もあなたの姿も変わるんだわ」
「ゆめ?」
いつの間にか、辺りの様相は変わっていた。黒く煙を上げる瓦礫も火の燻る焼け焦げた畑も、そこにはない。穏やかに回る風車と、広がる金色の小麦畑。足元には誰も倒れておらず、どす黒い赤の染み込んだ地面もなく、鮮やかな色の花が咲き乱れて青々とした草原の広がる丘。丘の下には石畳の道がある。ああ、覚えている。あの道はいつも、荷車を引いたジュース売りの男が鐘を鳴らしながら歩いてきた道だ。鐘の音が聞こえると、はしゃいで母親に小銭をねだったものだ。
視線を戻せば、男は覚悟を決めたような真剣な顔で少年を見ていた。
「……信じられないかも知れないけれどね、ここは夢の中なの。現実のあなたは眠っているのよ。アタシはあなたを、――グレイグちゃんをこの夢から覚ますためにここに来たの」
:
:
裏かつゴリバレ前の話が書きたくて
色々と要素を詰め込んだ話です
原作の年齢設定と一部ずれていますが
ご了承頂けますと幸いです。。
在庫等の最新情報はpixivを御覧ください。
[pixivのサンプルページヘ]
色々と要素を詰め込んだ話です
原作の年齢設定と一部ずれていますが
ご了承頂けますと幸いです。。
在庫等の最新情報はpixivを御覧ください。
[pixivのサンプルページヘ]