First Generation
|
真夜中、雷鳴とともにシアルフィ家の老家令は目覚めた。春も半を過ぎた草原の城は、穏やかな気候の内に、快い眠りに沈んでいる。 ”聞こえるか…聞こえるか我が民よ” 主たる公爵に良く似た声に呼ばれ、年取った従臣はまなこを擦ると、慌てて周囲を眺め回した。小さな寝室にはほかに誰もいない。言葉は、頭の中から響いてきたのだ。 「私に話し掛けるのはどなたです?」 ”我こそはバルド、シアルフィの祖なり。お前に重大な使命を託しに来た” 信心深い翁はたちまちかしこまって答えた。 「バルド!おお聖騎士よ!この私めにできます事なら何なりとお申し付け下さい」 ユグドラル大陸の人々は総じて純朴であり、聖戦士の御名を前にして、疑いや怪しみを示すなどもとより慮外の事だった。 ”お前も公爵家を取り巻く深刻な危機は察していよう” 「はっ…バイロン様が不在の折、ドズルとフリージは卑劣な謀を巡らし、シグルド様は危険な遠征に次ぐ遠征を命じられ、勝利を重ねてはいるものの、都からは妬みと恐れを買うばかり。果たして王国におけるシアルフィの地位は如何なりましょうや…」 ”それはどうでもよい。もっと差し迫った問題がある” 「と仰りますと?」 ”子供の不足だ” 「…はっ!」 ”シグルドの率いるシアルフィ軍には 「なるほど。確かにまず真の問題は外患より内憂。しかしどのようにすれば。男女の数の釣り合いばかりは、私めにも…」 ”案ずるな。お前にこれを授ける” 家令の目の前に突然、黒い光の帯をまとった一振りの杖が浮かび上がる。 ”魔杖リジェンダ。自然の理を整え、種族の繁栄をもたらすために竜族が産みだした至宝だ” 「と仰りますと?」 ”分かりやすくいえば、余った性をもう片方に変えるのだ” 「そ、それは…」 何やら不吉さを感じた翁は、射干玉に輝くねじれ木の棒から半歩後退った。 ”我が言葉を疑うのか?我の下せし使命を軽んじるのか?” 「いえ、滅相もない。ただ、私にはとても魔法の杖を扱う才能はありませぬ…」 ”案ずるな、我が力を貸し与えよう。一時、お前は司祭となるのだ” 突如、ヴェルダンの森よりなお暗い闇が、部屋の片隅から広がって、老臣を包み込んだ。 「おお…おおお…この力は…」 ”竜の力。大地を統べる王たる竜の力だ。では行け。我が僕よ。群雄に繁栄の恵みをもたらすのだ” 「はは…」 いつしか黒い薔薇の紋章を縫い取った長衣が、翁の身を包んでいた。新たに生まれ変わった神の僕は、自信ありげにリジェンダの杖を掴み、裾からもう一つ短い杖を振り出すと、高々と掲げる。 「リワープ!!」 たちどころに影のような姿が揺らいで、虚空に現れた六芒星の中へ消えた。 黒衣の司祭がたどり着いたのは、シアルフィ軍の本営だった。といっても将兵が忙しく行き来する一画からは少し離れた、指揮官の執務場所で、あたりは静けさに包まれている。音もなく現れた侵入者に、誰も気づいたようすはなかった。 翁が視線を巡らすと、すぐ向こうに従士の身なりをした少年と、戦装束をまとった若い男が腰かけ、灯火の下に床几を挟んで羊皮紙の束に取り組んでいるのが認められた。年下の方は肩までで切り揃えた髪に、愛くるしい相貌で、遠目には少女とも紛う外見だ。年嵩の方は豊かな青い髪をユグドの貴顕らしい落ち着いた形にまとめており、面立ちは精悍ながら、どこか優しげなところがある。まさしくシアルフィ家の次期当主、シグルドとその軍師オイフェである。 ”まずはあれだ” 神が短く告げると、翁は首を傾げて己の内に問い返した。 「シグルド様はすでに奥方を迎えられておりますが…」 ”愚かな。ほかの公子はたいてい、あの年なら側室の一人や二人迎えている。さもなくば嗣子に奇禍があった時、直系の血筋が絶えてしまうからな” 「しかしシグルド様はディアドラ様を娶られてからはあの方一筋。側室の話などいくら持ち出しても相手になさらぬのです」 ”そこよ。あれの堅物ぶりはよく知っておる。だが小さなころから身内同然にして育った腹心ならどうか?” 「は…もしや」 ”スサールの孫ならば、優秀な子を生むはずだ” 「なるほど…なるほど…さすがはバルド様。では早速。リジェンダ!」 黒い波動がたちまち、年若い軍師を捕える。 「うあ!!」 直前まで山間部での補給路について意見を述べていた少年が、いきなりへたりこんだ。主君は即座に立ち上がってそばへ歩み寄り、身をかがめて尋ねる。 「どうしたオイフェ?」 「はっ…はっ…いえ…んっ…なんでも…んぅっ!」 従士はいきなり股間を押さえ込んで、悲鳴を漏らす。頬は上気し、大きく見開いた瞳の端に涙がたまっていた。震えるうなじの辺りから、なにやら甘い香りが立ち昇る。シアルフィの公子は奇妙に胸が騒ぐのを覚えて、頭を振ると、そっと幼い軍師の肩へ掌を置いた。 「具合が悪いなら休め。それともクロード様か誰かを…」 「だ、だめ…だめです」 少年は左の手で主君の袖にしがみついて、あえぎながら首を振る。しかし右の手は本人の意志とは無関係に服の上から秘部をまさぐっていた。 「どうした。そこが痛むのか?」 「ひっ…ちが…だめ…だめです…シグルド様…」 「つまらない事で恥ずかしがるな。前線から離れていても戦場だぞここは。見せてみろ。手当てできなければ誰か司祭を呼ぶ」 「やだぁ!だめぇっ!!」 「暴れるな。しょうがないやつだな…」 膂力で優り、組み打ちにも長けたシグルドは、あっさりとオイフェの洋袴を脱がせる。下着がぐっしょり濡れているのを見て取り、よもや粗相をしたのかと匂いを嗅ぐと、野薔薇に似たむせるような薫が鼻をくすぐり、よろめきそうになる。 知将スサールの孫は、あられもない姿のまま、耳まで真紅に染めて、手で顔を隠していた。 「これも解くぞ」 わざわざ断る訳を自分でも分からないまま告げると、公子は年若い家臣の秘所をおおう薄布をはぎとった。するとそこには、あるべき幼茎がなく、あるはずのない細い割れ目が、栗色の毛に縁取られて覗いていた。 「オイフェ…これは…」 「え?」 主君の戸惑った声に、軍師も思わずむきだしになった脚のあいだに視線を落とし、驚愕の叫びを漏らした。 「えぇっ!?な…なに…僕なんで…え?どうして…」 「落ち着けオイフェ…これは恐らく何かの杖の力だ。敵軍の司祭か…あるいは…」 青年がさらに顔を寄せると、少年、いや少女は甲高い悲鳴を上げた。 「ひっ!シグルド様ぁ!近っ!だめ…息…かかっ…や…」 作られたばかりの陰唇は、ほんのわずかな刺激にも過敏に反応するようだった。シグルドは慌てて呼吸を止めたが、無意識のうちに指で割れ目の上側の縁にある包皮に覆われた突起に触れていた。 「きぃぁああああっ!!!!!」 「すまない!…しかし本物…としか思えない…こんな力を持った杖が…あるのか…クロード様か…レヴィンなら分か…だがなんだ…この…匂い…まるで…」 公子は憑かれたように従士へのしかかった。剣を握るのに慣れた指が、奇妙な大胆さで柔肉の濡れたすき間をこすり、新たな嬌声と痙攣を引き起こす。 「ふぁあ…ああああ!!!!…っやぁ…やらぁっ…シグルド様ぁ…」 「…可愛いな…ディアドラと同じくらい感じやす…って…ちょっと待て」 青い眉がきつく寄って、強い精神の集中を示す。幾多の闘いに鍛えられた長躯が、標的を前に飛び掛るのをためらう獣のごとくにおののいていた。牝を求める牡の性と、聖戦士の裔としての厳しい志操がせめぎあっているのだ。 「オイフェ…離れてくれ。私一人では…抑えきれない…すぐにクロード様を…」 誇り高い顔立ちを苦悶にゆがませながらも、シグルドは穏やかな口調で告げる。オイフェは言葉に篭る気遣いと優しさに、体の芯が熱くなるのを覚えた。主君に流れるのと同じバルドの血が沸き立ち、頭の奥を本能が爪を立ててかきむしった。 ”そうだ。子孫を残せ。栄えあるシアルフィの純血を” 「シグルド様ぁ…下さい…シグルド様の…お情けを…」 「そんな…オイフェ…」 みなまで云わせず、幼い唇が、兄とも慕ってきた男の台詞を塞ぐ。口淫を誘うつたない舌使いだけで、限界まで張り詰めていた忍耐の糸を断ち切るのには十分だった。 がっしりした腕が、以前よりさらに華奢になった小姓の背を抱いた。もう一方の手は秘裂をまさぐり、粘膜を擦って、いっそうしとどに濡れそぼらせていく。ただ裂け目をなぞり、内側をかき混ぜるだけでなく、時折、陰核をつねっては、細い四肢がもがくのを抑え付け、さらに嬲るように指の数を増やしていく。 「痛っ…いたぁあぃ…シグルド様ぁ…痛…ぎぅ!」 「どうしてだろう…オイフェにはディアドラにはしない乱暴をしたくなる…」 「…そんなぁっ…ぁんっ!」 「オイフェに…だけだ…だめか?…」 「…う…いぇ…どうぞ…ぁっ!?…ひぁああっ!!」 許しを得たとたん、男の指がまた若芽を強くひねる。仮初の少女は手足を突っ張らせ、弓なりに反り返った。寸毫を経て、小振りな尻が床に落ちると、敷物の上に温かい湿りが広がって湯気を立てた。 「粗相は…いけないな。きれい好きのオイフェらしくない」 「ひぐ…ひくっ…だって…だってぇ」 泣き出す年下の伴侶を眺めながら、シグルドは罪悪感と共に不思議な愉悦を味わっていた。 ”側室としての振る舞いを教えるのだ” 「…オイフェは悪くない。これまで軍師としての教えしか受けていなかっただけだ。側室…側室としての振る舞いはあとから学べばいい」 「側…室…?」 「あ…ああ…」 火と燃えていた公子の双眸に、かすかな翳りが過った。まるで押し付けられた演技に耐えられなくなった役者のように、獲物を貪る動きがぎこちなさを帯びる。 ”ためらうな。目の前で震える小さな体は、戦場でお前の怒り、昂ぶり、憂いを受け止める道具だ。時に故郷から伴った稚児や、遠征先で捕えた女を使って、ロプト帝国の頃より多くの将軍が続けてきた習わしだ。バルドの裔よ。お前は勝者として当然の生贄を喰らうのを拒んできた。気高かった。わずかな闇の付け入る隙もないほどに。だが最後にディアドラを抱いたのはいつだ” 「…私は…ヴェルダンやアグストリアで…兵の一人たりとも…軍規から外れた行いを許しはしなかった」 「…?…はい…」 「では…何故…部下に禁じた狼藉を、大事なオイフェにしているんだ…」 青年の逡巡に対して、少女となった少年は何と答えるべきか分からなかった。ただ火照った花芯から、耐え難い疼きが脈打つように全身へ伝わり、明晰な思考を難しくしていた。 ”オイフェ。主君の迷いを解け” 「ぼ、僕…シグルド様の…気持ち…分かっています…ディアドラ様の事も…でも僕は、シグルド様の助けになりたい…どんな風にでも…こうして抱いてもらえるの…幸せです…だから…」 「…そうか…そうなのか…それなら…」 再び口付けが始まる。今度はさきほどより遥かに長く、濃厚に、甘やかに。舌と舌とが互いを求めてからむあいだ、従士のほっそりした指は主君の腰の帯を解いて、服を緩めさせていく。 シアルフィの若殿は欲望の印を露にすると、スサールの後継ぎの秘所へ押し当て、閉ざされた門へと挿し入れていった。 「んむ…ひっ…ぁっ…」 「大きく息を吸って」 永遠にも等しい刹那のあとで、大小二つの体が完全につながる。涙を浮かべてすがりついてくる少女を、ごつごつした広い掌が優しく愛撫する。 「動くぞ…大丈夫か…」 「は…はい」 公子の腰使いは、はじめゆっくりと、やがて幼い軍師が耐えられる限度を計りながらも次第に速さを増していった。草原へ調教に引き出されたばかりの若駒の並み脚から、幾度も騎乗の訓練を受け、疾走に慣れた雄馬の駆け足へ徐々に移ると、最後には強靱な筋肉のすべてを活かして抽送を繰り返し、小さな愛人の子宮に当たるほど激しく突き上げる。 破瓜の印が愛液と混じり合って、薄桃に泡立ちながら流れる。痛みをこらえるうめきも、遂には嬌声へと転じた。従士は、膨らみかけた乳房をシアルフィのお仕着せごしに主君の胸板にこすり付け、胎内を攪拌する陰茎を固く食い締めると、何とか尻を振り、腰をひねって相手に快楽をもたらそうとする。 「無理を…するな…ディアドラも最初は私に任せていた」 「ひっ…はぃ…あんっ…あっ!?」 突如、腟に炎が点されたような熱が生じる。官能が灼けつく潮となって下腹部から胸へ、腿へと燃え広がっていく。 シグルドも変化を察したらしく、幼い愛人を宙へ抱え上げ、軽々と跳ね躍らせた。主君とのつながりのほか、身の支えを失ったオイフェは自重の分だけいっそう深々と剛直に貫かれ、随喜の涙を零した。 ”子種を求めよ” 「シグルド様ぁ…シグルド様ぁ…ひぎゅぅっ!…注いで下さいぃ!僕の中にぃっ!…きゃんっ!…」 「ああ…オイフェ…」 待ち望んでいた命の素が肉の器を満たしていく。シアルフィの血を引く”側室”は、至福のあまり失神しそうだった。腟に収まった逸物はなお完全には固さを失わず、結ばれたままの状態を保っている。そのまませっかちに接吻を求める主君に、幼い愛人は従順に応じた。 ”そうだ。それでいい” 「んむ…オイフェ…私の側室になってくれ…この杖の力はきっとバルドの恵みだ…オイフェのように賢い子が欲しい。セリスを支えてくれる兄弟が。できれば何人も」 「はい…お望みどおりに…んっ…シグルド様のまた大きく…っ♪」 「ちゃんと子供ができるようにしたい…これからは毎日時間を作る…それがシアルフィ直系の義務だ…なぜ今までそう思わなかったんだろう…」 ”城の執務にも、領土の視察にも、敵地への遠征にも。スサールの孫はどこへも付いていく。好ましい機会に脚を開かせて種付けすればいい。野営の慰めのため、常に葡萄酒をいっぱいにした革袋のように、いつも腹を精で満たし、お前への夜の奉仕だけ考えさせておけ。光の公子の軍師ではなく、淫蕩な妾として仕込むのだ” 「ああ…軍師の任は解かなくては…妾…いや側室にするのだから」 「え…」 「だめか…オイフェにしか頼めない」 先生の叱責を覚悟した生徒のような、不安げな上目遣いをしながら、シグルドは愛人の華奢な双臀を揺すり上げ、教え込んだ肉の歓びを思い起こさせる。オイフェは可愛らしく鳴くと、よだれと涙をぽたぽた落としながら、主君にひしと抱きついた。 「んぁっ!…はひ♪僕、シグルド様のお妾になります♪」 ”妾は世継ぎの養育をすべきではない” 「セリスの養育はほかへ任せよう…その時間はずっと私の膝の上に居てくれ」 ”ティルフィングの使い手はセリス以外に絶対に必要だ。何としてでも子供をもうけるのだ” 「混乱を避けるため、しばらく表向き軍師として仕えてもらう。だが服装は脱がすか捲るかしやすいものにしてくれ。短い空き時間でも子作りができるように。シルヴィアの穿いているようなものが良いだろう。あれは軽快で実用的だ。下着も防寒上避けられない場合以外は付けないでくれ」 少女の尻肉を鷲掴み、乱暴に揉み解しながら、青年は乾いた口調で指示を伝える。草原に沸く泉のような澄んだ瞳には、既にかすかな濁りが浮かんでいた。主君の何かが、外から抑え付けられ、捻じ曲げられているのを、従士は意識の奥底で察した。しかし深い愛情は変わっていなかった。同じように歪められてしまった幼い心は、悲しみよりも喜びで異常な命令を受け止めた。 「…はい♪シグルド様のお望みどおりに♪毎日、好きな時に抱いて下さいませ♪」 「良かった。オイフェには本当に助けられる」 「あれで良かったのでしょうか。バルド様…何か大きな間違いを犯した気がするのですが」 ”完璧だ。やはり兄弟同然に育った仲というのは素晴らしい。ほかの相手ならあそこまで簡単にシグルドは堕ちなかっただろう” 「堕ち?」 ”気にせずともよい。次はシャナンだ。バルムンクの使い手をあれ以外に作る必要がある” 「はぁ。しかしあちらはオードの家柄では」 ”今はシアルフィの傘下にいるではないか。よいかティルフィング、バルムンク、ミストルティンはいずれも闇を滅ぼす恐るべき力を持っている。言ってみれば同類だ。もはやミストルティンは剣、使い手とも問題ないが、ほかは危うい。バルムンクはイザーク攻めにより、適切な管理下に置かれたが、使い手はまだ躾も受けず野放しだ” 「シャナン様は幼くとも英明な御方ですぞ」 ”見所はある。先ほどのスサールの孫と同じように。だが念のため、別に子供を作らせ、こちらで確保しておくべきだ。来るべき反乱の時、神器と使い手がともに王国の側にあるように” 「バルド様の仰りようは私にはとんと…」 ”我を信じよ。さて、シャナンには叔母がいたな” 「アイラ様でいらっしゃいますね」 ”うむ。あれでいこう。イザークの者だけで固まっているところを狙って…” 司祭はぴたりと足を止めた。前方の土を踏み固めた道を、二人組の騎士が笑い交わしながら馬を走らせていったのだ。 「お待ち下さい。あれはアレクとノイッシュではありませんか」 ”どうでもよい” 「何を仰います!あの二人とアーダンはシアルフィの忠実な家臣。特にアレクとノイッシュは容姿も行いも優れ、武芸も達者であるにもかかわらず、六公家の血を引かぬがために結婚もできず、ひたすら武器ばかり鍛えておるのですぞ。何と哀れな若者たちか…」 ”どうでもよいというに。真の脅威は三剣と光竜だけだ” 「いやいやバルド様。そういう料簡の狭いのはいけません。私め。いささか邪道な気はいたしますが、あの二人のどちらかに花嫁を用意してやりますぞ」 ”…杖の使用回数には限度があるのだぞ。修理すると五万金はかかる。教団も緊縮財政の折…” 「神がけちけちなさいますな。そーれ追いついた。リジェンダ!」 しかし施術を焦ったせいか、あるいは二人の騎士のどちらにかけるかを迷ったせいか、杖の波動は何と双方を包み込んでしまった。 「何と」 ”言わぬ事ではない…” 呪文の残光が消えると、そこには金髪と緑髪、豊満な美女が二人、呆然と互いを見交わしていた。当然ながらアレクが乗る牝馬は牡に、ノイッシュの去勢馬は牝になっている。 「あわわどうしたものか…」 ”知らぬ。知らぬぞ…” 慌てふためく司祭を尻目に、騎士たちは転げるように鞍から降り、地面にうずくまった。二頭の駒は鼻息も荒く、互いの匂いを嗅ぐと、数秒して雌が走り出し、雄が後を追って、暗闇の中へ駆け去っていった。 青草の色の髪に頭巾をかぶった女が、苦しげに鎧の紐を解き始める。金髪の片割れも遅れて装備を解き始めた。平素は鮮やかな武具の扱いが、なぜかひどくもたついている。 アレクがようやく胸当てを外すと、ぶるんと音がしそうな勢いで西瓜のような乳房が双つ転び出た。ノイッシュも紡錘型をした肉鞠を解放すると、やっと息を吐く。 「なんだこれ…」 「胸…だな…女性の…」 神妙に呟く山吹の髪の騎士に、相棒は頬を引き攣らせたかと思うと、いきなり両の眼を見開き、大急ぎで腰当てを外し始めた。 「おいアレクどうした」 「まさか…うそだろ…」 緑髪の騎士は服の下に手を突っ込むと、凍り付く。 「ない!なくなってる」 「な、何がだ…」 アレクは返事をせずにノイッシュに飛び掛ると、熟練した手並みであっという間に腰当てを外し、強引に鎧下をずり降ろそうとする。 「ちょっ…アレク。お前いったい!?」 「やっぱりない!!俺たち女になっちまった!」 「馬鹿な。そんな事ある訳が…」 股間を覗いて眼を丸くする金髪の騎士に、緑髪の連れは呼吸を乱しながら、尋ねかける。 「…おい…しかも何か…熱くないか…」 「ああ…まさか…」 「病だ!…アグストリアの水のせい…かっ?…」 「ふざけるな…お前、城下でよくない遊びをして、おかしなものを伝染してきたんじゃ…ないだろうな」 ノイッシュの疑わしげな視線に、アレクはかっと頬を染めた。 「だったら…何でお前まで…んっ…こんなになってんだ…よっと!」 いきなり、深緑の籠手をはめた指が同僚の秘裂をまさぐる。 「ひぁっ!…よせ!…悪ふざけにもほどが…んっ…ぁんっ…」 「お前…こそ…遊び女みたいな…声出すじゃねぇ…かっ…」 「こいつ…調子に…ひんっ…んっ…」 ノイッシュは唇を咬んであえぎを抑えようとした。認めがたい快さと、恥ずかしさと、腹立たしさが頭をぐるぐると回っている。アレクはどんな状況でも優位に立っていないと収まらないのだ。従士としてシアルフィの宮廷に上がってすぐの頃は、何かにつけて器用な幼馴染のあとを付いて回る羽目になり、年は変わらないのにいつも目下扱いされていた。初めて自慰を知ったのもその時だった。笑われながら相手の掌で精通を迎えたのだ。 「くそ…いつまでも…そんな手が通じると…思うっ…な」 真紅の籠手が、若草色の茂みに触れ、力任せに秘貝を弄る。 「にゃっ!?…んっ…お前…っ…」 「どう…した…んっ…余裕がなさ…そうだ…ぞ…」 「…こんな事やっ…てる場合…ふぁっ…かっ…」 「そっちが…ぁっ…はじ…めた…」 「手…放せ…」 「そっちこそ…っ」 負けてたまるかとばかり、アレクは目の前のたわわな乳房に指を食い込ませ、乱暴に絞り上げる。痛みとともにとろけるように甘美な感触が広がり、ノイッシュの意識は心拍一つのあいだ、完全に飛んだ。だが持ち前の耐久力を発揮して、どうにか官能の渦に溺れず踏み止まると、相棒の赤く色づいた胸飾りをつまみ、容赦なく引っ張る。 「ぃぎぃぃいっ!!?」 「…っ…はっ…な、涙目に…なってるぞ…お前…」 「この…お、お前こそ…もう…我慢できないいん…じゃ…ないのか…」 「強がるなよ…胸…弱いだろ…がっ…きぅっ…」 「っ…お前の…ぁっ…ここ…もう…び…びしょびしょに…なって…」 「お前こそ…もう、籠手の指が…二本も…はっ…入って…」 どちらともなく噛み付くように接吻すると、汗に滑る二つの肢体が重なり、荒々しく絡み合う。遠目には騎士の組み打ちにも見える、力任せの戯れ。だが幼馴染たちは慣れない異性の官能に翻弄されながら、秘貝と秘貝を擦らせ、それぞれの肩に歯を立て、指で後孔さえ抉って、能う限り狡猾な攻めで、互いの快楽を掻き立てていた。 「んっ…ノイッシュ…お前…もう…本当に…限界…だろ…」 「アレクこそっ……あそこ…熱…」 嘲り返したつもりが、切なげな告白に変わっている。勝利の予兆を察したアレクは、情欲に導かれるまま、同僚の肉付きのよい太腿に舌を這わせてゆき、絶え間なく果汁を滴らせる杏の芯に触れた。 「ひぁあああっ!!!」 黄金の髪の乙女がだらしのない嬌声を上げる。緑髪の乙女は豹のように獰猛な笑みを浮かべ、弱点を遠ざけるように腰を高くもたげ、脚を左右に大きく開いて爪先立った。だが鼻先は獲物の最も柔らかな肉に埋めたままで、山吹の叢を掻き分けて、粘膜をねぶり、わざとらしく音を立てて愛液をすする。 「アレクぅ…アレクぅ…!!!!」 派手に潮を噴いて、ノイッシュが果てる。アレクは満足げに舌なめずりをして、秘所から口を離すと、体の向きを変えて、同僚の肩を抱き起した。 「俺の勝ちだな…ところで何でこんな事してたんだっけ」 「馬鹿…んっ…」 緑髪の乙女が唐突に唇を啄ばむと、相棒は大人しくされるがままになる。二人の陰部にはまだ燠火が燻っていた。むしろ怒濤の昂奮が過ぎ去ったあとには、かえって満たされぬ想いが募っていた。 「違う…これじゃ…」 「ああ…これじゃ…治まらない…」 四本の脚を複雑に交差させ、疼く性器を摺り合わせながら、二匹の牝は求めているものの正体を悟り、路傍にあえてしどけない格好をさらしたまま、じっと待ち受けてた。 やがて遠くから、地を震わすような重い足音と、鋼鉄の甲胄のぶつかる金っぽい響きが近付いてくる。やけによく通る野太い声が、先触れとなって乙女らの元へ届いた。 「アレク、ノイッシュ!夜戦訓練に俺を置いてくなよぉ!」 現れたのは誰あろうシアルフィの盾、固い、強い、遅いと三拍子揃った守将アーダンだった。分厚い装甲をまとった巨躯が、牛歩の鈍さで進んでくると、妖しく着衣を乱した騎士たちはふらりと立ち上がり、釣鐘型の乳房を露にして出迎えた。 「アー…ダンっ…♪」 「は?」 「よう…待ってぜ…」 「へ…どちらさま…ってアレク?ノイッシュ?お、お前らその格好いったいどうしたんだ!?」 立ち尽くす大男の左右に、それぞれたおやな女体がしなだれかかる。 「うあっ…おい止めろ!」 「固い事を言うな…」 耳元に熱い息を吹きかけながら、金髪の乙女が甲胄を脱がせにかかる。先ほど己の装備を解いた時より落ち着いて、よどみのない手捌きだ。アーダンは、同僚が従士時代から鎧の付け外しという騎士のたしなみを得意としていたのを思い出し、焦りを覚えた。 「ちょっと待て!待て!何をするつもりだ!」 「何って…聞くなよ…」 もう一人の女がくすくす笑いながら答えにならない答えを返す。次いで夏の盛りの木々の葉の色をした髪を揺すると、相棒と同じく肩当てや胸当ての紐をほどきながら、白くなるほど握り締められたごつい拳に、剥き出しの腹をこすりつけた。 「そんなに…がちがちになるなって」 「ほら…外れた…相変わらず…凄いな…」 「ふふ…俺たちが…どんなに鍛えても…いつも勝てないもんな…」 「すごく…逞しい…ぞ」 合わせて二十本の白い指が、岩の塊を積み上げたような筋肉を撫で回す。ノイッシュが背伸びして巨漢の耳を噛むと、アレクは腰を落として鋼板のごとき胸に舌を這わせ、乳首をくすぐった。 「頼む!勘弁してくれ!俺は…俺は普通の女の子と普通に結婚して…幸せな家庭を築くんだぁ!いくら美人でも男はぁ!男は嫌だぁ!!」 半泣きになるアーダンに、二人の同輩はともに怒ったような上目遣いをする。やがて緑髪の乙女がにやっと妙に男っぽい笑みを浮かべて、楽しげになじった。 「とかいって、従士の頃。夏至の祭りで光の巫女の仮装したノイッシュに興奮してただろ」 「そうなのか?」 「ノイッシュはがきだったからなぁ…蜜酒飲んでこのでかぶつの膝の上に座って、すやすや寝てただろ…あの時、切れたこいつが押し倒すんじゃないかとひやひやしたぜ」 「…で、でたらめだぁ…」 |
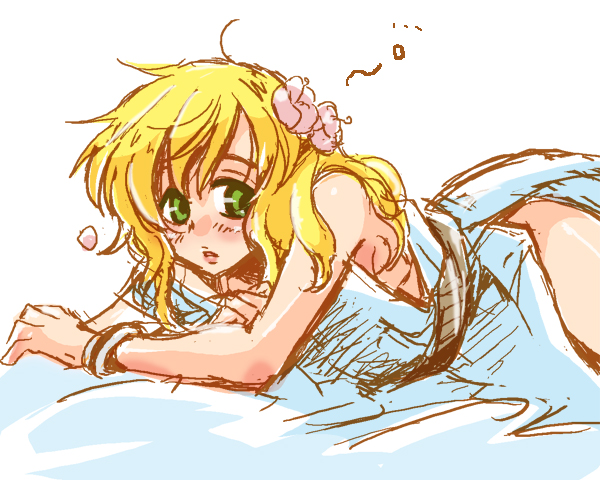 |
|
「そういえば…尻に何か固いものが当たっていた記憶が…」 「うわあああああ!ノイッシュ!アレクを信じるな!こいつは女の子とする練習とかいって厩にお前を連れ込んで、ほとんど毎晩接吻してだろ!いつも適当な嘘を吐くんだ!」 「ふぅん。覗いてたのか。あれも別に嘘じゃないぜ。割と参考になった。まぁでも、城下町の女の子より、ノイッシュの方がうまくなってたよ。最後の方は」 「馬鹿…あ…もしかして…アーダンも混ぜて欲しかったのか?」 「ち、違う違う違ーう!!」 「今なら…あの時は…できなかった事でも…してやるぞ」 ノイッシュは熱っぽい視線で、戦友の巌を彫り削ったような横顔を仰ぐと、膝を付いて、布地の上から魁偉な膨らみにしゃぶりついた。 「うほ!?」 快感の余り、アーダンは唇を蛸のように窄めて首を竦める。アレクも親友に負けじと腰を降ろすと、帯を外して、鎧下を脱がせた。 「ん…すご…」 丸太のような両腿の間に、子供の手首ほどもありそうな陽根が隆々と聳え立っている。きつい男の匂いに陶然としながら、山吹の髪の乙女はためらいもなく鎌首に口付けし、丁寧に舐め清めていく。思いのほか懸命な奉仕ぶりを、相棒はちょっと当てられたように眺めてから、遅れまいと肉棒に吸い付いた。二つの唇、二枚の舌が奪い合うように剛直をねぶり、ぬらつく先走りや恥垢にいたるまでを、甘露のごとくに味わっていた。 「うおおおおっ…おおおおお!!」 ヴァルハラにある色町の生え抜きの娼妓でさえ、とてもしないような丹念な仕事ぶりで、二匹の牝は牡を煽り立てる。 「ぐおおおおおお!!!」 獣じみた咆哮と共に、巨漢は濃い白濁をぶちまけた。黄金と翡翠、彩りの異なる艶やかな髪を欲望の徴が穢していく。性を転じた騎士たちは、ブラギの祝福を授けられたかのごとき恍惚とした表情で、汚辱を受け止めた。 「はぁっ…はぁっ…こんなの…はじめてだ…そんな女の子が…まさかこんな…いや、女の子じゃない…こいつらは女の子じゃない」 「試して…みるか…?」 緑髪の乙女が嫣然と見つめ返す。膝を曲げたまま両脚を広げて、指で肉襞を広げ、桜桃色の内側を恥ずかしげもなく剥き出しにしている。 「うぅ…う…」 「アーダンは、私の方がいいよな?…」 金髪の乙女は、守将のすねにかじりついて、豊かな胸を押し付けながら、潤んだ瞳で訴えかけてくる。 「うぉおおっ…」 「ふん…臆病者…据え膳に手も出せないようのろまだから、いつまでたっても恋人ができないんだよ」 「お、俺はのろまじゃない!!!くそ…やってやる!やってやるぞおおおお!!」 幾本もの綱索を捻り合わせたような腕が、娘の姿になっても決して軽くはない同輩たちをまとめて抱え上げる。一方はごつい指を蜜壺に捻じ入れ、もう一方は菊座を穿り、豊満な肢体を宙を支える手がかりにする。 「きゃんっ…♪」 「ひぎっ!?…そこ違…」 「うるさい。口答えするな!」 排泄口を弄られて不平をこぼすアレクを、アーダンはさらに指を奥へ捻じ込んで黙らせる。そのままのっしのっしと、篝火もかすかな光しか投げかけられない影へ歩いて行くと、振動でさらに深く内側を抉られた乙女らは、歓喜と苦悶の悲鳴を重唱を奏でた。 いきり立った巨漢は、石積みのすぐそばの平らな草地に荷を投げ出すと、力づくで四つん這いにさせた。 「よく聞けお前ら!まず俺をもう少し敬え!いつもひどいぞ!どこの城を訪れても、ご婦人方に注目されるのは、王族の方々を除くとお前らばかり!その癖アレクは女の子を紹介しないし!間違ってる!俺はこんなに固くて強いのに!馬鹿にして!」 「…わ、悪かったよ…結構傷付いてたんだな…お前…」 「でもアレクも私も決まった恋人が居る訳では…」 「もてるだけで十分羨ましいんだ!!ええい。馬に乗れるのがそんなに偉いか!再移動できるのがそんなに偉いか!」 シアルフィの守将は歯ぎしりしながら、騎士たちの引き締まった双臀を平手打ちした。 「うぁっ!!んっ…ぁっ!」 「ひぅっ…あん♪…ひぐっ!!ぁんんっ!!」 「それでもシグルド様はな。城の守りを任せられるのはお前だけだって…お前に任せられるのは城の守りだけだ…じゃないんだぞ!それなのに!お前らは!俺の生え際がどうとか!顔が蛮族とか!髪の色だけシレジア人っぽくておかしいとか!」 「ひぁっ…言ってな…きゃんっ!」 「待っ…っひぃっ!?…も…分かった…か…にぅっ!」 アーダンが折檻を止める頃には、二組の尻は幾重にも紅葉が積もって、すっかり腫れ上がっていた。ノイッシュは真赤にひりつく柔肌を無理に掴んで、しとどに濡れた金糸雀色の叢を広げる。 「も…そろそろ…してくれないか…」 「くぅ…都合のいい時だけ俺を便利に使いやがって…そんな体だけの関係で…」 「ちが…分かった…ちゃんとお前と結婚する…」 「ほげ!?じょ、冗談言うな…何でそんな姿なのか分からないが、元に戻った時どう…」 「…騎士に二言はない…私をお前のものにしろ…ちゃ、ちゃんと子供を作ってやる。お前の頑健さや、待ち伏せの技に長けた忍耐強さ…打たれ強さを持った子供を…沢山…」 抑え難い官能の高まりと羞恥をないまぜに、金髪の乙女は涙ぐみながらも、つかえつかえ大胆な求婚の台詞を紡ぐ。本来ならば年頃の娘へ、もっと違う表現で差し出されたはずの愛の告白は、しかし竜族の魔法によって屈折し、無骨な戦友へと向けられていた。 「う、嘘だろ…でも…ノイッシュと俺の子なら、固くて強くて、しかも馬に乗れて…再移動ができて…待ち伏せも必殺も突撃もできる…騎士に…だ、だけど俺みたいな徒士になったら…」 「別に…私は…子供がお前みたいな逞しい守将に育っても…構わない…ぞ…」 「うう…ノイッシュ…俺は…俺は…やる!!」 破城槌の一撃にも似た打ち込みが、前触れもなく潤みった秘裂を貫いた。予想だにしないような、子宮を押し上げられる凄まじい圧迫感に、乙女となった騎士はほとんど白眼を剥き、舌を突き出して、唾液の糸を幾筋も地面に落とす。新妻の純潔を示す血が、初夜の床となった白詰草の褥に紅玉の飾りを散らせた。 「…あ゛ぉお…っ!!!」 「ぬぅ…きつい…だが…騎士なら…耐えろ!」 「あぐっ!!?…ひぃ゛ぃぃっ!!!!」 小山のごとき体躯が備えた膂力のありったけを解き放って、後背位で挑みかかる。受け止める側は、肉付きのよい太腿に脂汗をにじませ、腰の骨をも砕けとばかりにぶつかってくる恐ろしい質量に、ただ打ち震える。たわわな胸の双丘は草地に押し付けられて潰れ、臙脂の唇は喃語めいたままやきを垂れ流すばかりになる。 「ノイッシュ…さっき…でかい口…利いた…割に…情けない…な」 アーダンは破顏して少し勢いを落とすと、相手の胸へ掌を差し入れ、指の間からあふれそうなたっぷりした乳房を包み込んで、按摩するように揉みしだく。ノイッシュはわずかに息を吐くと、けなげに尻をもたげ、さらなる蹂躙を待ち構える。 巨漢は余裕を装って低く笑うと、幾らかゆるい速度で抽送を続けながら、ほどんど痙攣に近い腟の締め付けを楽しみ、絹張りの鞠のような胸の柔肉を弄んだ。 「あ゛ぁ゛っ…あ゛ぅ゛っ…あ゛ーっ」 涙と洟と涎でぐしゃぐしゃになった騎士の容貌に、日頃の凛々しさはない。ついさっきまで、保っていた意気地もはや溶け崩れ、ただ桁違い力でぶつかってる男から少しでも優しさを引き出そうと、しなやかな背から腰をくねらせ、つたないしなを作るだけだ。 「ふんっ…強がり過ぎるから…そうなる……」 シアルフィの守将は、赤児のようにくしゃくしゃになった同輩の顔を見下ろしながら、尊大にうそぶいてみせる。 見習い時代もそうだった。廃城での胆試しを思いついたアレクに、ノイッシュはすぐ賛成して、アーダンを引っ張り込んだ。はしっこい従士たちは、柄のでかい割に臆病な同輩をからかうつもりだったろうが、いざ探検が始まると、どちらもひしと脇腹にしがみついてきて、言い伝えにあるロプト兵の亡霊とやらが出てきた場合に備え、文字通りの盾代わりにしたのだ。 はっきりいってアーダンだって怖くてたまらなかったのだが、仲間が生まれたての仔犬みたいに震えながら、体温の高い体を押し付けてくると、勇敢に振る舞うよりなかった。結局さまよう死者などはどこにも居なかったのだが。そういえばあの時、余計に怯えていたのは、緑髪の少年のほうだった。 ちらりと視線を向けると、アレクは唇を咬み、右の五本の指をすべて使って秘所をめちゃくちゃに捏ねまわしながら、左手で乳房を鷲掴み、乱暴にねじっている。緑柱石の双眸は、狂おしい嫉妬に燃えていた。 「アレク…欲しい…のか?」 「当り前だろ…ノイッシュが…堪え性…ないから…譲って…やっただけ…」 「分かった。交代するか…」 「やっ……ちゃんと…終わらせてから…」 金髪の乙女が懸命に腟を締め付け、咥え込んだ陽根を抜かせまいとするのへ、相棒はするりと近付いて、いきなり耳朶を噛み、擦れ声で囁いた。 「じゃぁさっさと搾り取れ。ちゃんと旦那様にお願いしてさ」 シアルフィの精鋭として名を馳せた騎士は、頬を鬼灯に染めると、馬鹿になりかけた腰を揺すって、かそけく鳴いた。 「アー…ダン…お前の…子種…注いで…」 「ぅおぉおう!!!孕めぇっ!」 二度、三度と腹を突き破るような打ち込みのあとで、灼熱の溶岩のような熱くどろどろした塊が、ノイッシュの胎内で爆ける。牝の歓びに蕩けながら、乙女は草の褥に突っ伏し、瞼を閉ざしてぐったりと動かなくなった。巨漢が太杭を引く抜くと、ぽっかり開いた穴から多量の白濁が赤いものと混じって溢れ出た。 「ったく…何だかんだでこいつは…おいしい所持ってくんだ…叙勲も俺より早かったし…」 アレクは羨望のこもった笑みを浮かべて呟くと、親友の秘所に指でを伸ばして、軽くかき混ぜてから、濃い精液を掬って、愛しげに口へ運ぶ。アーダンは肩で息をしながら、淫らな仕草を鑑賞していたが、出し抜けに腕を差し伸ばすと、むんずと相手のうなじを抑え、先ほど花嫁を貫いたのと同じように犬這いにさせた。 「俺は…お前らを公平に扱ってきたぞ…」 「痛たたたた…加減しろ…」 「うるさい!だけど今日は二人を差別してやる。だいたいいつも、俺を笑いものにするのはお前だよな、アレク。ノイッシュは素直だが、お前はいたずらばっかしやがって」 「な、何の話だよ…」 「林檎酒も飲んだ事ないノイッシュに、大人の食卓からちょろまかしてきた蜜酒を飲ませた挙句、俺の膝に行くようにそそのかしたの…誰だよ」 「…いや、だってお前がすごい目付きでノイッシュ見てたから、どんな反応するか知りたくて…」 「こいつ…どうしてそんな不真面目なんだよ!叙勲だって、お前がつまらん不行跡を慎んでいればノイッシュより早かっただろ!一昨年の山賊退治だってなぁ!」 「はは…今更…俺が真面目にやっても…意味ないだろ」 アレクは首を後ろにひねると、徒な流し目をくれる。街の女から覚えでもしたのか、ひどく男の気をそそる素振りだった。アーダンは唸って、肩から指を引き剥がす。 「ふん!わざわざお前の功績を報告した俺の身にもなってみろ!」 「…おい…じらすなって…」 「口答えするな!」 「んっ…あああっ!」 また肛孔を弄ってお喋りを封じる。口数の減らない騎士が、後ろを玩具にされるだけでひどく従順になるのを察して、巨漢はかさにかかって直腸を拡げる指を増やした。腸液がにじんでくるまでじっくり粘膜を擦ってやると、緑髪の乙女は泰然としたうわべをかなぐり捨てて、切なげな喘ぎを漏らし始めた。 「そこ…そこはぁ…」 「うるさい…」 「たの…む…本当にっ…そこ…やば…」 「何だよ…前に使われた事でも…あるのかよっ…?」 冗談めかして尋ねると、アレクはわなないて言葉を途切らせた。だが深緑の茂みからはさらにつゆが噴き出して、激しい興奮を明らかにしていた。 「…知らなかった…」 驚愕に目を見張ったアーダンは、それでも戦友の菊座を寛げるのを止めようとはしなかった。ノイッシュより、ややほっそりした肢体が、排泄口を抉られるたびに弓反りになって、可憐な反応を示す。 「別に…よくあ…あぅぅっ!!…ゆびぃ…っ…きもぢぃ…っ!…」 「それ誰だよっ?」 「…っ…それは…はぅ…んっ!…んぅっ…は…んっ…」 全部で四本の、剣だこの出来た指を、よく仕込まれた後門が苦もなく受け入れた。 「…じゅ…従士の頃…上級…騎士に…」 普段の洒脱な態度からはかけ離れた卑屈な笑みを浮かべ、緑髪の乙女は不浄の穴に男の手を締め付けた。封じ込めた記憶が蘇るとともに、熟れた体はまだ青い頃に教えられた媚態を忠実に再現しようとしていた。 「気づかなかった…」 「ふふ…夏至祭りで…一番目立つと…グリューンリッターのおっさんたちに…っ…呼ばれ……なぁ、それ…もっと…奥まで入れ……そぉっ!!!そこぉっ!!!すごぉ…っ!!んっ!」 「アレク…」 情けなくも、戦友の打ち明け話を聞いたアーダンの屹立は、いっそう誇らしげに天を衝いていた。確か光の巫女はノイッシュの前の年にアレクも演じていた。当時、従士の中で際立った美童として知られ、やたらとちやほやされていた同輩を、図体ばかり大きく不細工な徒士見習いはただ疎ましく感じていたのを思い出す。 「そんな…バイロン様は…」 「…あはっ♪…知ってた…だろ…っ…でもシグルド様はぜん…ぜん…はぁっ…久しぶり…このごりごりぃっ♪…もっと…引っ掻いて…乱暴にして…あひっ……」 整った面立ちを緩み切らせ、騎士は幼い頃に慣れ親しんだ嗜虐をせがみ、浸りきった。 「…俺…上手だったんだぁ…こんな風に…してもらいながら…バルドの叙事詩、諳じるのとか…蜜酒だって…ちょろまかしたんじゃ…んっ…ご褒美だった…んだから…」 「…そうか…」 ずるりと、蕾を拡げていた手を引き抜くと、月や星、遠い篝が作る仄明かりの下に、淫らな肉の華が咲くのが見えた。軽いようで本当はひどく気位の高いアレクが、かくも嬉々として稚児の役をこなすようになるまで、どの位かかったのだろうか。 「あ…もう止めちゃう…の…か…」 「お、俺は…こっちに用があるんだ」 襞を指で押し広げて、たっぷりした汁気を確かめるように軽く揉んでから、魁偉な逸物を押し付ける。緑髪の乙女は四つ足をついたまま頭を下げ、股の間から、凶器の侵入を凝視した。 「俺とも…子供作る…気かよ…」 淫らがましい格好のまま、形ばかり呆れ顔をつくろいながら、騎士は期待に満ちた熱い眼差しを返す。丈高い守将は大げさに頷いてみせる。 「おう…追撃と見切り…待ち伏せが使えて、おまけに固くて強くて、早い騎士をな!」 「うっぐ…ぁんっ♪」 さすがのアレクも、もう弁を振るうどころではなかった。後ろの孔が、どれほど男を知っていても、魔法で作られた前の孔に迎え入れるのは初めてなのはノイッシュと変わりがない。おまけに弱点の直腸を弄られて、完全に下拵えができあがっているために、ほんの三、四度の抽送を受け止めただけで、恍惚の際まで昇り詰めてしまう。破瓜の証を散らしながらも、緑髪の乙女は床慣れした娼妓のごとく嬌声を迸らせた。 「あぁっ!んっ♪ひぁっ…ひゃぅっ♪」 「…ぅ…うまい…こいつ…くっ…出るぞぉ!!」 「あ゛ぅ゛…ぁ゛!!!」 ほんの数時間前まで気の置けない友だった相手に、したたかに精を放ちながら、アーダンは子孫を残せる牡としての、深い満足を味わった。 ユグドラルの星辰は西へ西へと移ろい、ついには東の果てにひときわ鋭く輝く”ウルの瞳”が現れて、夜明けがもうまもなくだ告げた。 だだ広い練兵場は濃い暁闇に沈み、片隅の一箇所だけに、篝を崩して作った焚火のはかない灯が揺らめいている。傍らでは、牡牛を思わせる隆々とした筋骨の大男が、どっしりと胡座をかて暖を取っている。膝の上には黄金の鬣の乙女が丸くなって瞼を閉ざし、脇にはもう一人、同じくたおやな四肢の持ち主が、翡翠の鬢を掻き上げながら、幸せそうに寄り添っている。 「…下半身の感覚がない…絶対やりすぎだな…ノイッシュなんて途中で降参してたのに…気を失ってもしつっこくがっついて…童貞は加減を知らないからなぁ…」 「…んむむ…ノイッシュにはお前がけしかけたんだろ…」 「俺だって休む時間が要るだろ…交代交代でやっても、あいつがあんなに早くへばったら回復しきれない…ったく…体力と頑丈さだけが取り得のでかぶつとやるのは骨が折れる…」 「んむ…」 「…グリューンリッターのおっさんたちも、お前は持て余してたろうな。だいたい神速機動の騎士団を擁する我が公国に、何だって歩くばっかの鎧男が居るんだよ」 「…気にしてる事を…城の固めには俺みたいな守将が就くのが伝統だろうが。いいか、空を自在に駆ける竜騎士で恐れられるトラキアにも、凄い将軍がいてだな。マンスターとの国境に建つミーズ城を治めて、王の信頼も厚いそうだぞ」 「トラキア?あの禿鷹どもの国か?エスリン様とキュアン様の敵だろうが…」 「いや、その将軍はマンスターやレンスターの騎士にも一目置かれてるんだって…ふぅ…まぁ馬でそこらじゅうを駆け巡れるお前らには縁のない話だよなぁ…」 「またすねたのか?」 「うう…ノイッシュみたいに静かにしてれば可愛いのに」 「悪かったな…」 ぱちぱちと薪の爆ぜる音がする。快い疲労に浸りながら、恋人たちはまだ眠るつもりになれずにいた。アーダンは踊る焔をにらむと、ぶっきらぼうに尋ねた。 「ノイッシュはどうして、その、グリューンリッターのところに行かなかったんだ」 「…おっさんたちだって、寝ちまったがきを起こしてまで遊ぼうとは思わないだろ…それに、めんどくさそうな番犬が側にいたしな…」 「番犬…?」 「番牛かな…くく…」 アレクはふざけて指を伸ばすと、戦友の広い鼻を横から押した。 「…だけど…お前は…いなくなってた…」 「別に?…向こうもあと一年ぐらい中古で我慢できたんだろ…まだ背も伸びてなかったし、声変わりもしてなかったしさ。ちゃんと教わった曲も歌えたんだぜ…最後の方は、女性の部がきつかったけどな…」 「うう…」 「何落ち込んでんだよ。言っとくけど猟のこつとか、馬の扱いとか、武器の手入れとか、すっげぇ色々教えてもらったんだぜ?あれはグリューンリッターの候補入りって意味もあるんだし」 「むぅ…」 「俺はちゃっかりノイッシュの出世を邪魔して、上級騎士たちに顔を売っといた訳だ。だから多少不真面目にやっても将来は安泰なんだよ…だがまぁ…」 騎士の面差しから突然、笑みが抜け落ちて、淡い翳りが浮かび上がる。 「…あの一年前に番牛の横で寝たふりする手を思いついてたら、よかったかもな」 「あの時だって、そうすれば良かったろう」 きつい怒りのこもった声が割って入る。睡みから覚めたノイッシュが身を起こし、眉間に皺を寄せて幼馴染をねめつけた。 「私が寝ていても、アーダンの懐にはまだ空きがあったはずだぞ」 「…いや…」 「私たちじゃお前を守れないとでも思ったのか…」 「別に…守るとか…」 「シアルフィではシグルド様の軍こそが最強だ。俺とお前と、アーダンとで、誰にも負けはしない。あの時だって、グリューンリッターなど返り討ちにできた!」 「…よく言うぜ…あの時のお前なんて、吹けば飛ぶようなちびだったんだからな」 「私は本気だ!」 いきり立って拳を振り上げる騎士を、巨漢が後ろから抱きとめる。 「離せアーダン!こいつには言っただけじゃ分からないんだ!」 「頼むから喧嘩はやめてくれよ…まったく何でお前ら仲良いくせに喧嘩ばっかするんだ…」 「ふふ…何でだろうなぁ?」 アレクが笑いながら見つめると、ノイッシュが急に赤くなる。アーダンは羽交い絞めを解くと、ぽりぽりと頬を掻きながら、二人を交互に見比べて溜息を吐いた。 「もうお前ら二人が結婚しろよ…」 「どっちも女になっちまったんじゃなぁ…戻るとしても同時だろうし…」 緑髪の乙女がぼやくと、山吹の髪の乙女は黙ったまま、挙げた拳を大男の胸板へ打ち付けた。かなりの力がこもっていたが、相手は豪もこたえたようすはない。 「…どちらにしろ、私はお前と結婚すると誓ったんだぞ」 「げ…本気なのかあれ…」 「あれだけ中で出されたら…身籠る…まさか責任を取らないつもりか…?」 「取るよ…取るけど…こんなでたらめな話…うまくいくか…」 「おい!未来の父親がそんな事で立派な騎士が育てられるか!」 アレクは頬杖をついて、仲間のやりとりを眺めやりつつ、ぽつりと呟いた。 「俺も責任とってもらうしかないよな…」 「げ…アレクお前…」 「あんな事して人の過去喋らせといて、今更腰が引けてるのか。ていうか俺も腹がお前の子種でたぷたぷいってるんだが」 「…うお…」 ノイッシュは片眉を上げ、腕組みをして重たい乳房を抱えると、未来の夫を疑わしげに観察した。 「私を奥方にするといったんだぞ…どうするつもりだ…」 アーダンは頬を引き攣らせながら、夜天を仰ぐ。アグストリアの星空は、故郷よりいくらかよそよそしく、冷たく感じられた。 「だって…お前らが同時に襲ってきた…んで…そのどうするとか」 「アーダン!」 「そんな…」 「じゃぁ俺は二号さんでもいいよ。ただし贅沢はさせてもらう。女の着道楽ってのも結構面白そうだからな。あと城が一つと、召し使いも百人はつけて貰うぞ。連れて回って見せびらかせる騎馬の衛士隊もな」 「…私はつつましい暮らしで構わないが、側室の下に立つのは我慢できない。アレクに城と手勢を与えるなら、私はより良いものを貰う。少なくともアレクの隊と戦って勝てるだけの精鋭を揃えてくれ」 「お、お前ら俺の扶持が幾らか知ってるだろ」 「手柄を立てろ」 「出世しろ」 「無茶苦茶言うな!ただでさえ王族でひしめいてる我が軍でどうやって俺が…」 「ミーズ城の将軍は若くても王に信頼されてるそうじゃないか。お前が言ったんだぞ?」 「ト、トラキアの盾みたいになれってのか!?」 「当然だ。私の子供の父親にはそれくらいにはなって貰わないとな」 二匹の牝豹にからみつかれながら、巨漢はひたすら脂汗を流して、未だ明けぬ夜に視線を遊ばせ、この悪夢から一刻も早く覚める事を痛切に願った。 ”司祭よ…司祭よ…起きぬか…” 神のいらだった呼びかけに、庭木の影でうたた寝していた翁が、のろのろと瞼を開いた。老人の隠れ処は、睦み合う若者らの居る場所からそう離れていない。周囲の闇よりなお暗い帷が痩せ衰えた矮躯をすっぽり包んで、存在を気取られぬようにしていたのだ。 「ふぁ…すいません…若い者の体力はついていけませんで…」 ”お前が望んだのだぞ…けりはついた。次へ行かねばならない。まもなく朝だ。我が力は、いささか弱まる。次に居眠りなどすれば発見され、杖を取り上げられて使命を果たせなくなるぞ” 「おお…これは失礼をば…ふむ…アーダンめ意外とやりおる。やはり筋肉は鍛えておいて損はないのう」 ”司祭よ。あのような雑魚どもにこれ以上かかずりあうな…次は…” 「分かっております。エーディン様でございますな!かの御方と近衛の騎士、ヴェルトマーの公子、ヴェルダンの王子の三角関係、不肖この私めが解いて差し上げます」 ”いや、ウルの娘は問題ではない。あれは聖遺物の使い手ですらない。イチイバルは注意すべき武器ではあるが、やはり三剣こそが” 司祭は頷いて後を引き取った。 「皆まで仰いますな。真の問題は神弓に例えられた姫君本人ではなく、三振りの剣、すなわちミデェール卿、アゼル様、ジャムカ様のお三方の争いにあるのです。リジェンダの杖を以て憎しみを愛に変え、ユングヴィ、ヴェルトマー、ヴェルダンの三カ国に繁栄と強い結びつきをもたらしてみせましょうぞ」 ”なぜ話を聞かぬ…” 「聞けば、あの三人、毎朝エーディン様への挨拶に一番乗りしようと先を争っているとか。そこを狙って我が杖の効果で…むむ、老骨、久しぶりに血がたぎって参りましたぞ」 ”これは…人選を誤ったか…” だが神の嘆きをよそに、司祭は黒衣の裾を軽やかに翻し、朝焼けの中を駆け抜ていった。 |
| [小説目次へ] | [次へ] | |
| [トップへ] | ||