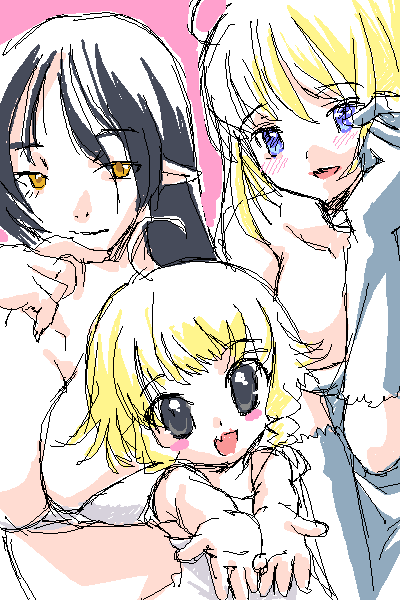 |
|
玉座に腰かけたバズズの股間に、大小三匹の雌が顔を寄せ、熱心に奉仕していた。向かって一番右は、流れる黒髪に金色の竜眼をした婦人で、熟れた果実のような乳房から白露を滴らせ、やや線の崩れた肢体をくねらせながら、年増らしい技巧で鈴口を舐っている。 「んむぅっ♪…おむ…んっ♪」 「やはりヴィルタが一番巧みよな。今宵の種付けは決まりか」 残る二人の口戯が懸命さを増す。左の端で、肉幹に舌を巻き付けるようにしているのは、金髪、細身に形のよい胸をした娘で、すらりとした四肢はどこか少年を思わせる。秘所には生白い未熟な陽根を勃ち返らせ、陰唇からの愛液とともに先走りを滴らせている。双生。男女どちらの性感でも調教できるよう産まれた愛玩奴隷。訴えるような上目遣いをしながら、丹念に雄の印に唾液を塗して磨き浄めていく。 「ふぅっ…んっ…む…ぅふ…ぐっ!…」 「姑には負けられぬという訳かトンヌラ…それほど我が輩の子が欲しいか…穢れたできそこないめが」 最後の一人、まだ四つん這いでは逸物に顎が届かない幼女は、競争相手の豊満な躰に挟まれて膝立ちになり、短い金髪を汗に濡れそぼたせながら、精嚢をしゃぶっている。拙い行為ではあったが、主の愛を得ようとするけなげさはほかに劣らない。ふっくらした頬、平らな胸、丸っこい曲線を描く胴、短い手足は人形のようで可憐だった。 「カリーンは上手になったな。どれ、ほかの二人に孫と曾孫を恵んでやるか…むっ…そろそろ…受け止めろ」 濃い精が飛び散って、美しい三つの顔を汚す。それぞれ舌を突き出して、愛しい男のものを受け止めると、互いの肌についた雫を美味しそうに舐め取っていく。丁度母猫が仔を毛繕いするような優しさで、年嵩の二人がまず、ぎゅっと瞼を閉じた幼女を浄める。次いで黒髪の姑が嫁を綺麗にし、もう一度孫の円かな貌を舐る。さらにカリーンは母を促して、祖母の齢を知らぬ竜顔に舌を這わせた。 「その位でよかろう…さて三人、誰に我がデビル族の戦士を生ませるか…」 「華奢すぎる嫁や孫に強い仔は宿せませんわ。竜王の末裔たるこのヴィルタにお情けを…バズズ様 ♥」 「義母様みたいに外見だけ若い蜥蜴より、産み頃の僕をどうぞ、神鳥の顕現たるトンヌラにお慈悲をバズズ様♪」 「だめだめ!そんなのより、まっさらなはじめてをうばってください。邪神の血族たるカリーンにご褒美を、バズズ様!」 ロンダルキアの太后がややだらしない肢体を床に横たえ、むっちりした太腿を開いて黒い叢を露に誘う。雌竜の麝香が強く香った。王妃は姑に跨がると、しなやかな胴をひねって品を作ると、細い秘具で天を衝きながら、下にある花弁を指で広げて蹂躙を乞う。凝乳のような肌が淡い光沢を帯び、女神の霊威を示していた。祖母と母の前を塞ぐように、あどけない姫宮が背を向けて双臀を突き出し、無毛の恥丘を指で開いて薄紅の粘膜を誘う。童児の昂ぶりを示す粘音が、聖邪ともに混じり合う蠱惑の流し目とともに、妖猿の化身をくすぐった。 「よし!決めたぞ。三匹ともに生ませてくれるわ!そろってぶざまに膨らんだ腹を並べて閨に侍らせてくれる!この懐の広さが憎い!まさに魔族の首魁に相応しい我が輩の度量!」 「ほう…」 氷結湖を吹き渡る冬風よりもなお、聞くものの骨を軋ませる声音が、玉座の裏から響いた。闇の帷から長身の影が現れる。濃紺の大鎧に、凶々しい破壊の剣。まともに向き合えば即、魂を抜かれる美貌に、死より昏い双眸、嘲りを浮かべた唇には殺戮の気配が張り付いている。 「ずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずズィータ様!!!」 勇者にして魔王たる光と闇の司は、ゆっくりとデビル族の長に近付いていく。 「夜中に俺の仕事場で何をしているかと思えば…」 「ご、ごごごごごごごごご誤解でござる」 シドーの騎士がさっと振り返ると、変化の術が解けた三匹のスライムが、互いに顔を合わせて楽しげに飛び跳ねていた。 ”バズズさま、ヴィルタにおなさけ” ”バズズさま、トンヌラにおじひ” ”バズズさま、カリーンにごほうび” 軟体生物の知能では、指示がなくなると教え込まれた台詞を繰り返すしかないのだ。 「ほう…何が誤解だ?ん?」 ズィータは驚くほど上機嫌に微笑みながら、愛用の武器を高く掲げた。バズズは歯をがちがち鳴らしながら、普段、計略を練る際に百倍する疾さで頭を働かせた。 「これはその!ズィータ様がハーゴンの残党の幻術にかかって誘惑を受けた場合を想定した予行演習でして!」 「ほう…面白いな。嗤えるぞ中々」 「ひいいっっ」 ロンダルキア王はにっこりすると、刃を下げて、背後を振り返った。 「アトラス!」 「お呼びで」 眼帯を付けた髭もじゃの巨漢がぬっと頭を出す。裁きを待つ赤髪の青年は、恐怖と困惑の篭もった視線を同僚に向けた。 「こいつをただ殺してもつまらん。自分の行いの意味をよく分からせてやらんとな。姦れ」 「承知」 「い、いやあああああああああああああ!」 巨人の移し身は、丸太のような大腕で妖猿の変化の喉を捕えると、易々と洋袴を裂いて、引き締まった下半身を剥き出しにする。次いで冗談のように太く長い剛直を露にし、硬い尻にあてがった。 「死ぬ!死ぬ!絶対死ぬ!」 「これも宿命…ベリアルによろしくと伝えてくれ」 めりめりと音を立てて巨根が括約筋を広げていく。アトラスの容赦ない挿入に、バズズははらはらと涙を流しながら、悲鳴を迸らせる。 「アッー!!!!」 真黒に暗転する脳裏に、薔薇の花弁が一枚、ひらりと舞い落ちる絵が浮かんだ。 ”ウキー!!!!!!!” 絶叫とともに跳ね起きたバズズは、左右に添い寝する二匹の姉から裏拳による制裁を受け、また床に沈んだ。滝のような冷汗を掻きながら、手を枕の下に差し入れて、忍ばせておいた古い写本を抜き取る。”ゾーマの書”の断片。眠りのうちに帝王の栄光を垣間見られるとの伝説に惹かれて試したのだが、とんだ悪夢を押し付けられた。 ”と、途中までは…すごく…よかった気がするが…” またデビルロードたちに両脛を同時に蹴られて、痛みに眉を顰めながら黙り込む。 いや、内容ははっきり覚えていないが。己の真の望みではないはずだ。シドーの騎士にして魔族の領袖たるデビル族の長が、穢れ者を求めるなどあるはずがない。まして初潮を迎えたかも定かでない、あどけない幼女や、苦難の末に里帰り叶い、美しさと健やかさを蘇らせた尊ぶべき竜母に欲情するなど、あるはずがないではないか。 とりあえずこの不埒な羊皮紙の束は、明朝にでも焼き捨てようと、妖猿は臍を固めたのだった。 |
| [小説目次へ] | [次へ] | |
| [トップへ] | ||