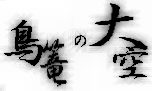300Hit自爆記念小説
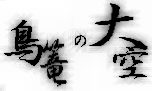
此処の空気は何て重たいのだろう。
一歩も外へ出る事を許されず。
訪れるものもほとんどいない。
一日3回、決まった時刻に転送されてくる食事と、中庭から見上げた空を運行する太陽だけが、刻を知るすべで。
此処の時間は止まっているかのように、静かだ。
神殿とは名ばかりの、この牢獄に入れられて、もうどれだけの時が過ぎたのだろう。
近頃では、「歌」を強要されることもなくなった。
本当に、声が出ないからだ。
「歌」は強要されなくなったが、アイツは此処へやってくる。
俺をいたぶるのが楽しいのだ。
悲鳴も罵声も上げられない俺を、好きなように弄ぶ。
俺が気絶するまで抱きたいだけ抱いて、放り出して帰っていく。
恨み言一つ、言う事も出来ない。
夜は眠れず、やっと眠れたと思ったら夢を見る。
あれからきっと長い時間が経ったはずなのに、毎日のように夢を見る。
紅い夢だ。
全てを失った瞬間の、真っ赤な夢。
俺は夢の中で泣き叫んでいる。
けれど目が覚めてみれば、喉はひゅうひゅう鳴るばかりだ。
今日も同じ夢を見て飛び起きた。
途中までは幸せな夢なのに、真っ黒なアイツが現れて、夢は真っ赤に染まる。
ぼんやりとしながら、中庭で空を見ていた。
無機質なこの場所の中で、唯一緑色の場所。
遠い遠い青空。一日に数時間しか差さない太陽。
思い出すのは、幸せな日々。
二度と戻れない、美しい日々。
目を閉じて、このまま空気に溶けて消えてしまえと願う。
すると、あの人の最後の言葉を思い出す。
「生きろ」という、たった一言が、俺を繋ぎとめている。
哀しい。
哀しい。
けれど、生きなければならない。
例えこの身を仇に汚されようとも。
それがあの人の願い、あの人の思いなら。
鳥篭は絶望を育んでいく。
生きながら死んでゆく。
大空はそこに見えるのに、決して届きはしないのだ。
鳥篭の中の金色の鳥は、そっと静かに目を閉じた。
ウインドウを閉じてお戻りください。
+サーチエンジンなどからこのページにやって来られた方はこちら+